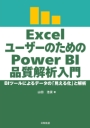中小製造業が部材のリサイクルを最適化するにはどうすればいいのか:あらためて取り組む中小製造業のIoT活用(7)
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。最終回となる第7回は、カーボンニュートラルと同様に製造業が対応を求められているサーキュラーエコノミー(循環経済)で必須となるリサイクルの最適化を図る手順と管理のポイントについて解説する。
前回は、カーボンニュートラルに向けたエネルギー管理の強化を行うために、電力などのエネルギー情報を設備や製品単位に収集しCO2の排出量や削減量の最適化を図る手順と管理のポイントについて解説しました。
今回は、カーボンニュートラルと同様に製造業が対応を求められているサーキュラーエコノミー(循環経済)で必須となるリサイクル管理の強化に向けた、部材のリサイクルの最適化を図る手順と管理のポイントについて解説します。
⇒連載「あらためて取り組む中小製造業のIoT活用」バックナンバー
1.リサイクル管理の目的と強化のポイント
本稿ではリサイクルを「部材の再利用」に位置付けて説明します。金属や樹脂だけでなく加工工程などさまざまな工程で、一度加工した部品を材料に戻して部材として再利用することが可能になっています。製品の品質を確保した上でリサイクルを行う必要があるため、リサイクルを行うには厳密な管理が必要となります。リサイクル管理の強化ポイントとしては以下の3点が挙げられます。
- (1)リサイクルできる材料として正しいか「品番」のチェックをする
- (2)1回の生産ロットの基準量範囲か「使用量」のチェックをする
- (3)使用期限(賞味期限)など利用可能か「期間」のチェックをする
2.リサイクル管理の手順
(1)リサイクル対象の品番の管理
リサイクルを行う品番の情報をマスター情報として整理します。リサイクルする部材は新規利用の部材とは別に品番を付けて管理することが一般的です。その際に使用できる加工品の品番と生産ロットに対するリサイクルできる比率が異なる場合がありますので、それを管理します。品番が変わると1回の生産量の数〜数十%と幅があるのが一般的です。
(2)リサイクル部材の入庫処理
リサイクル部材が発生した場合、リサイクル部材に以下の情報を付与します。
- 品番:リサイクル部材の品番を表す
- 数量:部材の荷姿単位の数量を表す。一般的にはkgなどの重量で表現しているものが多い
- 入庫日:リサイクル部材が発生した日付。年月日表示が一般的
- 使用期限:再生可能な期限を表す。使用期限は部材ごとに異なる場合がある
これらの情報はリサイクル部材が発生した際に表示するため、現品票に明記することになります。後でデジタル的にチェックできるように2次元バーコードなどにこれらの情報を記録して、現品票に印刷すると効率良く管理できます。RFIDを利用する場合は、RFIDの識別コードと現品票の情報をデータでひも付けておき、後工程でRFIDを読んだ際にひも付けた情報を呼び出して利用するとよいでしょう。
(3)リサイクル部材の使用時の対応
リサイクル部材を使用する際に、これから加工する品番と使用するリサイクル部材の現品票の2次元バーコードを読み取り、(1)で整備したマスター情報から以下のチェックを行います。
- 誤品チェック:加工する品番とリサイクル品の組合せが正しいかのチェックをする
- 使用量チェック:加工する品番のロットサイズに対して投入する部材の投入量が基準範囲かチェックする。この場合、荷姿分投入したものと端数で投入したものが発生するため、重量計などと連携して投入量の実測値もチェックする
- 使用期限チェック:現品票の情報から使用期限内かチェックする
上記1.〜3.のいずれかでNGがある場合は、現品票を読み取った時点や投入量の計量時点でエラーを表示して生産ができないようにインターロックをかけるとよいでしょう。
(4)リサイクル部材保管時の管理
(2)でリサイクル部材の荷姿単位の情報に対して入庫日と使用期限が分かるようになっているため、定期的に使用期限切れがないかチェックをします。使用期限になる前にリサイクル品を使い切るように計画を立てることで廃棄ロスを減らすことができます。
これらのリサイクル管理は、製品の品質確保が正しくできているかを確認することを目的としていますが、本来はリサイクルすることでGHG(地球温暖化ガス)の削減につながることがあるべき管理となります。例えば、金属の端材を再度溶かして利用すると地金をつくるときに比べエネルギーの使用量を削減できることから、再生材の活用で資源の有効活用とGHG削減の両面の効果が得られるケースもあります。このような観点でも取り組みを推進していただければと思います。
今回で本連載は終了となります。中小製造業の経営者の方とお話をしていく中で、「IoT(モノのインターネット)導入はDX(デジタルトランスフォーメーション)につながるのか?」といった話がよく出てきます。製造業の現場を見ていると、何となくムダがありそうに感じる箇所はあるが定量的に把握できていないため、改善の余地はあるが改善につながっていない現場が多いと感じます。
その中で品質問題が発生すると、回収作業や再納入および再発防止に追われて経営的なダメージを受けます。日々の生産活動を安定かつ効率的に実施/継続できるからこそ、他社と差別化できて付加価値も見いだされ、それらがDXにつながると説明しています。地道な活動が多いですが、昭和の時代から継続してきた人間力に頼るアナログな管理手法をデータドリブンのデジタルな管理手法に進化させていく取り組みをぜひ継続していただきたいと思います。(連載完)
「ExcelユーザーのためのPower BI品質解析入門」が発売中
本連載筆者の山田浩貢氏が執筆した「ExcelユーザーのためのPower BI品質解析入門」(日科技連出版)が発売中です。
これまでの製造業のデータ分析はExcelが主流でしたが、Excelのみではビッグデータの活用には対応できません。本書ではExcelよりも大量データが扱えるMicrosoftのBIツール(Business Intelligence tool:データを集約、可視化、分析することで、意思決定や課題解決を支援するツール)であるPower BIを使用して、「見える化」から解析といったデータ活用の手順を具体的に解説します。
BIツールによるデータの「見える化」と解析を行うための手順について、QC7つ道具で使用する具体的なグラフサンプルの作成手順を解説しています。書籍購入の方は、株式会社アムイのWebサイトからPower BIの基本データを無償でダウンロードできます。ぜひご一読ください。
筆者紹介
株式会社アムイ 代表取締役
山田 浩貢(やまだ ひろつぐ)
NTTデータ東海にて1990年代前半より製造業における生産管理パッケージシステムの企画開発・ユーザー適用および大手自動車部品メーカーを中心とした生産系業務改革、
原価企画・原価管理システム構築のプロジェクトマネージメントに従事。2013年に株式会社アムイを設立し大手から中堅中小製造業の業務改革、業務改善に伴うIT推進コンサルティングを手掛けている。「現場目線でのものづくり強化と経営効率向上にITを生かす」活動を展開中。
関連記事
- ≫連載「あらためて取り組む中小製造業のIoT活用」バックナンバー
- ≫連載「トヨタ式TQM×IoTによる品質保証強化」バックナンバー
- ≫連載「ラズパイで製造業のお手軽IoT活用」バックナンバー
- ≫連載「品質保証の本質とIoTの融合」バックナンバー
- ≫連載「いまさら聞けないISO22400入門」バックナンバー
- ≫連載「鈴村道場」バックナンバー
- ≫連載「トヨタ生産方式で考えるIoT活用【実践編】」バックナンバー
- ≫連載「トヨタ生産方式で考えるIoT活用」バックナンバー
 中小製造業のカーボンニュートラル、まずはIoTでエネルギー管理を強化せよ
中小製造業のカーボンニュートラル、まずはIoTでエネルギー管理を強化せよ
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第6回は、カーボンニュートラルに向けてエネルギー管理を強化するために、電力などのエネルギー情報を設備や製品単位に収集する手順と管理のポイントを解説する。 IoTで品質管理を強化するための手順と管理のポイント
IoTで品質管理を強化するための手順と管理のポイント
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第5回は、IoTを活用した品質管理の強化に向けて、検査結果や製造条件の収集/分析を行うための手順と管理のポイントを解説する。 設備保全管理をCBMで強化する、PLCデータの収集で設備稼働監視も実現
設備保全管理をCBMで強化する、PLCデータの収集で設備稼働監視も実現
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第4回は設備保全管理の強化をテーマに、金型治工具の使用状況の可視化とメンテンナンス精度の向上を図る手順と管理のポイントを中心に説明し、PLCデータの収集による設備稼働監視や予兆管理についても解説する。 ニワトリが先のアプローチでIoT導入、まずはラズパイで生産管理指標を可視化せよ
ニワトリが先のアプローチでIoT導入、まずはラズパイで生産管理指標を可視化せよ
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第3回は「IoTによる製造工程管理の強化」をテーマに、ラズパイを活用した生産管理指標の可視化手順と管理のポイントについて解説する。 IoT導入の成功とは何か、中小製造業の経営者は何をすべきか
IoT導入の成功とは何か、中小製造業の経営者は何をすべきか
本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第2回のテーマは「IoT導入成功に向けた進め方」だ。経営者が何をすべきかを中心に解説する。 製造業のIoT活用ブームから10年、なぜ中小製造業のIoT導入は進まないのか
製造業のIoT活用ブームから10年、なぜ中小製造業のIoT導入は進まないのか
製造業におけるIoT活用ブームが始まった2015年から10年が経過した現在も、中小製造業のIoT導入はなかなか進んでいない。本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第1回は、連載の狙いと全体像について説明する。 製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ
製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ
高い品質を特徴としてきたはずの国内製造業だが、近年は品質不正や重大インシデントなどの発生が後を絶たない。本連載は、品質管理の枠組みであるトヨタ式TQMと、製造現場での活用が期待されるIoT技術を組み合わせた、DX時代の品質保証強化を狙いとしている。第1回は、その基礎となる「品質保証強化の4つのステップ」について紹介する。 ラズパイで設備稼働情報を「見える化」するための5ステップ
ラズパイで設備稼働情報を「見える化」するための5ステップ
生産現場が特に効率化したいテーマを中心に、小型ボードコンピュータ「Raspberry Pi(ラズパイ)」を使った、低コストかつ現場レベルで導入できる手法について解説する本連載。第1回は、設備稼働情報を収集、蓄積、可視化して現場の改善につなげる、いわゆる「見える化」の方法を紹介します。 日本製造業の品質保証が抱える問題、解決の方向性を示す
日本製造業の品質保証が抱える問題、解決の方向性を示す
2017年後半から検査不正問題や製造不良による事故の発生が相次ぎ、高品質をウリとする日本製造業ブランドを揺るがしかねない状況です。そこで本連載では、これまで日本製造業では品質保証をどう行ってきたのか、品質保証における問題は何かといった点に注目し、問題解決の方策について各種手法や最新技術の活用、組織マネジメント論の面から取り上げます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり
コーナーリンク