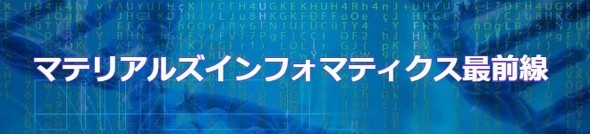MI-6のソリューション 素材開発工数「4分の1」と期間を「10年から半年」に:マテリアルズインフォマティクス最前線(6)(3/3 ページ)
Lab Automationとは?
MONOist Lab Automationはどういったサービスでしょうか。
入江氏 当社の研究開発拠点「横浜ラボ」(横浜市中区)で実験機器を組み立てて、自律的に稼働させる環境を構築し、 Lab Automationのサービス化に向けてパートナー企業とともに概念実証(PoC)を進めている。
Lab Automationのサービスでは、実験データなどを自動で取得できる環境の提供を目指している。というのも、現在はAIの進化により大量のデータを高速で処理できるようになったが、AIがスムーズに読み込めるデータが圧倒的に足りていない。こういった課題を Lab Automationで解消したい。 Lab Automationの目標は、フィジカル空間とデジタル空間をつなぎ合わせ、MIやAIと組み合わせて自律的な開発環境を構築することだ。
当社は現状でも一部装置を遠隔でモニタリングし無人で稼働させられるが、それは使用装置などが限定された特定の系(機器やシステムの構成)でのみ成り立っている。しかし、どのような機器や装置の構成でもラボオートメーションを実現できるサービスでなければスケールアップできない。そういったサービスの構築に向けて研究開発を推進している。
MONOist MI-6が提供しているサービスの特徴や強みについて改めて教えてください。
入江氏 1つ目はベイズ最適化を活用した探索型AIの研究開発に注力している点だ。このAIにより、不確実で少ないデータセットでもMIによる支援が行えるようにしている。2つ目は、150社以上の国内企業にMIを導入した実績から得られたMI推進のノウハウで、幅広い顧客に対応するMI活用の知見が蓄積されている。3つ目はユーザーが使いやすいMIソリューションの開発を行っている点だ。MIソリューションでは、「豊富な機能」「ユーザーのMI成熟度」「ユーザーの体験価値」がトレードオフの関係にある。機能が多いと使わなくなり、少ないとユーザーのMI活用が上達しない。そこで、さまざまな人が扱いやすく満足な体験価値を得られるMIソリューションの開発を意識している。
このように当社では、「システムに人間を当てはめる」という欧米的な思想ではなく、「ツール側が人間に寄り添う」という日本的なアプローチを重視している。
MONOist MI-6のMIサービスを利用している顧客の内訳や導入の効果はどうなっていますか。
入江氏 当社の顧客は、全体のうち半分が素材/化学メーカーで、残りを医薬品メーカー、建設資材メーカー、鉄鋼/非鉄メーカーなどが占めている。この結果から、素材/化学メーカー以外からもMI活用のニーズがある。そのため、今後は「MI」というキーワードが持つ「素材」という限定的なイメージを払拭(ふっしょく)し、MIを広くインフォマティクス技術として捉えさまざまな業界で展開していきたいと考えている。
導入の効果に関しては、素材の開発工数を4分の1に短縮したり、開発期間を10年から半年にしたりとさまざまな成果を創出している。加えて、Hands-on MIによる支援や研修プログラムを通じて、AIやMIの技術を「なんとなく」使うのではなく、「なぜ使うのか」を理解した上で活用できるデータドリブンな文化の醸成に貢献している。
MONOist 今後の展開について教えてください。
入江氏 Hands-on MIなどのMIソリューションに関しては、開発業務で活用できる機能の幅を拡張する。これにより開発者とMIの接点を増やすとともに、素材などの研究開発に関する社内コミュニケーションの活性化を促す。加えて、スペクトルデータなど、対応するデータの種類も増加する。
ラボオートメーションに向けた取り組みでは、実験装置や分析装置からソフトウェアへのデータ連携をシームレスにするデータ基盤の構築を進める。
また、当社は2025年6月に、大阪大学接合科学研究所、日本原子力研究開発機構、松浦機械製作所、古河電気工業、島津製作所、石川県、金沢大学とともに提案した研究開発課題「高付加価値設計・製造を実現する統合型レーザー金属積層造形技術の研究開発」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「経済安全保障重要技術育成プログラム(K-Program)/高度な金属積層造形システム技術の開発・実証」に採択された。
この研究開発では、金属積層造形技術のさらなる高機能化/生産性向上を目指し、設計、造形、後処理の各プロセスを統合的に最適化することを目指している。その中で当社は、MIを活用し、データ駆動型の造形条件最適化やシミュレーション技術の高度化を推進することで、金属積層造形の性能向上と製造プロセスの効率化に貢献している。
こうした取り組みを通じて、金属3Dプリンタにおける造形条件の最適化を支援し、試行錯誤の回数を減らすことで、より多くの人がMIの恩恵を受けられる環境を実現していきたい。
加えて、当社では2025年7月16日にMIに特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」を開催する。MI Conf 2025では、「研究開発DXの更なる加速へ。最前線の実践知、ここに集結」をテーマに、企業におけるMIの取り組みや大学などの最新技術の研究などを発信する。今後もこういったイベントでMIの認知度向上を図る。
関連記事
 積水化学型MIは超やる気人財が主導、配合設計の検討速度900倍など成果も高速で創出
積水化学型MIは超やる気人財が主導、配合設計の検討速度900倍など成果も高速で創出
本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第1回では積水化学工業の取り組みを紹介する JSRや出光はマテリアルズインフォマティクスのプロ人材をどのように育成したのか
JSRや出光はマテリアルズインフォマティクスのプロ人材をどのように育成したのか
本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第4回は、国内化学メーカー向けにマテリアルズインフォマティクスのコンサルティング実績を積み重ねてきたEnthoughtを紹介する。 半年勉強するだけでもマテリアルズインフォマティクスは可能、TBMの挑戦
半年勉強するだけでもマテリアルズインフォマティクスは可能、TBMの挑戦
本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第3回は環境配慮素材「LIMEX」と再生素材「CirculeX」を展開するTBMの取り組みを紹介する。 MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?
MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?
本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第5回は、光学材料部品事業や電子材料部品事業を展開するデクセリアルズの取り組みを紹介する。 SpaceXやAppleに見る、日本のモノづくり力を過去の栄光とした先進の材料設計とは
SpaceXやAppleに見る、日本のモノづくり力を過去の栄光とした先進の材料設計とは
エンソートのマイケル・ハイバー氏が「研究開発におけるAI活用事例:マテリアルズインフォマティクスによる材料探索と製品開発」と題した講演を行い、日本のモノづくり力を超える原動力となりつつあるAIを活用した先進的な材料設計について説明した。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
素材/化学の記事ランキング
- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設
- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調
- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」
- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート
- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発
- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは
- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用
- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど
- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材
- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調
コーナーリンク