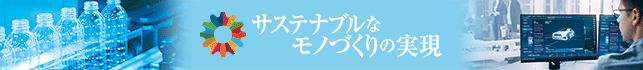デザイナーの登竜門「サローネサテリテ」で活躍する日本の若手3Dプリンタ使いたち:林信行が見たデザイン最前線(2)(3/3 ページ)
マテリアルごとの個性の模索、伝統と革新の融合――アイデアあふれる展示群
前述の通り、今年は2年に1度のサローネ国際照明見本市(エウロルーチェ)の開催年ということもあり、ミラノデザインウィーク全体で照明関係の展示が多く、サテリテに出展していた日本人デザイナーの間でも照明作品の出品が目立っていた。
その中でも、面白かったのがアルミからレザー、ヘチマ、れんがまで、さまざまなマテリアルの“照明器具としての可能性”を探っていたATSUSHI SHINDO(進藤篤)氏の展示だ。
メインの展示は、着物の羽織りに着想を得た「HAORI」という作品。布状の素材を巻いた羽織りを思わせる自立するシェードの襟の部分に棒状のLEDを取り付け、それぞれのマテリアルの反射が生み出す光の表情の違いを楽しめるようにしたものだ。メッシュ状のアルミ、世界的ブランドでもある「神戸ビーフ(神戸牛)」の皮革素材「神戸レザー」、さらには老舗染色加工会社「セイショク」が提案する布をアップサイクルした素材のバージョンを用意していた。
 画像5 「HAORI」を中心とした進藤篤氏の展示。記事中で紹介した照明作品の他に、腐らず保存できるハチミツをインテリアとして飾れるようにした作品や、そのインテリアをモチーフにした照明なども展示していた[クリックで拡大](撮影:筆者)
画像5 「HAORI」を中心とした進藤篤氏の展示。記事中で紹介した照明作品の他に、腐らず保存できるハチミツをインテリアとして飾れるようにした作品や、そのインテリアをモチーフにした照明なども展示していた[クリックで拡大](撮影:筆者)さらに「LOOF」という照明では、かつてたわし作りなどにも使われ、現在では需要も生産量も落ちているヘチマを材料にしたシェードを採用し、人と自然とのつながりを表現していた。
一方、温かいオレンジ色の光をともす「DIG-DUG」は、れんがを用いた照明となっている。織部製陶の独自技術「クレイマイスター」と呼ばれる手法が用いられており、形成した陶土を48時間乾燥させた後、全長50mの連続窯を通し、1320℃の高温還元焼成炉で48時間かけて焼き上げることで独特の風合いを生み出している。そして、その表面に酸化鉄を直接塗り込むことで、より豊かな赤色の光をともらせるようにしたという。
その他、展示会場では、話題の生成系AI(人工知能)を使った作品も見られた。デザイナーの山澤英幸氏は、AIが生成したチェアのデザインを、和紙に糊漆(のりうるし)などを塗って成形する「紙胎(したい)」という技術でアップサイクルしたボール紙を用いて実現していた。これは“再創造される生命”をテーマにした作品だったが、最新のAI技術と組み合わせ、伝統工芸技術である漆芸(しつげい)が再創造されている点も大変興味深いものだった。
 画像6 山澤英幸氏の展示ブース。紙に「紙胎(したい)」という技術を施し、アップサイクルして作ったチェアや再生素材から作った樹脂を用いて製作した色のグラデーションが美しいローテーブルなどを展示[クリックで拡大](撮影:筆者)
画像6 山澤英幸氏の展示ブース。紙に「紙胎(したい)」という技術を施し、アップサイクルして作ったチェアや再生素材から作った樹脂を用いて製作した色のグラデーションが美しいローテーブルなどを展示[クリックで拡大](撮影:筆者)以上、サテリテの展示会場で存在感を放ち、注目を集めていた若手日本人デザイナーの作品やそのコンセプトなどを紹介してきた。最後に、サテリテの展示会場取材のダイジェスト映像をお届けする。一部重複する内容もあるが、記事では紹介し切れなかったブースも取材しているのでぜひご覧いただきたい。
関連記事
 A-POC ABLE ISSEY MIYAKEとNature Architectsが織りなす革命的なテキスタイル成形技術
A-POC ABLE ISSEY MIYAKEとNature Architectsが織りなす革命的なテキスタイル成形技術
イッセイ ミヤケのブランド「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」とベンチャー企業のNature Architectsがファブリック製品の全く新しい製造技術を共同開発し、ミラノの旗艦店でプロトタイプを披露した。現地取材の模様をお届けする。 超大型3Dプリンタを製造現場へ、コミュニティー主導型モノづくりで挑戦を続けるExtraBold
超大型3Dプリンタを製造現場へ、コミュニティー主導型モノづくりで挑戦を続けるExtraBold
欧米が中心で、日本は大きなビハインドを負っている3Dプリンタ業界において、ペレット式の超大型3Dプリンタという変わった切り口で市場参入を目指すExtraBold。同社が発表した大型3Dプリンタ「EXF-12」は、FDM方式3Dプリンタを単純に大型化したものではなく、一般の製造ラインで活用されるための工夫が随所にちりばめられているという。同社 代表取締役社長の原雄司氏に超大型3Dプリンタ開発にかける思いを聞いた。 廃棄された畳のイ草と生分解性樹脂で3Dプリント家具を製作、畳の魅力を次世代へ
廃棄された畳のイ草と生分解性樹脂で3Dプリント家具を製作、畳の魅力を次世代へ
ExtraBoldは、デザインラボ「HONOKA」が手掛ける“廃棄された畳のイ草と生分解性樹脂”を用いた3Dプリント製家具の製作および材料開発を支援したことを発表した。 大型3Dプリンタによる空間装飾の造形サービスで、循環型モノづくりを確立
大型3Dプリンタによる空間装飾の造形サービスで、循環型モノづくりを確立
積彩と光伸プランニングは、大型3Dプリンタを用いて空間装飾などの造形サービスを提供する「空間印刷所」を開始した。3Dプリンティング特有の有機的な什器や空間構造物などを設計、製造する他、造作物を再利用して循環型モノづくりを目指す。 3×3×3mの超大型造形が可能な3Dプリンタでリサイクルプラ製ベンチを製作
3×3×3mの超大型造形が可能な3Dプリンタでリサイクルプラ製ベンチを製作
エス.ラボは、最大造形サイズが3000×3000×3000mmの超大型ペレット式3Dプリンタ「茶室」(開発名)を開発。同時に、慶應義塾大学SFC研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボ、積彩と共同で、茶室と材料にリサイクルプラスチックを用いた大型プラスチック製ベンチの造形にも成功した。 新潟タキザワがExtraBoldの大型3Dプリンタを導入、家具や内装の製作に活用
新潟タキザワがExtraBoldの大型3Dプリンタを導入、家具や内装の製作に活用
新潟タキザワはExtraBoldの大型3Dプリンタ「EXF-12」を導入し、店舗向け家具や内装などの製作に3Dプリンティング技術を活用する新規事業を開始する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
メカ設計の記事ランキング
- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」
- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス
- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援
- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”
- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発
- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!
- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件
- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう
- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」
- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?