カーエレの発展に欠かせない“5つのエポック”:知っておきたいカーエレクトロニクス基礎(2)(2/4 ページ)
第2のエポック 〜シリコン半導体の出現〜
次に筆者が選んだ第2のエポックは「シリコン半導体の出現」です。
先ほど紹介したゲルマニウム半導体の接合温度が80℃、これに対してシリコン半導体の最大接合温度は150〜180℃です。筆者がこの業界に入ったころは、まだゲルマニウムトランジスタが存在しており、基板にはんだ付けをする際は壊れないように細心の注意を払ったものでした(実際、何個か壊してしまったこともありました)。
さすがに、これでは自動車に使用できないなぁ……。そう嘆いていたところに、登場したのがシリコン半導体です。これならはんだ付けで壊れる心配をしなくて済みますし、何より自動車に使える! と喜んだ記憶があります。
これ以外にも、ゲルマニウムからシリコンにすることで得られるメリットがいくつかあります。
1つ目は“資源”の問題です。ゲルマニウムに比べてシリコンの方が資源が豊富です。そのへんにある砂にまじっている白い粒がシリコンですから無尽蔵にあります。2つ目は“熱”に関係します。シリコンの熱の放散性はゲルマニウムの3倍です。この2つを比較すると、ゲルマニウムは熱がこもりやすく、シリコンは冷めやすい特性を持っています。そして、3つ目は“絶縁膜としての酸化膜”の問題です。半導体には外部から守るための絶縁膜や集積回路を作る場合に隣の半導体と絶縁する膜が必要になります。酸化ゲルマニウムは水に溶けやすく、約800℃で分解してしまいますが、酸化シリコンであれば簡単に作ることができますし、水に溶けにくく、1420℃でも分解しません。以上のようにシリコンは、半導体としてまさに理想的な材料といえます。これらの理由から、現在でもシリコンが半導体材料の王座に君臨しているのです。
このシリコン半導体が世に出てから、最初に自動車の機構部品として使用されたのが“オルタネータ用のシリコンダイオード”です。この事例について以下で紹介します。
従来、自動車用発電機は「ダイナモ」と称して、“直流発電機”を使用していました。その直流発電機の原理図が図1です。
界磁により発生する磁界中を電機子巻線(コイル)が回転すると、フレミングの右手の法則により、電機子巻線に起電力が誘導します。ここで、導線Aの起電力と導線Bの起電力は方向が逆になるので、電流の流れる方向が逆になります。
例えば、導線Aからの電流が整流子(コミュテータ)を通りブラシAに流れます。そして、ブラシBから電流が整流子を通って導線Bに電流が流れます。導線Aが回転して導線Bの位置に来ると、導線Aに流れる電流は今度は逆の起電力となり、ブラシBから電流が整流子を通り導線Aに流れます。そして、導線Bから電流が整流子を通りブラシAを通じて流れます。つまり、導線Aと導線Bの回転位置にかかわらず整流子とブラシにより、常にブラシAは+(プラス)、ブラシBは−(マイナス)の出力電流となり、負荷に直流電流が流れることになります。
電流容量の小さい直流発電機の場合、界磁は永久磁石でもよいのですが、普通の直流発電機では、界磁は巻線(コイル)に電流を流して磁界を作ります。なぜなら、その方が強い磁界を作れますし、磁界を制御できるからです。
自動車用発電機の場合は、数十Aもの電流が必要となります。直流発電機のように電機子を回転させてブラシから出力電流を取り出す際、電機子には数十Aの電流が流れます。ここでいう電機子とはコイルのことですから、当然インダクタンスがあります。つまり、前回の点火コイルと同じ原理で、電流切り替え時にブラシと整流子の間で火花が発生します。エンジン回転数が高くなればなるほど同じ電流でも遮断時間が短くなり、火花電圧は高くなりますので、これでは回転数を高くすることもできませんし、高出力化は不可能といえます。
このように、直流発電機では高出力化が実現できませんでしたが、実は“交流発電機”であれば実現可能です。図2に交流発電機の原理図を示します。
直流発電機の整流子の代わりに2つのスリップリングを用いて、各スリップリングにブラシを接触させます。後は直流発電機と同じ原理です。これにより、ブラシの両端には交流電圧が発生します。また、図3の回転子の種類に示すように、交流発電機であれば電機子を固定して、図3(a)のように界磁を回転させても電機子の導線は磁界を横切りますので、電機子の出力に起電力が発生します。
界磁電流は電機子の電流よりも少ないため、スリップリングとブラシの負荷が少なくなりますので高出力が図れます。また、電機子が固定できれば3組の電機子巻線をそれぞれ120度ずつずらした位置に配置することにより、三相交流が得られて脈動が少なくなり、高品質の電流が得られます。図4に三相交流発電機(オルタネータ)の原理図と三相全波整流波形を示します。
実際、この程度のことであれば、直流発電機の設計者は十分理解していましたが、当時は“良いダイオード”がなかったため実現したくてもできない、という状態が続きました。しかし、その後のシリコンダイオードの登場により状況が一変し、晴れて自動車用オルタネータの誕生を迎えたのです。この自動車用オルタネータの実現こそが、カーエレクトロニクスの面目躍如たるところです。さらに、シリコントランジスタもスイッチング回路に大いに使用されたことを考え、筆者は「シリコン半導体の出現」を第2のエポックとしました。
しかし、シリコン半導体を制御回路に使用するには、次のような問題がありました。
アナログ回路の基本といえる“増幅回路”、この増幅回路を担うトランジスタで最も重要な特性は“電流増幅率”です。ちなみに、コレクタ電流ICとベース電流IBとの比を直流電流増幅率hFE(ちなみに、hFEの値は100程度)といいます。このhFEとIBには温度ドリフト(温度により特性が変化する)があります。つまり、周辺温度が変わると出力のIC電流が変化してしまうのです。そのため、帰還(フィードバッグ)を掛けるなどの改良がなされましたが、自動車用の増幅回路としては不十分でした。これに加えて、乗算や除算、微積分のような演算を行うとなるとさらに厳しいものがありました……。(第3のエポックへ)
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 【問題14】 トランジスタでLED点灯(2) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう
- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ
- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】
- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略
- Xilinxの訴訟や3度のIPO延期を耐えたActelは晴れてFPGAベンダーの3位グループに
- インフィニオンのSiCデバイスがトヨタ自動車の新型「bZ4X」に採用
- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得
- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ
- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得
- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定
コーナーリンク
よく読まれている編集記者コラム
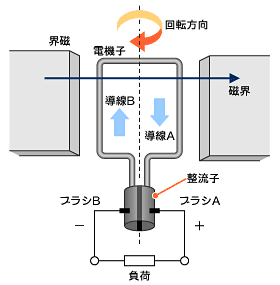 図1 直流発電機の原理
図1 直流発電機の原理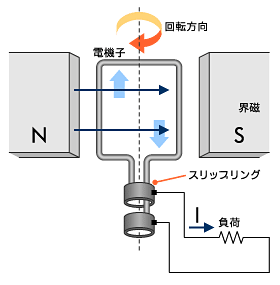 図2 交流発電機の原理
図2 交流発電機の原理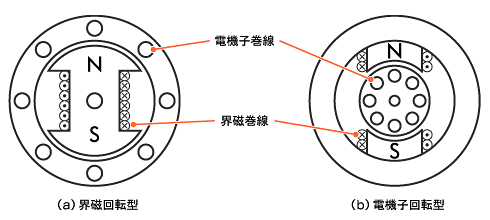 図3 回転子の種類
図3 回転子の種類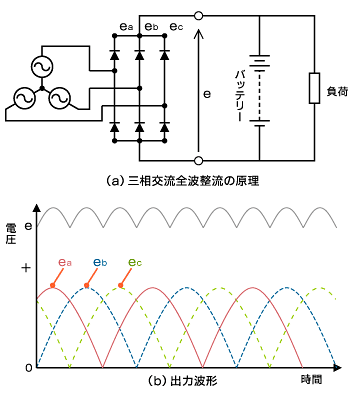 図4 三相交流全波整流の原理と出力波形
図4 三相交流全波整流の原理と出力波形

