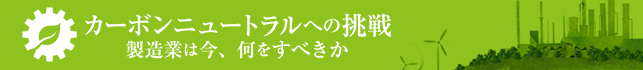バイオディーゼルは「今すぐできるCO2削減」、普及には連携が不可欠:脱炭素(3/3 ページ)
商用車の目線
商用車は用途に応じて汎用から専用まで、架装物による仕事から人や物の輸送まで、多様なラインアップがある。そのため商用車の脱炭素化も車両のサイズや使い方、市場動向に応じて最適な動力源や燃料を選ぶマルチパスウェイで対応が必要だ。電気や水素、カーボンニュートラル燃料を供給するインフラの整備も不可欠。
いすゞ自動車は2023年4月にカーボンニュートラル戦略を推進する統括部門を新設し、カーボンニュートラル燃料の使用に向けた評価や検証を全社横断で実施している。性能評価、耐久性評価、ハードウェアの仕様検証などを行う。
カーボンニュートラル燃料は、ディーゼルエンジンと併せて脱炭素社会の実現に有効なコストミニマムな手段だと位置付けている。HVOは軽油と同等のエネルギー密度や取り扱いが可能で、商用車を使う上での利便性に影響がなく、電動車と比べて導入ハードルは低い。既販車でも利用できる。いすゞは2014年からユーグレナとの協力を継続しており、自社の通勤バスでHVO混合燃料を利用してきた。藤沢工場で2台、栃木工場で1台のバスが運用されている。HVO51%の燃料を使用している。
燃料メーカーの目線
ユーグレナは、会社名と同名のミドリムシ(微細藻類)を5つのF(食料、繊維、飼料、肥料、燃料)に活用することに取り組んでいる。2018年には研究開発用プラントを設置してバイオ燃料の商用化に取り組んできた。2021年にはユーグレナのバイオジェット燃料でホンダジェットが飛んだ。
ユーグレナ エネルギーカンパニー 上席執行役員/カンパニー長の新田直氏はバイオジェット燃料で航空機が飛んだ回数について、2021年時点ではグローバルで34万3276回だったのに対し、日本は5回だったと紹介した。直近では世界で88万回まで増加したが、日本は伸び悩んでいる。
陸のモビリティのバイオディーゼルは、欧州で普及が進んでいる。軽油への混合ではない100%HVOがガソリンスタンドで給油でき、イタリアのENIが1200カ所のガソリンスタンドを展開している。
100%HVOの価格はイタリアでは1l(リットル)350円程度。300円ほどの通常の軽油と比べても価格差は小さい。欧州では2022〜2024年に100%HVOのステーションが5倍に増加した。北欧とイタリアで普及が早かったが、2024年にはドイツとフランスでも使用が許可された。HVOの小売価格は軽油と同等か10%増程度に抑えられている。
日本では税制上HVO100%のバイオディーゼルで公道を走るのは難しいため、51%混合が最大量となる。ユーグレナが提供しているHVO51%混合軽油が「サステオ」だ。国内規格では軽油として扱われるが、サステオで走るクルマは改正省エネ法において輸送事業者や荷主が非化石エネルギー車として報告できる。事業者はEVやFCVを導入するのと同じ効果を得られる。
ユーグレナは現在、マレーシアでの大規模な商業プラントの建設に向けて投資を最終決定した。ユーグレナを含む3社の合弁事業で、同社は15%を出資している。ここで生産したHVOやSAFなど10万kl(キロリットル)は日本向けに輸出したい考えだ。マレーシアのバイオ燃料プラントは、コストや技術面の理由でミドリムシではなく廃食油を原料にスタートするが、2030年初めにはミドリムシを原料としたバイオ燃料を生産したい考えだ。
燃料供給の目線
サステオを含むバイオディーゼルは日々のCO2排出削減だけでなく、災害など非常時の備えにもなるとアピールするのは平野石油だ。
平野石油は自社ローリーでは関東、関西、九州に、提携会社も含めると全国に燃料を配送する企業だ。サステオも提携会社との協力で全国配送が可能で、建築、土木、物流、自治体などから引き合いが増えているという。小型ローリーを活用した少量配送を行っており、地下や高層階での給油や、災害地への配送にも対応してきた。
軽油はガソリンよりも引火点が高いため安全で、比較的取り扱いやすい。運搬可能な数量や容器などの制限はガソリンより軽油の方が緩やかだ。また、消防署に届け出不要で保管可能な量も軽油の方が多い。そのため、200l(リットル)未満であれば消防法の適用を受けずに簡易給油機を事業所などの敷地内に置くことができる。
平野石油はBCP(事業継続計画)対策となる簡易給油機を提案している。タンク容量は190l(リットル)で、軽油に該当するバイオディーゼルでも利用可能だ。190lの軽油があれば、燃費が18km/lのクルマで東京/福岡間を3.8往復するか、50kVAの発電機で20〜30人程度のオフィスが79時間稼働することができる。日常的に使用した燃料は給油機に補充されるので、常に新しい燃料を備蓄することにもなる。
災害発生後、燃料の輸送は24時間以上止まる可能性がある。実際に東日本大震災では東京都内で大渋滞が発生し、震災発生後24時間は平野石油のタンクローリーの平均速度は時速1kmだったという。エネルギーが確保できるまでどのような手段で生活や事業をつなぐかが重要で、ディーゼル車と発電機の両方で利用できる軽油は、BCPにおいて現実的かつ確実な選択肢だとしている。
関連記事
 自動車メーカー3社でエンジンの重要性を宣言、仕入先へのメッセージ
自動車メーカー3社でエンジンの重要性を宣言、仕入先へのメッセージ
トヨタ自動車とSUBARU、マツダはカーボンニュートラルの実現と電動化に対応したエンジン開発の方針を発表した。 大林組が建機に使い始めた「リニューアブルディーゼル」とは?
大林組が建機に使い始めた「リニューアブルディーゼル」とは?
出光興産と大林組、松林はCO2削減効果の高いバイオ燃料「出光リニューアブルディーゼル」を使う実証実験を開始した。出光興産としては初めてリニューアブルディーゼルを取り扱う。 日産の燃料電池が定置用でトライアル開始、使用するバイオ燃料も確保
日産の燃料電池が定置用でトライアル開始、使用するバイオ燃料も確保
日産自動車はバイオエタノールから取り出した水素で発電する定置型の燃料電池システムを開発し、栃木工場でトライアル運用を開始した。使用するバイオエタノールは、スタートアップ企業のバイネックスと協業して確保する。 「これはCSR活動ではない」、スズキが取り組む牛糞由来のバイオガス
「これはCSR活動ではない」、スズキが取り組む牛糞由来のバイオガス
スズキは「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」において、天然ガスとガソリンのバイフューエル仕様のインド市場向け「ワゴンR」を展示した。 トヨタの水素エンジン車が走った「スーパー耐久」ってどんなレース?
トヨタの水素エンジン車が走った「スーパー耐久」ってどんなレース?
S耐(エスタイ)と呼ばれるレースカテゴリーが日本に存在する。正式名称は「スーパー耐久シリーズ」。「スーパーGT」「スーパーフォーミュラ」と比べるとマイナー感は否めないが、市販車をベースにしたレースマシンで戦う国内最高峰の耐久レースシリーズとなっている。 次世代燃料、バイオ素材……国内モータースポーツで加速する脱炭素
次世代燃料、バイオ素材……国内モータースポーツで加速する脱炭素
国内で行われている3つの最高峰レースカテゴリー「スーパーフォーミュラ」「スーパーGT」「スーパー耐久」において、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが活発になっている。合成燃料や環境配慮素材の採用、次世代パワートレインの先行投入など、将来に渡って持続可能なレースシリーズの構築をめざす動きが急速に進んでいる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く
- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする
コーナーリンク