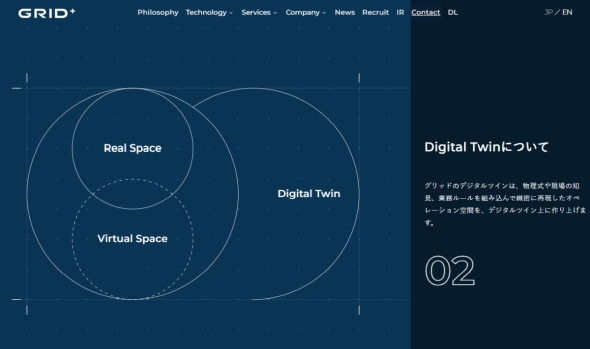AI配船の現場は“レシピ”で進化する――グリッドが語る数理最適化の現在地:船も「CASE」(1/3 ページ)
海運の領域で実用段階に入っているAIを利活用した「配船計画最適化」ソリューション。早期から取り組みを進めてきたグリッドの開発担当者に、AI配船導入の現状や積極的な導入が進むようになった理由、技術的アプローチに関する最新動向について聞いた。
AI(人工知能)を利活用した「配船計画最適化」ソリューションが、海運の領域で実用段階に入っている。その中心的存在が、数理最適化技術を用いて多業種の計画業務を支援してきたグリッドだ。同社は、2025年に入って太平洋セメントや日本郵船など、荷主と海運オペレーターのそれぞれで新たなプロジェクトを展開している。
日本において早い段階から海運業界に向けてAI利活用ソリューションを展開している同社の開発現場を率いるグリッド エンジニアリング第1部 DS第3グループ グループリーダーの宮本年男氏と製造・運輸領域担当エグゼクティブの尾脇庸仁氏に、AI配船導入の現状や積極的な導入が進むようになった理由、技術的アプローチに関する最新動向について聞いた。
半導体の進化が「AIで解ける問題」を広げた
以前取材したときは「ICTを説明することがまず大変」という状況だった海事関連企業でICTどころかAIの利活用ソリューションの導入が活発になっている。
宮本氏はその理由を「AI配船の導入が増えているのは、単純に“解ける問題が増えた”から」と明快に説明する。その上で、「要因は3つある。第1にCPUやGPUの計算性能向上、第2にソルバー(最適化計算エンジン)の改良、そして第3にクラウド環境の一般化が挙げられる」(同氏)という。
「10年前は解を出すのに何時間もかかっていた複雑な組み合わせ問題が、今では現実的な答えが得られるようになってきたものもある。クラウドで誰でも高性能演算環境を使えるようになったことも大きい」(宮本氏)
加えて、経営層がDX(デジタルトランスフォーメーション)やAIに対して積極的になったこと、業界全体で属人化解消の必要性が共有され始めたことも普及の後押しになっているという。
グリッドが自分たちのソリューションを「AI」と呼ぶとき、それはこれまでの認識にある一般的な機械学習とは異なると説明する。
「われわれのやっているAIによる最適化は、過去のデータを学習してパターンを見つける、いわゆる統計的AIではない。それとは根本的に違っている気がする。業務上の制約条件と目的を全て数式で定義し、その上で最も良い解を導き出すという考え方だ」(尾脇氏)
港湾のバース割り当てから喫水制限、積載重量、契約スケジュール、燃料コスト、天候など、配船計画に関わる膨大な要素を「数式化」し、目的関数(例えばコスト最小化や利益最大化)を設定する。グリッドのAI利活用ソリューションでは、数式で設定した制約下で最も良い解を探索する。「シミュレーションも同じ枠組みで実行できる」(宮本氏)と言うように、条件を変えた演算を繰り返すことで、現場が選択肢を比較検討する基盤も提供することになる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く
- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする
コーナーリンク

 グリッドの海事関連ソリューションの開発をリードする同社 エンジニアリング第1部 DS第3グループ グループリーダーの宮本年男氏(右)と製造・運輸領域担当エグゼクティブの尾脇庸仁氏(左)
グリッドの海事関連ソリューションの開発をリードする同社 エンジニアリング第1部 DS第3グループ グループリーダーの宮本年男氏(右)と製造・運輸領域担当エグゼクティブの尾脇庸仁氏(左)