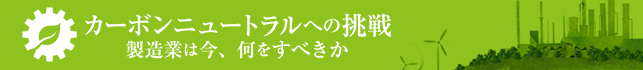バイオディーゼルは「今すぐできるCO2削減」、普及には連携が不可欠:脱炭素(2/3 ページ)
乗用車の目線
自動車のライフサイクル全体のCO2排出を見ると、使う段階での排出が全体の90%を占める。Well to Wheel(燃料の採掘からタイヤの駆動まで)の観点でのCO2削減が自動車メーカーの使命だという。また、日本のCO2排出量の内訳のうち20%運輸部門が排出源で、運輸部門が排出するCO2の80%以上が自動車だ。運輸産業で自動車が果たすべき役割は大きいとしている。
自動車の脱炭素化にはいくつかの組み合わせがあり、カーボンニュートラルに製造された水素とFCV、カーボンニュートラルな電力とEV、カーボンニュートラルな燃料とHEVやPHEV(プラグインハイブリッド車)が考えられる。マツダもマルチパスウェイ、マルチソリューションで取り組んでいる。
マツダ 取締役専務執行役員兼CSO カーボンニュートラル推進統括補佐の小島岳二氏は、次世代バイオディーゼル燃料であるHVOは今すぐCO2削減が可能な燃料だと説明した。
車格の近いEVとHEVで比較した場合、EVは製造時のCO2排出量が多いが、走行距離が10万kmあたりからCO2排出削減に貢献するという。HEVの燃料にHVOを使った場合は、燃料を使い始めてすぐCO2排出が削減できる。
また、5年間のリースでEVとHVOを使うHEVのコストを比較した場合、充電器や給油器など設備投資や電気代/燃料代を含めて同等の価格になるとしている。ただ、日本で利用可能なHVO51%混合の軽油は通常の軽油に比べて2〜3倍とコストが高い。需要拡大によって燃料のコストが下がれば、EVよりも経済的な脱炭素化の手段になり得る。
ただ、燃料を供給する事業者は需要が見込めなければ投資できず、需要側も価格が下がらなければ利用し続けるのは難しい。このジレンマを打破するため、地域や業界の連携による需給拡大や供給網の構築に関する課題の解決にマツダは取り組んでいる。一時的な負担を許容できる仲間を集めて供給網の構築を目指す。
マツダは生産拠点のある広島において、部品や完成車を輸送するトラックのCO2排出削減に向けて、中国経済連合会の中国カーボンニュートラル燃料推進部会での協議に参加している。物流など複数の業界とHVOの利用拡大を目指す。
関東では、ユーグレナが製造した次世代バイオディーゼル燃料を平野石油が輸送し、三井住友銀行の社用車で利用するという連携に取り組んでいる。車両はマツダが提供した。軽油はガソリンに比べて揮発しにくいため、事業所に簡易給油機を設置できる。災害時に自家給油することも可能なため、脱炭素化とBCPの両面で有効性を見込んでいる。
乗用車でのHVOの効果
カーボンニュートラルに向けてグリーンな発電に移行する期間は、地域ごとに差があるものの火力発電が残る。火力発電の残る地域でWell to Wheelやライフサイクル全体でのCO2排出を今すぐ削減できるのは、内燃機関の効率向上やHEVによる省エネ、カーボンニュートラル燃料の組み合わせだ。
HVOはエネルギー密度や部材の腐食性がないため、既存のエンジン向けに高い割合で混合して使用できるが、現時点では軽油よりも割高だ。マツダとしては、燃費改善によってユーザーが負担するコストの抑制を目指す。単なるエコカーではなく走る喜びも提供し、軽油と同等の性能を担保しながら、安心してHVOを利用できるようにする。
マツダはマイルドハイブリッドシステムと排気量3.3lのディーゼルエンジンを組み合わせた「e-SKYACTIV D3.3」にHVOを使用し、CO2排出削減効果を検証した。HVOと軽油のどちらを使用しても同等のトルクや出力性能を発揮できる他、クリーンな排ガスになる燃焼キャリブレーションを採用した。耐久試験も実施した。
ライフサイクル全体でのCO2排出量は、条件がそろえばHVO車がEVよりも優れると試算した。EVは製造時のCO2排出が多いが、使用中のCO2排出の増え方は既存のエンジン車よりも穏やかだ。EVの製造時のCO2排出は欧州の平均的な電源と電力使用量を前提にしている。
HVO混合のバイオディーゼルの場合は、HVO比率が51%であれば走行距離24万kmの時点でもEVよりCO2排出が少ない。100%HVOが日本でも使用可能になれば、ライフサイクル全体でのCO2排出はEVよりも大幅に少なくできると見込む。HVO100%であれば、CO2低減率はWell to Wheelで90%と試算している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く
- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする
コーナーリンク