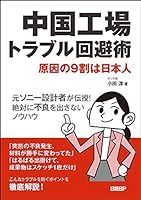量産開始後も続くODMメーカーとの関係:ODMを活用した製品化で失敗しないためには(12)(2/2 ページ)
2.製造ライン監査
製造ラインの監査は、量産開始時に1回と、量産後に定期的に行う。仮に、承認製品とは異なる、すなわち不良品が納品された場合、スタートアップは「承認製品と異なる製品は受け入れないのだから、監査は必要ない」と考えるかもしれない。しかし、最も大きな損害を被るのはスタートアップであることを肝に銘じておくべきだ。
不良品と判断されれば、販売できる製品がなくなり、顧客を失いかねない。さらに、受け入れ段階で不良品に気付かず市場に流出させてしまった場合は、顧客からの信頼を大きく損なうことになる。
こうした損失は正確に金額換算することが難しく、ODMメーカーに費用を請求することも難しいため、実質的に不利益を被るのはスタートアップ側なのだ。
量産開始時に行う監査では、「これから(梱包まで)製造される製品が、適切に組み立てられているか」を確認する。例えば、量産計画を50台/月と決めた場合、量産開始時にいきなり50台を組み立てることはせず、5台と45台などに分けて量産を進める。
その理由は明確だ。作業者はその製品を初めて組み立てるため、作業手順を十分に理解していない可能性がある。また、組み立て作業に使用する装置や工具についても、その製品に対して初めて使用するため、適切な設定値になっていないことが考えられる。
監査は、最初の5台を製造する際に行われることがほとんどだ。そこで仮に不備が見つかり、是正すべき内容が多ければ、その数日後に開始される6台目以降の量産においても引き続き監査を実施し、是正措置の効果を確認する。最初に行われる5台の製造のことを、「量産試作」あるいは「Pre-Production(PP)」と呼ぶ。
主な監査のポイントは、以下の通りである。
組み立て順が適切であるか
組み立て順を記載したQC工程表を入手し、その内容(工程順)に従って製品が組み立てられているかを確認する。量産開始時には、組み立てに使用する各部品に不具合が見つかる場合もあり、その対応として、暫定的な工程が追加されていることがある。また、そもそもQC工程表に沿った順番で工程が完成していないケースや、作業者が自分の作業範囲を理解していないケースも少なくない。こうした不備を発見した場合は、ODMメーカーに対して速やかに指摘し、是正を求める必要がある。
作業方法が適切であるか
各工程の作業標準書を入手し、そこに記載されている作業方法と作業順に従って作業が実施されているかを確認する。作業標準書が存在しない場合でも、実際の組み立て作業を見て、作業方法が曖昧であったり、作業順が決まっていなかったりする場合には、ODMメーカーに是正を求めるべきだ。
作業方法が曖昧であるとは、例えば「ラベルを製品の底面に貼る」といった内容である。製品の底面が広い場合、これではラベルの貼り付け位置が不明確だ。
一方、作業順が決まっていないとは、例えば「ビスを2本留める」といった内容だ。部品の固定用に左右2本のビスがあった場合、これでは右と左のどちらから先に留めたらよいか分からない。一見すると、どちらが先でも問題ないように思えるが、作業順の違いで不良品が発生することはよくある。
筆者自身も、ビスの留め順を指示しなかったことが原因で、不良品を発生させてしまった経験がある。「誰が組み立てても、同じ作業方法/同じ作業順になる」ことが重要だ。
設定値が適切であるか
装置や工具の設定値が適切な値になっているかを確認する。事前に設定値を取り決めている場合は、その内容が作業標準書に記載されているため、装置や工具がその設定値になっているかを実際に確認する必要がある。もし記載されていなければ、記載してもらう。
装置や工具は汎用(はんよう)品であり、他の製品では異なる設定値で使用されていることも多い。そのため、適切な値に設定されていないことがある。
治具が適切に作られているか/壊れていないか
治具には、誰が組み立てても全て同じ製品になるように、部品の位置関係や組み立て方法/手順を画一化する役割がある。しかし、治具の操作次第では、部品の位置関係がずれたり、組み立て方法や組み立て順にバラツキが生じたりする場合がある。こうしたポイントは、監査の立ち合い時に自分で部品を取り付け、組み立ててみると確認しやすい。
量産開始時に行った監査による是正内容を、QC工程表、作業標準書、治具に盛り込んでもらい、6台目以降の量産を開始する。これを「量産」あるいは「MP(Mass Production)」と呼ぶ。
量産フェーズでの監査は、年に1〜2回の頻度で実施し、「(量産試作での監査による是正内容を盛り込んだ)最終的な方法で組み立てられているか」を確認する(図2)。
より細かい監査になると、作業者への教育や5S(整理/整頓/清掃/清潔/しつけ)の実施状況、不良品に対する是正措置の内容などにも踏み込む。それらの内容に関しては、専門書を参考にしてほしい。 (次回へ続く)
筆者プロフィール
オリジナル製品化/中国モノづくり支援
ロジカル・エンジニアリング 代表
小田淳(おだ あつし)
上智大学 機械工学科卒業。ソニーに29年間在籍し、モニターやプロジェクターの製品化設計を行う。最後は中国に駐在し、現地で部品と製品の製造を行う。「材料費が高くて売っても損する」「ユーザーに届いた製品が壊れていた」などのように、試作品はできたが販売できる製品ができないベンチャー企業が多くある。また、製品化はできたが、社内に設計・品質システムがなく、効率よく製品化できない企業もある。一方で、モノづくりの一流企業であっても、中国などの海外ではトラブルや不良品を多く発生させている現状がある。その原因は、中国人の国民性による仕事の仕方を理解せず、「あうんの呼吸」に頼った日本独特の仕事の仕方をそのまま中国に持ち込んでしまっているからである。日本の貿易輸出の85%を担う日本の製造業が世界のトップランナーであり続けるためには、これらのような現状を改善し世界で一目置かれる優れたエンジニアが必要であると考え、研修やコンサルティング、講演、執筆活動を行う。
◆ロジカル・エンジニアリング Webサイト ⇒ https://roji.global/
◆著書
関連記事
 しっかりと把握しておきたいODMに必要な費用
しっかりと把握しておきたいODMに必要な費用
社内に設計者がいないスタートアップや部品メーカーなどがオリジナル製品の製品化を目指す際、ODM(設計製造委託)を行うケースがみられる。だが、製造業の仕組みを理解していないと、ODMを活用した製品化はうまくいかない。連載「ODMを活用した製品化で失敗しないためには」では、ODMによる製品化のポイントを詳しく解説する。第11回のテーマは「ODMに必要な費用」だ。 製品化を目指すなら押さえておきたい、優れた技術やアイデアよりも大切なこと
製品化を目指すなら押さえておきたい、優れた技術やアイデアよりも大切なこと
連載「ベンチャーが越えられない製品化の5つのハードル」では、「オリジナルの製品を作りたい」「斬新なアイデアを形にしたい」と考え、製品化を目指す際に、絶対に押さえておかなければならないポイントについて解説する。連載第1回は、ターゲットユーザーをきちんと想定しておくことの重要性について説く。 何のために製品を市場に出しますか?
何のために製品を市場に出しますか?
連載「ベンチャーが越えられない製品化の5つのハードル」では、「オリジナルの製品を作りたい」「斬新なアイデアを形にしたい」と考え、製品化を目指す際に、絶対に押さえておかなければならないポイントについて解説する。連載第2回は、製品化の際に必要となる志の考え方を取り上げる。 「あうんの呼吸」に頼る日本人の仕事のやり方
「あうんの呼吸」に頼る日本人の仕事のやり方
中国企業とのモノづくりにおいて、トラブルや不良品が発生する原因の7割が“日本人の仕事の仕方”にある。日本人の国民性を象徴する「あうんの呼吸」に頼ったやり方のままでは、この問題は解消できない。本連載では、筆者の実体験に基づくエピソードを交えながら、中国企業や中国人とやりとりする際に知っておきたいトラブル回避策を紹介する。 「言われたことをする」が基本の中国人の仕事のやり方
「言われたことをする」が基本の中国人の仕事のやり方
中国ビジネスにおける筆者の実体験を交えながら、中国企業や中国人とやりとりする際に知っておきたいトラブル回避策を紹介する連載。第2回では、前回の「『あうんの呼吸』に頼る日本人の仕事のやり方」に対して、中国人がどのような国民性を持っているのかを、2つのエピソードを交えて解説する。 「製品化」に必要な知識とスキルとは
「製品化」に必要な知識とスキルとは
自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第1回のテーマは「製品化に必要な知識とスキル」だ。まずは筆者が直面した2つのエピソードを紹介しよう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
メカ設計の記事ランキング
- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」
- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス
- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援
- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”
- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発
- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!
- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう
- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件
- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」
- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?