エアーは悪じゃない、真空を操るシュマルツが描く次の成長図:FAインタビュー(2/2 ページ)
“省力化”に役立つ手動搬送装置にニーズ、適切な製品選択で省エネも
MONOist 社長就任以降の2024年を振り返ってください。
小野氏(以下、敬称略) 2024年は、22年間にわたり日本法人の社長を務めてきたゲッテゲンス・アーネ氏の交代という大きな出来事があった中でも、業績としては掲げていた目標を達成しており、前年と比べても成長している。
自動車関連の受注が安定的に業績を引っ張ってくれた他、われわれの製品はバッテリー工場のフィルム搬送などにも使われており、伸びてきている。パッケージングや物流関連でも引き合いは多い。半導体関連は後ろ倒しになっている。また、製品はユーロで日本に輸入しているため円安が利益を圧迫している他、競合との競争が増している。
勢いがあるのは手動搬送装置の方だ。2024年は医薬、化学の工場向けで伸びたが、幅広い産業でニーズがあると思っている。
従来に比べて従業員の働き方に配慮する企業経営者が増えている。手動搬送装置は、省力化/省人化を実現するだけでなく、重量物を運ぶ際の負担を軽減する、従業員の“ウェルネス”に配慮した製品だ。
MONOist 近年は電動化の潮流もありますが、どのように捉えていますか。
小野 真空を作るために必要な圧縮エアーの消費を減らしたいという声はある。ただ、エアーそのものは悪ではない。最適な製品を使っていただければ、電動化するよりも消費エネルギーを抑えることは可能だ。
例えば、われわれの落下防止弁(チェックバルブ)は吸着していない真空パッドの真空回路を閉じるため、エアー漏れがほとんど起こらない。必要最低限のエアーを生成できる小型のブロワやポンプのラインアップも拡充している。吸着機器がつかめなくなる前に知らせするIoT(モノのインターネット)の機能も開発している。
電動のチャックでは開いて閉じるまでの時間や空間のバッファーが要る。傷や跡を残したくないデリケートなものなど、エアーを使った吸着でしかつかめないものはたくさんある。
最近は、ペットボトルなどでも多様な形状が開発されており、それに伴い搬送する段ボールもさまざまな形状、種類が作られている。それらのハンドリングや自動化をどのように進めればいいのか、生産技術の方が悩んでいる。そういった点で、吸着なら多品種の段ボールを1つのハンドで運ぶことができる。
多品種少量生産が広がる中で、ユーザー側ではロボットのハンドを変えずにいろんなものをつかみたいというニーズがある。そこで3Dプリンタを活用して吸着面を自由に設計できる、オーダーメイド式の真空グリッパーもラインアップした。日本に開発チームがいるため、ユーザーのニーズに合った製品の開発を続けていく。
MONOist 新たにポートフォリオに加わったmGripの特徴を教えてください。
小野 焼き菓子、果物、野菜、肉や魚の直接搬送が代表的なアプリケーションだ。労働人口が減り続けていく中で、食品産業は自動化が大きな課題になっている。食品領域はまだまだ伸び続ける。
シュマルツとしては、アプリケーションの幅を広げて、より幅広い産業で利用されるようにしていくことを考えている。インダストリアルグレードの素材開発を進めており、アプリケーションに応じた低価格ソリューションのポートフォリオ拡充プロジェクトを開始している。
MONOist 今後に向けた抱負を教えてください。
小野 顧客との関係性をより強固にしていきたい。自動車関連では新しいプロジェクトの動きもある。われわれが持つ技術は高く評価されている。顧客に対して、適切な技術を、適切なタイミングで、コンサルテーションも含めてわれわれから提案していきたい。
関連記事
 現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【基本編】
現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【基本編】
本稿では、製造現場や物流業務における重量物搬送の省力化に役立つ助力装置の概要や、導入する際のリスクアセスメントについて解説します。 現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【実験編】
現場/経営の“省力化”に役立つ助力装置とは何か【実験編】
本稿では、助力装置を導入する際のリスクアセスメントについて、体格の異なる2人による作業デモを通して解説します。 クリーンルームで重量物搬送を支援する手動搬送装置、最大100kgまで吸着昇降
クリーンルームで重量物搬送を支援する手動搬送装置、最大100kgまで吸着昇降
シュマルツは、クリーンルームでの重量物搬送を支援する手動搬送ソリューションを発表した。最大100kgまでのワークの吸着と昇降ができる真空バランサーと、ワークを水平移動するジブクレーンで構成される。 隙間があっても吸着搬送、協働ロボットのパレタイジングなど向け軽量ハンド
隙間があっても吸着搬送、協働ロボットのパレタイジングなど向け軽量ハンド
真空機器メーカーのシュマルツは軽可搬ロボットを使用したパレタイジングやデパレタイジング向けの真空グリッパー「ZLW」をリリースした。 自ら移動と充電を行う双腕型協働ロボット、SMC/THK/HDSが合同展示会で連携デモ
自ら移動と充電を行う双腕型協働ロボット、SMC/THK/HDSが合同展示会で連携デモ
SMC、THK、ハーモニック・ドライブ・システムズは「第2回 3社合同メカトロニクスショー」を開催し、3社連携デモンストレーションとして移動型人協働双腕ロボットを披露した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Factory Automationの記事ランキング
- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか
- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送
- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減
- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募
- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進
- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発
- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ
- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成
- サイバー攻撃を“つながり”で守る
- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す
コーナーリンク


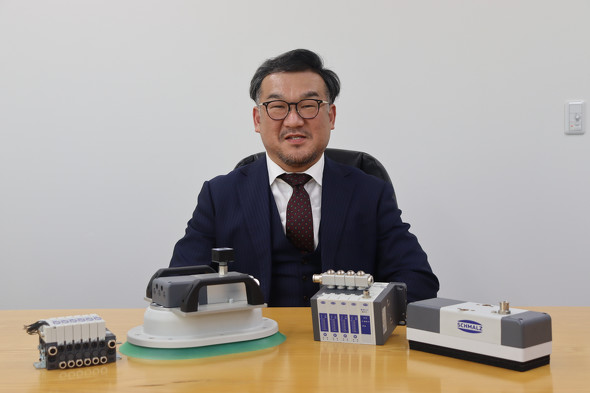 シュマルツ 日本法人 代表取締役社長の小野氏
シュマルツ 日本法人 代表取締役社長の小野氏


