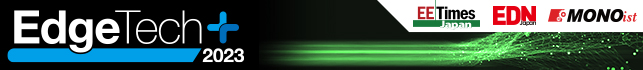ドライバーの認知、判断をそのままアルゴリズムに、市街地の自動運転向けAI:ET2018(2/2 ページ)
ルールベースは最終的に必要
認知と判断はそれぞれ個別にアルゴリズムを開発する。市街地と一言でいっても国や地域ごとに環境が異なるが、大本のアルゴリズムは共通で開発できるという考えだ。「地域ごとに違いは後から分岐させる。また、ルールベースが不要だという考えではない。ルールベースで走行する方が効率がいい場面もある。最終的には判断の制約としてルールを取り入れる必要があるだろう」(アセントロボティクスの説明員)。
このように、AIの学習で道路を実際に走ることに依存しないのが同社の特色だが、開発したアルゴリズムは最終的に実車で検証する。実験車両も自前で用意しているが、この車両はAIが学習するためのものではない。あくまでアルゴリズムの検証用で、道路環境や例外的なシーンの情報を収集する役割も兼ねる。
同社は2020年かそれよりも早い段階で、市街地の自動運転向けのアルゴリズムの開発を終え、自動車メーカーに採用されることを目指す。その中で、学習環境のATLASと実験車両を活用していく。ただ、車両には、カメラやミリ波レーダー、LiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)、温度センサーなどさまざまなセンサーが装着されている。石﨑氏は実験車両について、「高性能なコンピュータと膨大なセンサーで環境を理解している。とにかく全て検知して、そのデータを全部計算処理するのは、量産車として現実的ではない」と捉えている。
今後1〜2年は、より少ないセンサーを基にアルゴリズムの判断を再現し、検証できるかどうかが課題になるという。「脳の働きの便利なところもAIに取り込みたい。例えば人間は、目を向けた方向に聴覚を集中させ、雑音が多くても必要な音を聞き取ることができる。また、運転中のドライバーは常時360度を見ているわけではない。本当に全てを見る必要があるのか、見るべきところはどこかを絞り込んで、演算能力を控えめに抑えても、人間のように運転できるようにしていく」と石﨑氏は述べた。
関連記事
 なぜ“自動運転”の議論はかみ合わない? レベル3とレベル4を分けるのは
なぜ“自動運転”の議論はかみ合わない? レベル3とレベル4を分けるのは
「人とくるまのテクノロジー展2018」の主催者企画の中から、筑波大学 システム情報系 教授である伊藤誠氏の「自動運転」に関する講演を紹介する。 AIをブラックボックスにしないために、“判断の根拠”の解析を
AIをブラックボックスにしないために、“判断の根拠”の解析を
日立超LSIシステムズ 組込ソリューション事業部の猪貝 光祥氏が、NVIDIAのユーザーイベント「GTC Japan 2018」(2018年9月13〜14日)において、AIの品質保証に関する最新動向を紹介した。 ディープラーニングで最適なステアリング制御は実現するか、スバルの挑戦
ディープラーニングで最適なステアリング制御は実現するか、スバルの挑戦
SUBARU(スバル)は、NVIDIAのユーザーイベント「GTC Japan 2018」(2018年9月13〜14日)において、2024年以降の製品化を目指す開発中の自動運転システムについて紹介した。スバル 第一技術本部 自動運転PGMの主査で、開発に携わる小山哉氏が登壇した。 「あそこで曲がって」、乗員の指示に従って走る自動運転車
「あそこで曲がって」、乗員の指示に従って走る自動運転車
アイシン精機と名古屋大学、徳島大学は2018年10月25日、音声や視線、ジェスチャーで操作する自動運転車を開発したと発表した。 自家用車の自動運転は2025年以降? トヨタ奥地氏「NVIDIAでは厳しい」
自家用車の自動運転は2025年以降? トヨタ奥地氏「NVIDIAでは厳しい」
トヨタ自動車 常務役員の奥地弘章氏が、2018年7月20日開催の「CDNLive Japan 2018」で「自動運転技術への取組み」と題する特別講演を行った。自動運転に関するトヨタ自動車の考えや実現へのキーテクノロジー、課題などが紹介された。 GMの自動運転は“都市”で鍛え中、工事現場や信号機故障にも対応
GMの自動運転は“都市”で鍛え中、工事現場や信号機故障にも対応
ソフトバンクグループは2018年7月19〜20日、都内でユーザーイベント「Softbank World」を開催し、基調講演の中でGeneral Motors社長のダニエル・アマン氏が登壇し自動運転技術について語った。 ダイムラーの完全自動運転はNVIDIAの「DRIVE Pegasus」、バッテリーと一緒に水冷
ダイムラーの完全自動運転はNVIDIAの「DRIVE Pegasus」、バッテリーと一緒に水冷
NVIDIAとRobert Bosch(ボッシュ)、Daimler(ダイムラー)は、完全自動運転車と無人運転車に、NVIDIAのAI(人工知能)コンピュータ「DRIVE Pegasus」を採用する。 CPUやGPUと違うデンソーの新プロセッサ、運転中のとっさの判断を半導体で実現
CPUやGPUと違うデンソーの新プロセッサ、運転中のとっさの判断を半導体で実現
「Embedded Technology 2017」「IoT Technology 2017」の基調講演に、デンソー 技術開発センター 専務役員の加藤良文氏が登壇。「AI・IoTを活用したクルマの先進安全技術」をテーマに、同社が取り組む高度運転支援システム(ADAS)や自動運転技術の開発について紹介した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大
- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか
- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート
- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績
- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕
- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」
- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ
- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大
- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ
- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売
コーナーリンク