幾何特性の領域把握がはじめの一歩だ!:製図を極める! 幾何公差徹底攻略(5)(2/2 ページ)
» 2009年07月23日 00時00分 公開
[山田 学 ラブノーツ/六自由度技術士事務所,MONOist]
幾何特性の図示作法
幾何公差は、長方形の枠(「公差記入枠」という)の中に、左から右へ順に記入します。必ず図面を見る向き(水平方向)を基準として配置しなければいけません。矢の引き出し線は、基本的に公差記入枠から水平に引き出した後で直角に折りますが、示す形体が斜面の場合や、穴を正面から見た図形で寸法引き出し線と兼ねて引き出す場合は、直角でなくても構いません。
幾何公差の意図を表すためには、前回のデータムと同様に公差指示線の配置位置により指示領域が異なることを理解してください。
軸線あるいは中心平面を指示する場合
母線を指示する場合
JIS改正によって使えなくなった図示作法
ここでは、以前は使用できたものの、いまはJISの改正によって使用できない図示方法を挙げます。
公差を軸線または共通線、若しくは共通中心平面の形体に適用したとき、このような形体に直接矢を当ててはいけません(図5)。
データム形体と公差記入枠を直接結んではいけません(図6)。
次回は4つに分類される幾何特性のうち“カタチ”を制御する形状公差です。形状公差の特徴は、今回解説したデータムを不要とすることが特徴です。なぜデータムが不要なのか頭の中で十分に理解してください。(次回に続く)
◎併せて読みたい「CAD」関連ホワイトペーパー:
» 主要7製品を完全網羅! 製品選定・比較に役立つ「商用3D CADカタログ 完全版」
» 【導入事例】食品加工機械メーカー不二精機による“3D CAD推進”
関連記事
 最近のJISだと「寸法公差」ではなく「サイズ公差」なのはなぜか
最近のJISだと「寸法公差」ではなく「サイズ公差」なのはなぜか
機械メーカーで3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回はJIS製図における「サイズ」「サイズ公差」「幾何公差」について考える。 「設計から製図までチャレンジしてみよう」の巻
「設計から製図までチャレンジしてみよう」の巻
図面にも触れたことのないような初心者を対象とした、図面の読み方・描き方講座。お題をクリアしながら、解説を読み進めていくことで、いつしか図面の読み描きができるようになる! 今回は、集大成として設計から製図までの一連の作業に挑戦する。 2Dと3Dの融合と、公差設計の重要性
2Dと3Dの融合と、公差設計の重要性
機械メーカーで3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は構想設計から詳細設計までのプロセスを振り返りながら、公差設計の重要性について考える。 設計者必携! 板金設計がマスターできる絵辞書
設計者必携! 板金設計がマスターできる絵辞書
これまでの「甚さんシリーズ」の解説を少し振り返った後、この連載で使うツール「板金設計の50%がマスターできる絵辞書」を紹介する。 いまさら聞けない!? 製図の素朴な疑問たち
いまさら聞けない!? 製図の素朴な疑問たち
「外形線と寸法補助線は接して描かなければならないのか」「φは『パイ』と読むのか」などいまさら聞けない素朴な質問ばかりを集めてみた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
メカ設計の記事ランキング
- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”
- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」
- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結
- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援
- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走
- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス
- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?
- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!
- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件
- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR
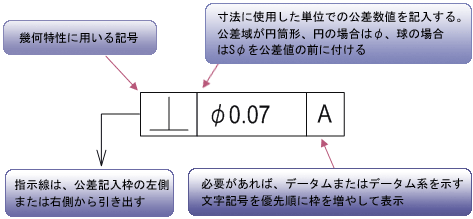 図2 公差記入枠の作法
図2 公差記入枠の作法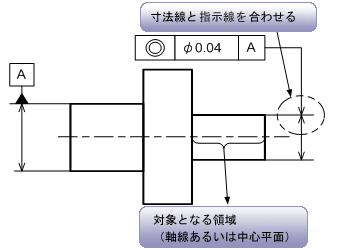 図3 軸線あるいは中心平面指示の例
図3 軸線あるいは中心平面指示の例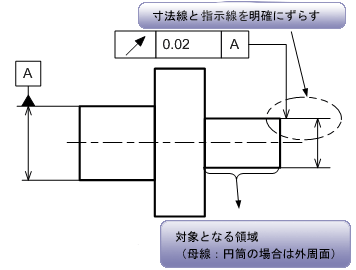 図4 母線指示の例
図4 母線指示の例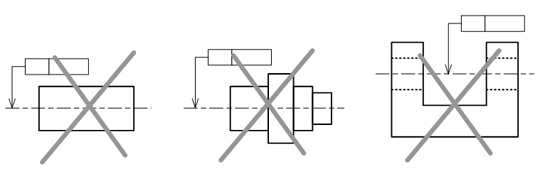 図5 直接矢を当てられない例
図5 直接矢を当てられない例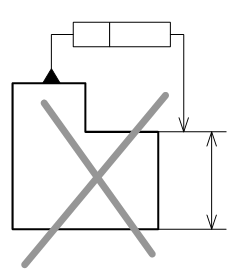 図6 データム形体指示と公差記入枠は直接結ばない
図6 データム形体指示と公差記入枠は直接結ばない






