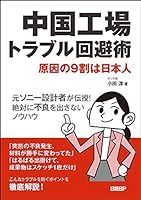試作セットの設計検証(試験や測定)項目の決め方【後編】:ODMを活用した製品化で失敗しないためには(8)(2/2 ページ)
安全性と信頼性の品質レベル
安全規格以外の評価項目は、スタートアップが判定基準と併せて決める。評価項目が少なく判定基準が低ければ、設計期間は短くなり部品コストも安くできるが、その製品の品質レベルは低くなる。逆に、評価項目が多く判定基準が高ければ、設計期間は長くなり部品コストも高くなるが、その分、製品の品質レベルは高くなる。
しかし、初めて製品を作るスタートアップにとって、どの程度の品質レベルにするか、つまりどのくらいの数の評価項目と、判定基準のレベルにするかを決めるのはとても難しい。既に市場にある他社製品の評価項目と判定基準を参考にしようにも、それらは企業機密であるため知ることはできない。よって、相談に乗ってくれるODMメーカーの選定が重要になるのだ(参考:連載第4回「ODMメーカーの種類と特徴、そして選び方のポイント【中編】」)。
品質レベルはスタートアップが自由に決めてよいものではあるが、信頼性も安全性と同じく“壊れやすい”と評判になれば、その製品は売れなくなる。つまり、最終的な判断は市場が行うことを忘れてはならない。また、製品を市場に出した後は、品質に関して市場の意見を聞き、それを次の製品の設計に生かすことだ。これを繰り返すことによって、スタートアップの品質レベルが徐々に定まってくる。
製造性の検証
製造性とは、その製品の製造時に、正しく組み立てやすいことである。正しく組み立てにくい製品は、組み立てミスが生じて不良が出やすい。製造性は、設計で対応すべき内容と、量産する製造(製品の組み立て)で対応すべき内容の2つに分かれる。設計検証で行う製造性の確認は、設計で対応すべき製造性の確認であるため、「正しく組み立てやすいように設計されているか」をチェックする。
この検証は、初めて製品を作るスタートアップにとっては難しいように思えるが、実は簡単だ。試作セットを自分たちで組み立ててみればよいのだ。検証のポイントを以下に列挙する。
- 1)同じ製品の違う部品が取り付かないか
- 2)部品が違う方向で取り付かないか
- 3)部品が常に決まった位置に固定されるか
- 4)1人が両手で組み立てられるか
- 5)人力で組み立てられるか
- 6)手指をケガしないか
- 7)組み立て中に部品が変形/破損しないか
スタートアップの担当者が自ら組み立ててみて、上記に関して何か問題があると感じたら、それは多くの場合、量産が始まってからも同じ問題が発生する。その理由は、量産の作業者だからといって、必ずしも製造経験が豊富とは限らないからだ。どちらかといえば、そのような傾向が強い。よって、見つけた問題点はどんどん指摘するのがよい。
ODMは設計製造を委託することなので、製造で不良品が発生した場合、それはODMメーカーの責任であり、自分たちには関係ないと思いがちである。しかし、不良品が市場に流出してしまえば、たとえその改修費用をODMメーカーに賠償してもらったとしても、製品の供給は滞り、ブランドイメージも著しく低下するなど、その代償は大きい。設計製造委託(ODM)だからといって、ODMメーカーに任せきりであってはならないのだ。 (次回へ続く)
筆者プロフィール
オリジナル製品化/中国モノづくり支援
ロジカル・エンジニアリング 代表
小田淳(おだ あつし)
上智大学 機械工学科卒業。ソニーに29年間在籍し、モニターやプロジェクターの製品化設計を行う。最後は中国に駐在し、現地で部品と製品の製造を行う。「材料費が高くて売っても損する」「ユーザーに届いた製品が壊れていた」などのように、試作品はできたが販売できる製品ができないベンチャー企業が多くある。また、製品化はできたが、社内に設計・品質システムがなく、効率よく製品化できない企業もある。一方で、モノづくりの一流企業であっても、中国などの海外ではトラブルや不良品を多く発生させている現状がある。その原因は、中国人の国民性による仕事の仕方を理解せず、「あうんの呼吸」に頼った日本独特の仕事の仕方をそのまま中国に持ち込んでしまっているからである。日本の貿易輸出の85%を担う日本の製造業が世界のトップランナーであり続けるためには、これらのような現状を改善し世界で一目置かれる優れたエンジニアが必要であると考え、研修やコンサルティング、講演、執筆活動を行う。
◆ロジカル・エンジニアリング Webサイト ⇒ https://roji.global/
◆著書
関連記事
 製品化を目指すなら押さえておきたい、優れた技術やアイデアよりも大切なこと
製品化を目指すなら押さえておきたい、優れた技術やアイデアよりも大切なこと
連載「ベンチャーが越えられない製品化の5つのハードル」では、「オリジナルの製品を作りたい」「斬新なアイデアを形にしたい」と考え、製品化を目指す際に、絶対に押さえておかなければならないポイントについて解説する。連載第1回は、ターゲットユーザーをきちんと想定しておくことの重要性について説く。 何のために製品を市場に出しますか?
何のために製品を市場に出しますか?
連載「ベンチャーが越えられない製品化の5つのハードル」では、「オリジナルの製品を作りたい」「斬新なアイデアを形にしたい」と考え、製品化を目指す際に、絶対に押さえておかなければならないポイントについて解説する。連載第2回は、製品化の際に必要となる志の考え方を取り上げる。 「あうんの呼吸」に頼る日本人の仕事のやり方
「あうんの呼吸」に頼る日本人の仕事のやり方
中国企業とのモノづくりにおいて、トラブルや不良品が発生する原因の7割が“日本人の仕事の仕方”にある。日本人の国民性を象徴する「あうんの呼吸」に頼ったやり方のままでは、この問題は解消できない。本連載では、筆者の実体験に基づくエピソードを交えながら、中国企業や中国人とやりとりする際に知っておきたいトラブル回避策を紹介する。 「言われたことをする」が基本の中国人の仕事のやり方
「言われたことをする」が基本の中国人の仕事のやり方
中国ビジネスにおける筆者の実体験を交えながら、中国企業や中国人とやりとりする際に知っておきたいトラブル回避策を紹介する連載。第2回では、前回の「『あうんの呼吸』に頼る日本人の仕事のやり方」に対して、中国人がどのような国民性を持っているのかを、2つのエピソードを交えて解説する。 「製品化」に必要な知識とスキルとは
「製品化」に必要な知識とスキルとは
自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第1回のテーマは「製品化に必要な知識とスキル」だ。まずは筆者が直面した2つのエピソードを紹介しよう。 一度決めると簡単には変更できない!? 「製品化の日程」を検討する際のポイント
一度決めると簡単には変更できない!? 「製品化の日程」を検討する際のポイント
自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第2回のテーマは「製品化の日程」だ。製品化までの日程は、多くの関係者と調整し、展示会や法規制認証申請などの予定も考慮しながら慎重に検討しなければならない。日程検討の基本的なポイントについて詳しく見ていこう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
メカ設計の記事ランキング
- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」
- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス
- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援
- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”
- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発
- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!
- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件
- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう
- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」
- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走