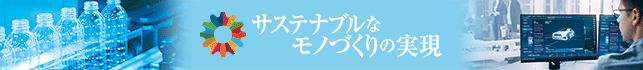3Dプリンタだから実現できた東京五輪表彰台プロジェクトとその先【前編】:未来につなげるモノづくり(4/4 ページ)
延期決定後に量産スタート、7000枚のパネルを約20日間で
だが、無情にもこの直後から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を奮いはじめる。2020年3月にWHO(世界保健機関)がパンデミックを宣言、日本国内でも感染が急速に広がり、同じく3月に東京2020大会の1年間の延期も正式に決定した。
このタイミングで、既にパネルのデータも造形に使用する材料も確定しており、翌月(2020年4月)からエス.ラボの協力の下、12台の材料押し出し方式3Dプリンタによって量産するという段階まで来ていた。このとき、量産をすぐにでも開始できる状況まで準備が整っていたこともあり、表彰台の製作そのものは続行となった。
量産期間は約20日間。この期間内に7000枚のパネルを12台の3Dプリンタで量産する必要がある。当初は、田中浩也研究室に設置してある装置と同じものを12台使用する想定で話を進めていたが、エス.ラボはこのプロジェクトのために装置を新規設計し、1台の装置で3つを同時に造形できる、よりコンパクトな材料押し出し方式3Dプリンタを開発。それを4台並べ、期日内に7000枚ものパネルを見事に作り上げた。
そして、その後は組み立てや装飾などの工程を経て、2020年6月に全98台の表彰台は無事に完成したが、1年後の開催に備えて、そのまま倉庫で保管されることとなった。
そこから約1年が経過した2021年夏、あらためて日の目を見る機会を得た表彰台。田中氏は「オリンピック・パラリンピックのような特別な機会の中で、これまでやったことのない技術や課題に挑戦し、同じ1つのデータから7000枚ものパネルを3Dプリンタで量産できたことを成果として実証できた点は非常に大きな意味を持つ。さまざまなことを同時並行で検証しながら、これらを統合的かつ短期間で実現できたのはやはり3Dプリンタのおかげだ」と表彰台プロジェクトを振り返る。
以上、表彰台を製作するプロジェクトとしては、東京2020大会の開催そのものがゴールとなるわけだが、このストーリーはここで終わらない。次回【後編】では、田中氏が提唱する「リープサイクル(跳躍循環)」と呼ばれるコンセプトと、そこで目指すビジョンについてお届けする。 (【後編】を読む)
関連記事
 3Dプリンタだから実現できた東京五輪表彰台プロジェクトとその先【後編】
3Dプリンタだから実現できた東京五輪表彰台プロジェクトとその先【後編】
本来ゴミとして捨てられてしまう洗剤容器などの使用済みプラスチックを材料に、3Dプリンティング技術によって新たな命が吹き込まれた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)表彰台。その製作プロジェクトの成功を支えた慶應義塾大学 環境情報学部 教授の田中浩也氏と、特任助教の湯浅亮平氏に表彰台製作の舞台裏と、その先に目指すものについて話を聞いた。 コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速
コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速
コロナ禍で、あらためてその価値が再認識された3Dプリンティング/アディティブマニュファクチャリング。ニューノーマルの時代に向け、部品調達先や生産拠点の分散化の流れが加速していく中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、その活用に大きな期待が寄せられている。2021年以降その動きはさらに加速し、産業界におけるデジタル製造の発展を後押ししていくとみられる。 3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目
3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目
単なる試作やパーツ製作の範囲を超えたさらなる3Dプリンタ活用のためには、「造形方式」「材料」「構造」の3つの進化が不可欠。これら要素が掛け合わさることで、一体どのようなことが実現可能となるのか。本稿では“材料×構造”の視点から、2020年以降で見えてくるであろう景色を想像してみたい。 「単なる試作機器や製造設備で終わらせないためには?」――今、求められる3Dプリンタの真価と進化
「単なる試作機器や製造設備で終わらせないためには?」――今、求められる3Dプリンタの真価と進化
作られるモノ(対象)のイメージを変えないまま、従来通り、試作機器や製造設備として使っているだけでは、3Dプリンタの可能性はこれ以上広がらない。特に“カタチ”のプリントだけでなく、ITとも連動する“機能”のプリントへ歩みを進めなければ先はない。3Dプリンタブームが落ち着きを見せ、一般消費者も過度な期待から冷静な目で今後の動向を見守っている。こうした現状の中、慶應義塾大学 環境情報学部 准教授の田中浩也氏は、3Dプリンタ/3Dデータの新たな利活用に向けた、次なる取り組みを着々と始めている。 3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき
3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、サプライチェーンが断絶し、生産調整や工場の稼働停止、一斉休業を余儀なくされた企業も少なくない。こうした中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、あらためて3Dプリンタの価値に注目が集まっている。HP 3Dプリンティング事業 アジア・パシフィックの責任者であるアレックス・ルミエール(Alex Lalumiere)氏と、日本HP 3Dプリンティング事業部 事業部長の秋山仁氏に話を聞いた。 絶対に押さえておきたい、3Dプリンタ活用に欠かせない3Dデータ作成のポイント
絶対に押さえておきたい、3Dプリンタ活用に欠かせない3Dデータ作成のポイント
3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第4回は、3Dプリンタを活用する上で欠かせない「3Dデータ」に着目し、3Dデータ作成の注意点や知っておきたい基礎知識について解説する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
メカ設計の記事ランキング
- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”
- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」
- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結
- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援
- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走
- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス
- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?
- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!
- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件
- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう