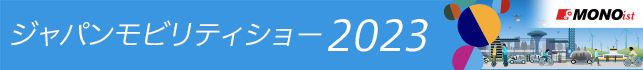「走行距離650kmは足りない」、FCVの新型ミライが目指す安心感:東京モーターショー2019
トヨタ自動車は「第46回東京モーターショー2019」(会期:2019年10月24日〜11月4日、東京ビッグサイト他)において、燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」の次期モデルの開発最終段階を示すコンセプトカーを展示している。
トヨタ自動車は「第46回東京モーターショー2019」(会期:2019年10月24日〜11月4日、東京ビッグサイト他)において、燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」の次期モデルの開発最終段階を示すコンセプトカーを展示している。
新型ミライについては、既にプレスリリースで幾つかの情報が公表された。車両サイズやホイールベース、駆動方式、乗車定員といった諸元値の他、日本や北米、欧州などで2020年末に発売することが明らかにされている。また、燃料電池(FC)システムを一新し、FCVとしての性能を大幅に向上させるとともに、水素搭載量の拡大により、走行距離を従来モデル比で30%増やすことを目標にしている。
ミライは現行モデルであっても、1回の水素充填で650km走行できる(JC08モード)。水素の充填作業が3分程度で終わる点と併せて、ガソリンエンジン車と同等の利便性を実現したとうたってきた。しかし、「水素の残りが少なくなってくると不安だという声をいただいた。理由は水素ステーションの数が少ないからだ。走行距離が少しでも長ければ安心して使ってもらえるのではないか。水素ステーションがないことを理由に諦める人も多いと聞いている。水素ステーションが少ないことを理由に買うのをためらってほしくないので、ネガティブな部分を払拭する」(トヨタ自動車 Mid-size Vehicle Company MS製品企画 ZF 主査の清水竜太郎氏)。
また、新型ミライは前輪駆動から後輪駆動となる点も大きな変化の1つだが、清水氏は「初めから後輪駆動にすると決めていたわけではない」と説明。「現行モデルは良くも悪くもいろいろな意見をいただいており、今回はスタイリングにこだわった。また、現行モデルは4人乗りだったので、5人乗りの普通のセダンとして使ってもらえるようにしたいという思いもあった。そうした中でレイアウトを検討した結果、TNGAの後輪駆動のプラットフォームがうまくはまった。後輪駆動に行き着いたので、これを生かす走りの良さにもこだわっている」(清水氏)という。
乗車定員が4人から5人にできたのも、レイアウトの工夫が効いた。「レイアウトの詳細は新型車として発表するまで言えないが、プラットフォームから見直しているので現行モデルとは変わっている(清水氏)。
トヨタ自動車は新型ミライを普通のクルマとして売り出す。「現行モデルはFCVだから買ってくれる人が多かったが、おカネを払っていただく上で“FCVだから”というアピールは通じない。“いいと思ったクルマがたまたまFCVだった”というくらい、見ても乗っても所有しても喜びのある、クルマ本来の魅力を持たせたい」(清水氏)という。
新モデルではFCVらしさを演出するデザインにはこだわらなかった。現行ミライは、酸素の確保とFCシステム冷却のために空気を取り込む左右のグリルを強調したデザインにより、FCVとしての独自性を象徴するフロントフェースとなっている。「現行モデルのデザインは機能面でも必要な形になっているものの、賛否両論だった。新型ミライでは、冷却性能が向上して現行モデルのようなグリルが不要になったこともあり、FCVらしい形にはしていない」(清水氏)。
関連記事
 トヨタから1年遅れ、それでもホンダは燃料電池車を普通のセダンにしたかった
トヨタから1年遅れ、それでもホンダは燃料電池車を普通のセダンにしたかった
ホンダは2016年3月10日、セダンタイプの新型燃料電池車「CLARITY FUEL CELL(クラリティ フューエルセル)」を発売した。水素タンクの充填時間は3分程度、満充填からの走行距離は750Kmとし、パッケージングも含めてガソリンエンジン車とそん色ない使い勝手を目指した。 FCV「ミライ」が2020年末に全面改良、後輪駆動化、定員は5人に
FCV「ミライ」が2020年末に全面改良、後輪駆動化、定員は5人に
トヨタ自動車は2019年10月11日、「第46回東京モーターショー2019」(一般公開日:2019年10月24日〜11月4日、東京ビッグサイト他)において、燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」の次期モデルのコンセプトカーを初公開すると発表した。日本や北米、欧州などでの2020年末の発売に向けた開発最終段階を披露する。 バイオエタノールで走る日産の燃料電池車、「ミライ」「クラリティ」より低コストに
バイオエタノールで走る日産の燃料電池車、「ミライ」「クラリティ」より低コストに
日産自動車は、バイオエタノールから取り出した水素で発電して走行する燃料電池車のシステム「e-Bio Fuel-Cell」を発表した。圧縮水素タンクや、白金など希少金属を使う触媒を必要としないため、トヨタ自動車の「ミライ」やホンダの「クラリティ フューエルセル」と比較してコストを大幅に低減できる。2020年に商品化する。 2030年のFCV普及見通しは乗用車タイプで1000万台超、FCトラックは50万台
2030年のFCV普及見通しは乗用車タイプで1000万台超、FCトラックは50万台
自動車メーカーやエネルギー産業、重工業の大手企業13社で構成する水素協議会(Hydrogen Council)は、2050年までを視野に入れた水素利用の調査報告を発表した。水素エネルギーの普及によりCO2排出量を現状比で年間60億トン減らすとともに、平均気温の上昇を2℃までに抑える上で必要なCO2削減量の20%をカバーする見通しだ。 電気自動車が後付け部品で燃料電池車に、ベース車両はほぼそのまま
電気自動車が後付け部品で燃料電池車に、ベース車両はほぼそのまま
フランスのSymbio FCellは、「第13回 国際水素・燃料電池展」において、日産自動車の電気自動車「e-NV200」を改造した燃料電池車を紹介した。外部からの充電と水素の充填、どちらでも走行できる。 子ども向けに本気で作った、運転免許なしで乗れる燃料電池車
子ども向けに本気で作った、運転免許なしで乗れる燃料電池車
メガウェブは2015年12月26日から、子どもが自分で運転できる燃料電池車(FCV)「FC-PIUS」を使った走行体験イベントを始める。燃料電池車について正しく理解してもらい、「燃料電池車=水素爆発」といった誤解を解くために、技術者たちが奔走して時間とコストをかけて子ども向けの燃料電池車を開発した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く
- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする
コーナーリンク