最先端テクノロジー×産業特化支援 東大発AIスタートアップ「燈」が照らす道:製造ITニュース
東京大学発のAIスタートアップ企業である燈は、最新テクノロジーを活用して業界特化の業務支援をはじめとした、同社の事業取り組みについて説明した。
燈は2025年10月23日、東京都内で記者会見を開き、事業について説明した。同社は2021年2月に創業した、東京大学大学院工学系研究科 「松尾・岩澤研究室」発のAI(人工知能)スタートアップ企業である。現在は、約360人が会社に在籍しており、平均年齢29.8歳と若い人材を中心とした組織で構成されている。
燈 取締役COO Co-Founderの石川斉彬氏は、「『日本を照らす燈となる』を使命として、これまで事業を展開してきた。テックカンパニーでありながら、古風な良い部分を併せ持ち、昭和的な企業文化を持っている組織でもある。われわれは、AI時代に最先端のテクノロジーで日本産業をアップデートし、世界をけん引する会社を目指している」と語る。
燈は日本最先端の研究開発レベルのAI技術を産業特化のソリューション開発に活用し、企業の生産性の向上に取り組んでいる。建設業界向けサービスの提供から始まり、現在では製造業や物流業などにも事業を展開している。
最先端技術を生かして産業特化のサービスを提供できることが燈の強みである。例えば、1週間前に発表された論文を基にしてプロジェクトの精度を上げるなど、進化が早いAI技術に対応し、独自の研究開発を社内で進めることが可能だ。この高い研究開発力によって生まれた最新のテクノロジーを活用し、モノづくりの各業界ならではのワークフローや専門知識に合わせた、新しい技術開発に取り組んでいる。
現在の燈では、DX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューション事業とAI SaaS(Software as a Service)事業の2つを柱事業として展開している。DXソリューション事業では、顧客要望から2000以上のプランを用意するAI住宅営業ソリューションや、AIを搭載したカメラを取り付けた車両で道路を走ることで道路のひび割れなどの異常を自動で検知してマッピングできるソリューションなどを展開している。
一方AI SaaS事業では、主に業界固有の文化やワークフローに最適化させた生成AIツールをパッケージソフトとして提供している。具体的には、建設業界向け管理業務DXサービスの「Digital Billder」シリーズ、製造業向けAIエージェントサービスの「工/Takumi」など、燈固有のAIモジュールを搭載し、UI/UXを最適に仕上げた業界特化AIサービスを展開している。
「近年では、製造業とのやりとりが増えている。例えば、燈独自のシミュレーション基盤を活用して、工場や建物のデータの3D化を行い、この3Dモデル内で生産ライン配置や人員配置のシミュレーションをしている。実際に稼働しないと分からない部分がシミュレーションで判明し、やり直しなどの余計なコストを抑えることができるソリューションを提供している」(石川氏)。
燈のAI/DXソリューションは「どんなに良いものを作っても、使いこなせなければ意味がない」という考えで技術開発に取り組んでおり、現場で実際に使用してもらって成果を確認し、顧客に喜んでもらう部分までを一気通貫してサポートしている。石川氏は「燈にはカスタマーサクセスチームが存在しており、操作説明に加えてどのように操作したら扱いやすいかという具体的な使い方のサポートをしている。例えば、生成AIの導入時に、業務での使い方が分からない人に向けて、『この業務をする際には、こういう質問文を入力するとこのような回答が出るので、試してみてほしい』といったレベルまで細かい指導をしている」と強調する。
燈は今後、ロボット活用を中心にモノづくり産業のDX/AX(AIトランスフォーメーション)に力を入れていく。そして、モノづくり産業だけではなく、インフラや不動産、金融など社会の根幹を担う分野に事業拡大を予定している。石川氏は「日本を代表するAI会社を目指して、社会問題を解決するソリューションを提供し、"日本の希望の光"になれるように事業を展開していきたい」と述べている。
関連記事
 大学発ベンチャー表彰2025 AIスタートアップの燈が経済産業大臣賞を受賞
大学発ベンチャー表彰2025 AIスタートアップの燈が経済産業大臣賞を受賞
経済産業省は「大学発ベンチャー表彰2025」の受賞者が決定したと発表。東京大学 松尾豊研究室発のAIスタートアップである「燈(あかり)」が経済産業大臣賞を受賞した。 オフィスデータを活用した生成AIの共同開発契約を締結
オフィスデータを活用した生成AIの共同開発契約を締結
イトーキと燈は、生成AI共同開発契約を締結した。両社の強みを生かして、オフィスデザイン自動生成AIと関連したアプリケーションや、瞬時にオフィスデザインをシミュレーションできるアプリケーションを開発する。 国内ERP市場はクラウド化が加速、2025年に25%へ
国内ERP市場はクラウド化が加速、2025年に25%へ
矢野経済研究所は、国内ERPパッケージライセンス市場の調査結果を発表した。2024年の市場規模は前年比12.1%増の1684億4000万円となった。クラウド化が進み、2025年にはSaaSのみの利用が全体の25%を占める見通しだ。 伝えた通りにAIが設計し、3Dプリンタで自動造形 日本発スタートアップの挑戦
伝えた通りにAIが設計し、3Dプリンタで自動造形 日本発スタートアップの挑戦
トコシエが、AIで設計から製造までを自動化する製造プラットフォームの開発企業として、「Techstars Tokyo」に採択された。同社の「モデリング・プロフェッショナルAI」は、設計部品の条件を入力すると、AIが3D CADを操作してモデルを生成し、3Dプリンタで自動造形を行う。 オムロンがインドに共創型オートメーション拠点開設、国内の製造DX促進
オムロンがインドに共創型オートメーション拠点開設、国内の製造DX促進
オムロンは、インドのベンガルールに「AUTOMATION CENTER BENGALURU」を開設した。同センターを通じてインドの製造DXを促進し、同国の生産性や国際競争力の向上を支援する。 中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの
中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの
本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第1回は同プロジェクトのデジタル化の実証実験の概要と、結果について紹介します。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり
- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- AWSは信頼性への投資に注力 フィジカルAI開発を支援する新たなプログラムも発表
コーナーリンク
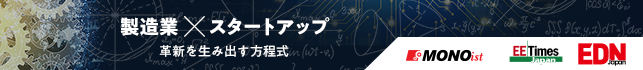
 燈 取締役COO Co-Founderの石川斉彬氏
燈 取締役COO Co-Founderの石川斉彬氏







