FreeRTOSがライバル!? イタリア発のRTOS「BeRTOS」は古のBeOSとは関係ない:リアルタイムOS列伝(50)(3/3 ページ)
2015年にGitHubへ移行、そして現在は……
ちなみにBeRTOS 2.7.99時点での対応ハードウェアは以下のようになっている。
- ARM7TDMI:Atmel AT91SAM7、NXP LPC2XXX
- Atmel AVR:ほとんどのAVR8をサポート(Arduinoを含む)
- Cortex-M3:Luminary Stellaris LM3S、ST Microelectronics STM32、Atmel SAM3
- PowerPC/x86/x86-64:エミュレータ動作
ここでLuminary Stellarisというのは、まだ独立企業だったLuminary Microのことで(2009年にTIが買収)、同社のStellarisシリーズはそのままTIから発売されている。またPowerPCがエミュレータのホストに挙がっているのは、まだ当時はPowerPC MacからIntel Macへの移行の途中の時期に当たっており、製品はともかくユーザーはまだPowerPC Macを使っていたという事情によるものである。
ただそれまでは独立して存在していたBeRTOSのWebサイト(図4)であるが、2015年にWebサイトそのものがGitHubにリダイレクトされるようになり、サポートページやコミュニティーなどに一切アクセスができなくなった。
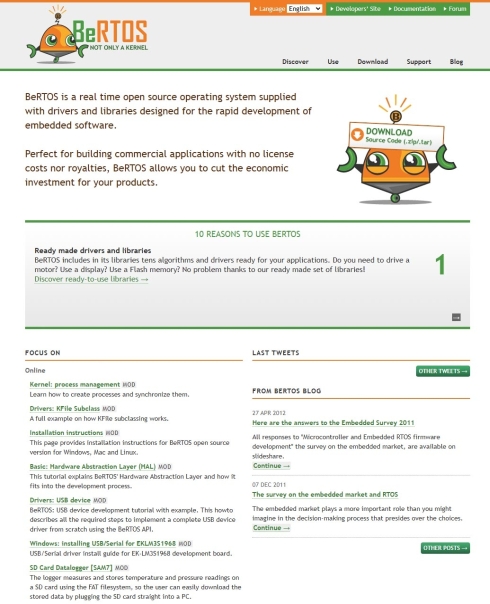 図4 2014年12月30日付のBeRTOSのWebサイト(現在は存在しないためWebアーカイブを参照)。上のロボットがマスコット? ちなみにこれは英語版で、イタリア語版だと“NOT ONLY A KERNEL”が“NON SOLO KERNEL”になっている[クリックで拡大] 出所:Develer
図4 2014年12月30日付のBeRTOSのWebサイト(現在は存在しないためWebアーカイブを参照)。上のロボットがマスコット? ちなみにこれは英語版で、イタリア語版だと“NOT ONLY A KERNEL”が“NON SOLO KERNEL”になっている[クリックで拡大] 出所:Develer元のBeRTOSのWebサイトで提供されていたブログエントリ(現在は存在しないためWebアーカイブを参照)も、2012年4月27日分(現在は存在しないためWebアーカイブを参照)が最後のようだ。そしてGitHubの方も、2018年11月27日にアーカイブされてしまっている。2012年7月のVersion 2.7.99が最終バージョンとなったようで、以来動きはない。
Develerの“Our free projects”のWebサイトの冒頭にBeRTOSは出てくるので、別になくなった訳ではないのだろうが、もうBeRTOS SDKの販売は行われていない(Premier Supportも多分終了しているのだろう)ので、使う場合は普通にソースを落としてきてビルドするという形になる。
GitHubのBranchを見ても、STM32 Nucleo向けのBranchがある程度で、こちらもVersion 2.7.99である。まぁ、Arduinoあたりに入れて遊ぶには手頃なRTOSかもしれないが、もはやそれ以上ではないというのが正直なところだろう。
関連記事
- 連載記事「リアルタイムOS列伝」バックナンバー
 アマゾン買収から2年半、「Amazon FreeRTOS」は最も手頃なRTOSに
アマゾン買収から2年半、「Amazon FreeRTOS」は最も手頃なRTOSに
IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第2回は、アマゾンの買収によってRTOSのメインストリームに躍り出た「Amazon FreeRTOS」について紹介する。 さらば「Mbed OS」、RTOS淘汰の波にはArmも逆らえない
さらば「Mbed OS」、RTOS淘汰の波にはArmも逆らえない
IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第49回は、ついにEOL(End of Life)がアナウンスされたArmの「Mbed OS」について、なぜ淘汰の波に飲まれたのかを考察する。 「RT-11」はUNIXの“/usr”ディレクトリの語源なのか 歴史と機能から検証する
「RT-11」はUNIXの“/usr”ディレクトリの語源なのか 歴史と機能から検証する
IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第48回は、UNIXの“/usr”ディレクトリの語源という説が流れた「RT-11」について、その歴史や機能を紹介する。 DECとともに消えた名機VAX向けRTOS「VAXELN」の栄枯盛衰
DECとともに消えた名機VAX向けRTOS「VAXELN」の栄枯盛衰
IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第47回は、DECがかつて提供していたVAXという32ビットミニコンピュータ向けのRTOS「VAXELN」について紹介する。 FDDからブートできる「MenuetOS」とCPUキャッシュにOSが載る「KolibriOS」
FDDからブートできる「MenuetOS」とCPUキャッシュにOSが載る「KolibriOS」
IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第46回は、フロッピーディスク(FD)1枚にOSとアプリケーション一式が収まる「MenuetOS」と、MenuetOSからフォークした「KolibriOS」について紹介する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開
- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断
コーナーリンク



