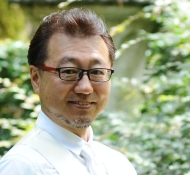カシオがなぜ? ギタリスト向け「音のレシピ」アプリをリリースしたワケ:小寺信良が見た革新製品の舞台裏(37)(3/3 ページ)
音楽におけるオリジナルなど新たな挑戦を支援
小寺 レシピという考え方だと、一般的には著作権が発生しないことになっています。ですが音の場合、特定の楽曲や特定のフレーズがあっての「あの音」だと思います。例えば、誰かが著名人のサウンドを使って「その曲を弾いてみた」的なレシピを投稿した場合、どうなりますか。
川田氏 まず音楽著作権に関して言うと、オリジナルのサウンドを使って誰でも動画投稿ができる作りになっています。
国内の著作権管理団体であるJASRACとNexToneの2社とは契約を結んでいますので、既存の楽曲を使った場合、その2つの団体で管理を委託されている楽曲については、投稿時に何の曲を使ったかを入力してもらうことで権利が確保されます。われわれの売り上げの中からその利用分が著作権管理団体経由でアーティストさんに支払われるというスキームですね。
次に、オリジナルがいいかどうかという話については2つのポイントがあると考えています。1つ目は、やっぱり特定の楽曲のあのフレーズというようなみんなが思い浮かべる名曲のイントロの音のようなものを、みんなが再現するというような楽しみ方です。一般の方が再現してみたり、もしくは本人が再現してみたりすることで、コミュニティーで盛り上がるというような使い方ですかね。
2つ目には、もっと実験的なところで価値を生む可能性があると考えています。音楽は創作活動だと思いますので、実験的に探索して、何か新しいものを見つけた時に、それを自分の楽曲に反映させたり、今後の作品に生かしたりすることにつながります。これらの実験的な音楽を創作する場ということがあると考えています。そこで生まれたオリジナルのものを投稿してもらうこと自体も価値があると思っています。
小寺 なるほど。そうなると、このサービスのマネタイズがどうなってるのか、というところにつながりますが、どうなっているのでしょうか。
川田氏 今アプリには都度課金型の機能が入っており、アーティストさんのコンテンツやレシピを買い切りという形で販売をしています。ただ、これは今現在の話で、今後コミュニティープラットフォームとしていろいろ展開できる余地がありますので、ユーザーや市場と対話しながら、追加のマネタイズ方法などを実装していく予定です。
小寺 それ以外に、今後の展開というのはどう考えていらっしゃるでしょうか。
川田氏 まず1つすでに行っているものとして、InstagramにTONEBOOKというアカウントがあります。フォロワーが1万5000人ぐらいいるのですが、すでにそこでコミュニティー運営みたいなものを過去2年半ぐらいやってきています。
そこで、ユーザーとの対話を行ったり、アーティストから実際に音のレシピに近い情報をいただいたりしています。例えば、どういったものをライブで実際に使っているかということなどですね。こうしたコミュニティーにおけるグロースのさせ方というものもノウハウができていますので、このグロースモデルのようなものをアプリにも転用できると思っています。
2つ目は、やはりアーティストさんに対価を還元できるような仕組みにしたいなというのをずっと考えています。それが投稿するインセンティブになったりだとか、ご自身の音楽活動の副産物として収入、副収入になったりするような仕組みを構想しています。
小寺 今そのInstagramの方を拝見していますけど、結構な情報の積み重ねがありますね。
川田氏 今アーティストさん400人ぐらいに取材をしています。海外も東南アジアや東アジアの方に取材を行っており、台湾、韓国、ロシア、フィリピン、タイ、中国の方などの掲載をさせていただいてます。
小寺 これは最初からカシオの運営でやっているということですか。
川田氏 最初は私が個人のプロジェクトとしてプライベートでやっていました。ただ、ものすごく反響があったんですよ。
ユーザーから「この人を取り扱ってほしい」「誰誰さんの取材をしてほしい」というようなリクエストがめちゃくちゃ来て、フォロワーも一気に伸びました。そこで「こういう音のレシピというもの自体に需要があるな」と確信が持てたので、途中からカシオに持っていったという形です。
小寺 個人としてもカシオの中の人としても、プロのギタリストに接点を持つのは、なかなか難しくないですか。
川田氏 はい。そこはもう知り合い経由でまずは頼みまくって「何のお返しもできないですけどこういうコンセプトのものを考えてるので協力してくれないか」と頭を下げ回りまくって徐々に形にしてきました。
ただ地道に積み重ねていくと実績が出てくるので、それを見た他のアーティストさんが「なんか面白そうだから乗ってやるよ」というような感じで、興味を持っていただけるようになりました。
カシオ製品とのつながりも
小寺 この流れで、将来的にはやっぱりカシオとして、何らかの製品に落とし込むようなことはあり得るんですかね。
川田氏 そこももちろん考えています。カシオはメカに強い会社だと思っていますし、もともと私もメカのエンジニアで鍵盤楽器を作っていたので、メカを絡めたいという思いはあります。よくあるBluetoothでつながるとか、そういう直接的な連携ではなくて、もっと違う形で価値を作れないかを模索しています。あくまでもTONEBOOKの情報に価値があって、そこに対して人がついてきてくれているので、自社に限らず他社さんも巻き込みながらやりたいという構想は持っています。
小寺 なるほど。レシピ公開がゴールじゃないということですね。
川田氏 そうですね。TONEBOOKは自分的には活動をモチベートするものだと思っています。
特に初心者であったり、コピーバンドをこれまでやっていて今からオリジナルをやるぞという時であったり、音楽でも世界が変わる場面があると思うんです。そこで不安になったり、モチベーション下がったり、継続できなかったりする話はよくユーザーからも聞きます。そこで誰かの刺激があると新たな動機になるんですよ。そういう刺激を受けられる場にしたいなと思っています。レシピというのも、そのモチベーションを生み出す手段の1つなんです。
カシオとギターの音のレシピは関係ないのでは、と思っていたが、実際にはもっと深いところで音楽そのものを続けていくモチベーションにつながる活動だというお話を聞いて、腑に落ちたところである。いくら電子ピアノがレッスンしてくれるとはいっても、結局音楽を持続していけるのは、人からもらえるパワーだったりするのだ。
シンセサイザーのようなデジタル楽器は、音色データを保存して一発で再現できたりもする。しかしレコーディングやライブでは楽器からのとって出しの音がそのまま使われるケースは少なく、何らかの加工がなされているものだ。プロとアマチュアの違いは、その「何らかの加工」の部分であり、そうしたところをひもといてくれるのがTONEBOOKということになっていくのだろう。
実は音楽雑誌は、いまだ健在である。楽器入門者がなくならない限り、こうした需要は続くのだろう。その一方で、インタラクティブ性を持つ音楽情報アプリとして、TONEBOOKはこれまでになかったアプローチである。すでにギターだけでなく、キーボードやハープなど、他の楽器の情報も集まり始めている。楽器をやる人、音をいじりたい人には、要注目のサービスである。
⇒連載「小寺信良が見た革新製品の舞台裏」のバックナンバーはこちら
⇒製造マネジメントフォーラム過去連載一覧
筆者紹介
小寺信良(こでら のぶよし)
ライター/コラムニスト。1963年宮崎市出身。
18年間テレビ番組編集者を務めたのち、文筆家として独立。家電から放送機器まで幅広い執筆・評論活動を行う。一般社団法人「インターネットユーザー協会」代表理事。2015年から4年間、文化庁文化審議会専門委員を務めたのち、2019年に家族で宮崎へ移住。近著に改訂新版「学校で知っておきたい著作権」がある。
Twitter(現X)アカウントは@Nob_Kodera
近著:改訂新版「学校で知っておきたい著作権」(汐文社)
関連記事
 カシオが作ったモフモフAIロボット 生き物らしい「可愛さ」をどう設計したか
カシオが作ったモフモフAIロボット 生き物らしい「可愛さ」をどう設計したか
カシオ計算機が2024年11月、AIペットロボット「Moflin」を発売した。ペットロボット市場はベンチャーの製品が多い印象だが、なぜ大手メーカーであるカシオ計算機が参入したのか、同社が蓄積してきたメカトロニクス技術をMoflinにどう生かしたか、お話を伺った。 人に合わせる「人間工学電卓」、カシオはレガシーな製品をどう進化させたのか
人に合わせる「人間工学電卓」、カシオはレガシーな製品をどう進化させたのか
カシオ計算機が「人間工学電卓」という電卓を新たに開発した。操作面に3度の傾斜を付けており、キーも階段状に配置がなされている。PC用キーボードでは人間工学的視点を取り入れた製品は少なくないが、電卓に適用するのは盲点だった。開発の背景を担当者に伺った。 なぜ電子音源が“生”の音を奏でるのか、ヤマハの歴史が生んだ新しいピアノ
なぜ電子音源が“生”の音を奏でるのか、ヤマハの歴史が生んだ新しいピアノ
音の問題などで家でピアノを弾きづらい場合、練習用に電子ピアノを使うことがある。だが、やはり生楽器とは音もタッチ感も違ってしまう点がもどかしく感じる人もいるだろう。その中で、ヤマハが発表したサイレントピアノのシリーズとして「トランスアコースティックピアノ」は、電子でありながら”生ピアノ”に近づける工夫が幾つも施されている点で注目だ。 鹿島建設が作った不思議なスピーカー ステレオ音源を立体音響にする技術とは
鹿島建設が作った不思議なスピーカー ステレオ音源を立体音響にする技術とは
クラウドファンディングで爆売れ中のスピーカーがある。建設会社として180年以上の歴史を誇る鹿島建設が開発した立体音響スピーカー「OPSODIS 1」だ。 プロジェクター市場半減の衝撃、カシオの生きる道は“組み込み”へ
プロジェクター市場半減の衝撃、カシオの生きる道は“組み込み”へ
コロナ禍もあってプロジェクター市場が急減している中、カシオ計算機は独自のプロジェクター技術を生かすべく、「プロジェクションAR」向けに用いられる組み込みプロジェクションモジュールを新規事業として立ち上げた。現在、最も強い引き合いがあるのが、スマートファクトリー向けの作業ガイドだという。 デライトデザインの先行事例としての“音のデザイン”
デライトデザインの先行事例としての“音のデザイン”
「デライトデザイン」について解説する連載。連載第4回では、デライトデザインの先駆的な事例といえる“音のデザイン”を取り上げる。音のデザインが生まれた背景や音の性質、音質指標などについて紹介するとともに、具体的な実施アプローチとして、クリーナー(掃除機)への適用例を詳しく説明する。 メイカーズから始まるイノベーション、ポイントは「やるかやらないか」
メイカーズから始まるイノベーション、ポイントは「やるかやらないか」
メイカーズの祭典である「Maker Faire Tokyo 2018」(2018年8月4〜5日、東京ビッグサイト)では、パソナキャリアの企画によるセミナー「メイカーズから始まるイノベーション」が開催された。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり
コーナーリンク