カシオがなぜ? ギタリスト向け「音のレシピ」アプリをリリースしたワケ:小寺信良が見た革新製品の舞台裏(37)(1/3 ページ)
2025年7月末、カシオ計算機はギタリストの音作りを支援するスマートフォンアプリ「TONEBOOK」をリリースした。ギターやエフェクターを作っているわけではないカシオがなぜ「ギターの音作り」に取り組むのか。その舞台裏を小寺信良氏が伝える。
連載「小寺信良が見た革新製品の舞台裏」趣旨
今までにない新しい製品のアイデアや発想はどこから生まれてきたのか小寺。映像系エンジニア/アナリストの小寺信良氏が商品企画や設計・開発の担当者へのインタビューを通じ、革新製品の生まれた舞台裏に迫る。
2025年7月末、ちょっと不思議に感じたニュースが流れてきた。カシオ計算機(以下、カシオ)が、ギタリストの音作りを支援するスマートフォンアプリ「TONEBOOK(トーンブック)」の提供を開始したというのだ。
カシオと音楽との関係で言えば、カシオトーンが有名だ。これは、プリセットシンセサイザー的なもので、多くの音を簡単に切り替えてさまざまな演奏が楽しめる。かつてはミニ鍵盤にサンプラーを内蔵した「SK-1」というヒット商品もあった。
シンセサイザーの世界でも、1980年代には独自開発のPD音源を内蔵した「CZシリーズ」を展開した。「CZ-5000」はシンセサイザーに8トラックシーケンサーを内蔵したモデルで、筆者が初めてシーケンサーなるものを理解したモデルである。近年ではコロナ禍の巣ごもり需要として、「Priviaシリーズ」などの電子ピアノが大ヒットしたのも記憶に新しいところだ。
とはいえ、ギターは関係ないはずだ。特にカシオはエフェクターを作っているわけでもない。ギターのエフェクターはほとんどがアナログ回路であり、かつてCMで一世を風靡した「デジタルは、カシオ」からは最も遠い存在のようにも思える。
一体なぜカシオが、ギタリスト向けの音作り支援アプリをリリースするに至ったのか。今回はその背景を伺うべく、取材をさせていただいた。お話を伺ったのは、TONEBOOKプロジェクト責任者でカシオ計算機 サウンド・新規事業部 第二戦略部 第一企画室の川田遼平氏だ。
TONEBOOKはそもそもなぜ生まれたのか
小寺 カシオには楽器事業があり、音楽に詳しい方も多くいらっしゃるとは思うのですが、どちらかというと得意なのは鍵盤楽器ですよね。一方、今回のTONEBOOKのように、ギターのサウンドレシピという方向へ行くのは、カシオのカラーとしては想像していなかった方向性でした。
川田氏 そもそも私がもともとバンドマンでしたので、「音のレシピ」というコンセプトが浮かんだ際に、自分の嗅覚が利く領域がギター領域でした。
小寺 ギターで音を作るというと、エフェクターとアンプになりますが、そこはカシオが手掛けていない分野ですよね。そうなると他社の製品情報を扱っていくことになると思うのですが、そのあたり、社内的にはどのような形でコンセンサスを取ったのでしょうか。
川田氏 そこは本当におっしゃる通りです。逆に言えば「だからこそギターにした」というのも2つ目の理由としてあります。
最初から鍵盤で進めると「うちで鍵盤やってるのになぜ他社の製品を取り扱うんだ」というような話になります。私の思いとしては、自社製品だけを取り扱う、いわゆる「オウンドメディア」みたいな形ではなく、楽器の特定領域を幅広く取り扱うものがやりたいと思っていました。われわれはコミュニティーと呼んでいるのですが、一方通行のメディアとは異なるものがやりたいと考えています。
また、ユーザーにとっても、1メーカーの商品情報だけが見えるのではなくて、幅広くいろんな音色を知ることができることにメリットがあるはずです。そういった意味でも、あえて弊社で扱っていない領域に飛び込んでいこうということになりました。
小寺 ギターのエフェクターって、アナログのものが多いですよね。一方、カシオは「デジタルはカシオ」なので、アナログの情報を扱っていくのは、新しい動きだったりするのですか。
川田氏 実際掲載しているものの多くはアナログな情報です。でも、そこが新しいという考えは特にないんですよね。
例えば、エフェクターやギターの設定値だけではなく「なぜこれを使っているのか」のような「思い」的なところや入手背景などを取材して掲載しています。「このツマミの位置がどう」といったセッティングだけを紹介しているわけではないんです。もちろんそうした具体的なセッティング情報も見どころではあるのですが、やはりアーティストさんの熱量が高い情報を掲載するところがコンセプトになっています。
小寺 そのあたりはかつてのギター系の雑誌が扱っていたような情報だと思います。これらを今の時代なりの出し方で発信していくということでしょうか。
川田氏 具体的に言うと、TONEBOOKのコンセプトというのは、実際の音が聞けることと、その音の情報を網羅的に把握できるということを大事にしています。
従来の雑誌だと、紙媒体なので音は聞けません。また、一般のユーザーさんが「最近買ったこれいいよ」みたいなことをSNSでレコメンドしても、網羅性がありません。
私はいつもラーメンに例えて説明しているのですが、ラーメンは、麺とスープとトッピングで決まりますよね。例えば「この麺いいんですよ」と言われても、そもそもスープが何系で、トッピングが何なのか分からないと、そのラーメン自体がおいしいかどうか分からないですよね。
ギターの音も同じです。ギターは何で、エフェクターは何で、アンプは何で……と、そこをきちんと押さえた上で、聴覚情報として聞いて、この音がちょっと好きだから再現してみようであったり、このギターを持っていないけど買ってみようであったり、進んでいくわけです。そういう行為につながる場としての価値を提供したいと考えています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?
コーナーリンク
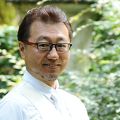

 TONEBOOKプロジェクト責任者である川田遼平氏 出所:カシオ計算機
TONEBOOKプロジェクト責任者である川田遼平氏 出所:カシオ計算機




