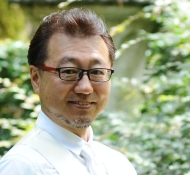音のズームレンズ? 聴覚拡張に挑戦するシャープ「SUGOMIMI」のスゴいところ:小寺信良が見た革新製品の舞台裏(35)(3/3 ページ)
自然の音や外国語の聞き取りで活用
―― なるほど。コンシューマー機器になれば、誰でも買えるわけですよね。SUGOMIMIが想定しているユーザー層は、どういう方なんでしょうか。
磯部氏 SUGOMIMIは、難聴者向けということではなく、まさに“聴覚拡張型”イヤホンとして、幅広い人に使用してもらいたいと考えています。極端なことを言うと、特に耳に問題のない方にお使いいただいても全く構わないと考えています。そこは、大きな違いになっています。
そうはいっても大きなターゲットとなるのは聞こえで気になることがある人だと思います。一般的な補聴器のユーザーは、大体70代が平均的な年齢層ということになりますが、SUGOMIMIはそれより少し若い世代がメインになると見ています。例えば、年齢的に耳の聞こえのことが少し気になり始める50代や60代に使っていただけるといいと思っています。
あとは、自然の音を楽しむのに最適なシーン設定を設けているので、アクティブに日常生活を送っている人もターゲットになるかなと考えてます。
もう1つ、開発の最中に行ったインタビュー調査などでは、仕事や趣味で英語や中国語などの外国語に触れる機会が多い方がこの商品を高く評価いただいたことがありました。そういう方々にもっとアプローチしていくことも今後考えていきたいと思っています。
―― 特に外国語は、母国語とは違う高域部分をちゃんと聞き取ることがすごく大事なので評価を受けているということでしょうか。
田邊氏 外国語に関しては、日本語よりも高い3〜4kHzといったところに重要な子音の音がある場合があります。そこがしっかり音として聞こえないと、言葉としても聞き取りにくい、理解しづらいということになります。
それが聞きにくいというのは、2つ要因が考えられます。1つは、加齢性のもので、年齢とともに耳の中の神経が劣化して、高音が聞き取りにくくなるというものがあります。もう1つは、われわれ日本人が長年日本に住んでいて、日本語として会話を成立させるために聞かないといけない音が、そこまで高い音ではないため、耳と脳が日本語をより聞きやすくなるように回路が出来上がっているためです。どうしても高音域をノイズとして落としやすくなっている傾向があります。
これに対し、少し高域を持ち上げることで、聞き取りやすくなる場合があります。それがその人の意識を変えたり、あるいは脳にある程度影響を与えたりして、外国語を聞き取りやすくする効果もあるのではないかと思いますね。
補聴器という製品は、極論をすると、会話をするための機械なのだと思います。音がしっかり聞こえなくて会話が成立しない状況は、周囲の人も大変だし、本人もつらいものです。ひいては、孤独感や認知症みたいな問題につながったりします。とにかく重要なのは、会話です。だから日本人同士が会話をすることをサポートするなら、特に日本語でよく使用される500〜2kHzの音域をしっかりその人に対して調整することが求められます。
一方でメディカルリスニングプラグは、低い周波数から6kHzぐらいまでしっかり自然に聞き取れるという特徴がありました。これであれば会話だけじゃなく、別の音を聞く機械として成立させられるんじゃないかというメディカルリスニングプラグをやってみて分かったことをベースに、SUGOMIMIの仕様をまとめていったというところもありますね。
―― 確かに川の音や料理の音など、特定の音にフォーカスするという聞かせ方は、これまであまりなかったアプローチですよね。
田邊氏 1番分かりやすいのは、自分の聴力に関して欲しい音を補うという考え方だと思います。例えば川の音を聞きに行くとします。でも川と自分の距離は変えられないですよね。だから本質的には川が流れてる音の大きさは変えられないんです。
それを、SUGOMIMIを使えば、手元で大きくできます。耳は周波数特性を変えられないので、もともとの音が持ってる成分の一部にフォーカスして、そこを強調することで大きく聞こえるのです。それができるようになることで、音の聞き方が変わるという面白さが生まれると考えています。
目や視覚では、そういう一部にフォーカスをしたり、それを支援する機器やツールもいろいろあると思うんです。でも耳でそれを経験した人はあまりいないと思うので、それを体験いただきたいなと思っています。ここに市場性があるようでしたら、聞こえの世界にも可能性がもっと広がると見ています。まずはこういう機器が市場でどのように受け止めらめられるかを、見ているところです。
お話を伺って感じたのは、これは「耳のズームレンズ」ということなのではないか、ということである。遠くのものが見たいと思えば、望遠鏡やズームレンズを搭載したカメラで手前に引き寄せてみることができる。じゃあ音も同じことができていいんじゃないか、ということである。
全部の音を大きくするだけなら、ただの集音器だ。だが周波数特性を絞って聞かせることで、特定の音にフォーカスできる。これこそまさに、ズームレンズで倍率を上げてフォーカスを合わせるのと、同じことである。
昨今はAppleが「AirPods Pro 2」を使った、ヒアリング補助機能を提供している。イヤホンによる聞こえの調整という方向に、少しずつ世界が注目し始めている。そんな中でいち早く医療用機器の要件をクリアし、コンシューマー機器で明確なコンセプトを打ち出したシャープは、こうした流れに対して一歩二歩のリードをキメたポジションにいる、といえるだろう。
⇒連載「小寺信良が見た革新製品の舞台裏」のバックナンバーはこちら
⇒製造マネジメントフォーラム過去連載一覧
筆者紹介
小寺信良(こでら のぶよし)
ライター/コラムニスト。1963年宮崎市出身。18年間テレビ番組編集者を務めたのち、文筆家として独立。家電から放送機器まで幅広い執筆・評論活動を行なう。一般社団法人「インターネットユーザー協会」代表理事。2015年から4年間、文化庁文化審議会専門委員を務めたのち、2019年に家族で宮崎へ移住。近著に改訂新版「学校で知っておきたい著作権」がある。
Twitterアカウントは@Nob_Kodera
近著:改訂新版「学校で知っておきたい著作権」(汐文社)
関連記事
 鹿島建設が作った不思議なスピーカー ステレオ音源を立体音響にする技術とは
鹿島建設が作った不思議なスピーカー ステレオ音源を立体音響にする技術とは
クラウドファンディングで爆売れ中のスピーカーがある。建設会社として180年以上の歴史を誇る鹿島建設が開発した立体音響スピーカー「OPSODIS 1」だ。 耳をふさがず音漏れは最小に、逆相で音を打ち消す新技術搭載のイヤフォン
耳をふさがず音漏れは最小に、逆相で音を打ち消す新技術搭載のイヤフォン
NTTソノリティが「nwm MWE001」というワイヤードイヤフォンのクラウドファンディングを実施した。耳をふさがないオープン型イヤフォンでありながら、音漏れが小さいという。「逆相の音」で打ち消す「PSZ技術」が活用されているというが、これは何か。NTTソノリティの担当者に開発経緯と併せて話を聞いた。 Z世代の心に響け、ソニーの“穴あき”イヤフォン「LinkBuds」に見る音の未来
Z世代の心に響け、ソニーの“穴あき”イヤフォン「LinkBuds」に見る音の未来
ソニーが2022年2月に発売したイヤフォン「LinkBuds」は、中央部に穴が開いたリング型ドライバーを搭載している。あえて穴を空けることで、耳をふさがず、自然な形で外音を取り入れるという技術的工夫だ。これまで「遮音」を本流とした製品展開を進めてきたソニーだが、LinkBudsにはこれまでの一歩先を行くという、同社の未来に向けた思いが表れている。 ソニーが「発明」した新しい音体験、「ウェアラブルネックスピーカー」の秘密
ソニーが「発明」した新しい音体験、「ウェアラブルネックスピーカー」の秘密
ここ最近注目を集めている「ネックスピーカー」というオーディオの新ジャンルを生み出したのが、2017年10月発売のソニーのウェアラブルネックスピーカー「SRS-WS1」だ。今回は、このSRS-WS1の開発に関わったメンバーに話を聞いた。 完全ワイヤレスイヤフォンのキラー技術「NFMI」の現在・過去・未来
完全ワイヤレスイヤフォンのキラー技術「NFMI」の現在・過去・未来
左右分離型のワイヤレスイヤフォン、いわゆる完全ワイヤレスイヤフォンが人気を集めている。2016年ごろからKickstarterでベンチャー企業が製品化して話題となったところで、同年末にアップル(Apple)が「AirPods」を発売。 カシオが作ったモフモフAIロボット 生き物らしい「可愛さ」をどう設計したか
カシオが作ったモフモフAIロボット 生き物らしい「可愛さ」をどう設計したか
カシオ計算機が2024年11月、AIペットロボット「Moflin」を発売した。ペットロボット市場はベンチャーの製品が多い印象だが、なぜ大手メーカーであるカシオ計算機が参入したのか、同社が蓄積してきたメカトロニクス技術をMoflinにどう生かしたか、お話を伺った。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?
コーナーリンク