“環境”を競争力のきっかけに、セイコーエプソンが考える日本の製造業の勝ち筋:製造業は環境にどこまで本気で取り組むべきか(1/5 ページ)
大手精密機械メーカーとして、環境についての世界的な要求の高まりを事業成長の機会として生かそうとしているのが、セイコーエプソンだ。「環境ビジョン2050」を掲げる同社の考え方と取り組みについて、セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏に話を聞いた。
環境問題に対する透明性や取り組み内容が製造業にとっても事業活動に直結するようになりつつある。一方で、環境に対する取り組みは事業活動とのトレードオフになる場合も多く、製造業はこの流れに対し、どういう考え方でどのように優先順位をつけて取り組むべきなのだろうか――。
大手精密機械メーカーとして、環境についての世界的な要求の高まりを逆に事業成長の機会として生かそうとしているのが、セイコーエプソンだ。「環境ビジョン2050」として、2050年にカーボンマイナスと地下資源消費ゼロを目指す同社の考え方と取り組みについて、セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏に話を聞いた。
連載「製造業は環境にどこまで本気で取り組むべきか」の企画趣旨
環境への取り組みは重要性を増す一方で、収益とのバランスが難しいケースも多く存在します。そこで、MONOistでは、環境特集「カーボンニュートラルへの挑戦」および「サステナブルなモノづくりの実現」の中心企画として、製造業として環境への取り組みにどのように向き合い、どのような優先順位で進めているのかを各企業のキーマンに伺う本連載を企画しました。
⇒連載のバックナンバーはこちらから
“田舎の大企業”として環境への取り組みを先導する
MONOist 昨今の製造業を取り巻く脱炭素や資源循環などの環境への取り組みへの要求についてどう捉えていますか。
木村氏 製造業にとって、環境への取り組みと事業活動をバランスを取りながら進めていくことは、難しいことだと捉えています。しかし、中長期で考えた場合、人口も増え、資源も有限であり、大量生産大量消費で続けていくということが難しくなるのは自明です。今の局面だけを見て考えてコストアップになっても、中長期で考えると進める方向に舵を切らなければ、持続可能なものにはなり得ないというのがわれわれの考えです。
特に、エネルギー資源のない日本で、資源を使って製品を作る日系製造業にとっては、環境問題への対応は死活問題になり得ます。円安や地政学的問題などで、電力価格の高騰が進み、国内の製造業が今どの企業も苦しい状況を強いられていることを見ても、その一端を身近に感じることができます。これらを考えると、分散型エネルギーによる地産地消の推進など、自分たちで取り組めるところは取り組んでいかないと将来的には製造業の事業運営そのものが厳しくなってくるでしょう。今までのように人件費が安いところで製造活動を行うというような、単純な経済的原理だけでは語れなくなってきています。
われわれは長野県諏訪市に本社があり、自分たちでも“田舎の大企業”だという認識があります。そのため、リソースが限られる地方都市の中でそういうエネルギーの問題などにより強く向き合わざるを得ない状況があります。一方でこういう問題は世界的な動きとして「大企業から進めるべきだ」という機運が高まっており、望むと望まざるにかかわらず環境への取り組みを自らけん引していかざるを得ない立場だと捉えています。どうせやらなければならないのであれば、企業として社会に役立つという原点に立ち、これらの動きを先導していきたいと切り替えて今取り組んでいるところです。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり
- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- AWSは信頼性への投資に注力 フィジカルAI開発を支援する新たなプログラムも発表
コーナーリンク
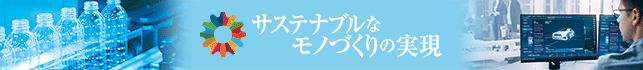
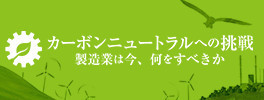
 セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏
セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏



