インテル、「Atom」を武器にアミューズメント市場へ:組み込みイベントレポート(2/3 ページ)
肉声に極めて違い音声合成も実現
高度な音声系ソリューションでも面白いものがいくつかあり、日立超LSIシステムズの音声合成ミドルウェア「Ruby Talk」が傑出していた。Ruby Talkは、日本語処理技術で漢字かな交じりテキストを文脈も含め読み分け、自然発話に極めて近い韻律、感情表現で音声を合成する。男性・女性、子供・壮年などのプロファイルが用意されているのも特長だ。なお、Ruby Talkには、組み込み機器に最適化した「Micro Ruby Talk」があり、ソニーのPS3や任天堂のニンテンドーDSのゲームソフトなどにも採用されている(画像9)。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 日立超LSIシステムズ |
| ⇒ | ソニー |
| ⇒ | 任天堂 |
また、セイコーエプソンの「感情認識チップ」は、人の声を分析して感情(喜・怒・哀・平常・笑い・興奮)の度合いを定量評価するシステムLSIで、ソフトウェアにはベンチャー企業のAGIが開発した「Sensibility Technology」を採用する。AGIの担当者は「辞書ではなく、ロジックルールで感情を判定しているためソフトウェアが非常に軽量なのが特長。専用チップの登場で幅広い組み込み機器へ搭載できる」と期待していた。どのような組み込み用途が生まれてくるのか、注目される(画像10)。

 画像9(左) 音声合成ミドルウェア「Ruby Talk」は、自然発話に極めて近い音声合成が可能。ソニーPS3用ソフト「ダービータイム」にも採用されている/画像10(右) セイコーエプソンは各種音声ソリューションを前面で展開。特に人の感情を検出する「感情認識チップ」は、今後の用途開発に期待がかかる
画像9(左) 音声合成ミドルウェア「Ruby Talk」は、自然発話に極めて近い音声合成が可能。ソニーPS3用ソフト「ダービータイム」にも採用されている/画像10(右) セイコーエプソンは各種音声ソリューションを前面で展開。特に人の感情を検出する「感情認識チップ」は、今後の用途開発に期待がかかる随所でAndroidの可能性を示すデモ
話題の携帯電話機向けプラットフォーム「Android」で人を集めるブースもあった。Linux対応のARM搭載CPUボード「Armadillo」シリーズを展開するアットマークテクノは、最新の「Armadillo-500 FX」(Freescale製ARM11プロセッサ「i.MX31」、128MB DDR SDRAM、32MBフラッシュメモリ)にAndroidを搭載し、動作デモを行っていた。ウィルコムの通信モジュール「W-SIM」をインターフェイスボードに装着し、組み込みLinuxベンダのアックスが開発したAndroid上でW-SIMを制御するプログラム(radio interface layer)を実装。Androidの電話機能、SMS機能を利用可能にしていた。多くの人が“動くAndroid”を前にして足を止めていた(画像11)。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | FPGA+Linuxで“究極のプラットフォーム”提供 |
| ⇒ | アットマークテクノ |
| ⇒ | ウィルコム |
| ⇒ | アックスの組み込みLinuxはほかと根本的に違う |
| ⇒ | アックス |
組み込みLinuxを得意とする富士通ソフトウェアテクノロジーズは、Android上で構築したカーナビを参考出展していた。ARM9をCPUコアとする富士通のカーナビ向けLSI「MB86R01」上でAndroidを稼働させ、4枚のフレームバッファを独立制御。カーナビアプリ、動画・文字・画像表示の同時動作を可能としたものだ(画像12)。さらに、Android端末と富士通の「FPcode(Fine Picture Code)技術」(印刷物に埋め込んだ電子透かしを端末で読み取り、Web接続行うもの)を組み合わせたデモサービスを紹介。同社では「Androidをプラットフォームとすれば、Java技術者がアプリケーション開発に参加しやすくなり、サーバ連携も容易」と話しており、Androidは幅広い組み込みソリューションで活用される可能性を秘めている。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 富士通ソフトウェアテクノロジーズ |
| ⇒ | 富士通 |
実用性を高めた静的解析ツール
開発支援ツールを展示しているブースはどこも人だかりで、開発を効率化するソリューションを求めているユーザーがいかに多いかが分かる。その中でも静的解析ツールの注目度は高かった。例えば、コベリティがデモを行っていた「Coverity Prevent Static Analysis」は、モジュール間の関連性も含める「プロシージャ間解析」、実行パスをトレースする「パス解析」により、ソースコードを“広く深く”解析し、静的解析ながら多様なバグを検出できる点がユニークだった。気になる誤検出率も「15%程度」だという(画像13)。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | コベリティ |
また、国産ツール「PGRelief」を擁する富士通ソフトウェアテクノロジーズも、「導入企業が増えるに従い、ユーザーからのフィードバックで解析精度が上がっている。今後は構造が複雑なC++での精度を高めていく」としている(画像14)。今後も静的解析ツールはジワジワ浸透していきそうな気配である。
設計支援ツールでは、この分野のリーディングベンダであるキャッツが注目の的だった。状態遷移表を用いて設計品質を高める「ZIPC」シリーズのみならず、画面遷移図からGUIを設計していく「Drawrial」も関心を集めていた(画像15)。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 「品質100%保証」を実現するCASEツールへ |
| ⇒ | キャッツ |
さらに、テスト駆動型開発を訴えていたのが日本IBM。ソースからテストのスタブ・ドライバを自動生成する「Rational Test RealTime」により開発者主体でテストが行え、同時にメモリ、性能のプロファリング、カバレッジ分析の解析も行えるという。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 日本IBM |
また、アジレント・テクノロジーが提案していた「多元同期デバッグ」も、組み込みシステムのデバッグで今後のトレンドとなっていきそうだ。これはオシロスコープとロジックアナライザを連携させ、アナログ特性を踏まえデジタル信号を精緻(せいち)に検証するもの。超高速なデジタル回路が増えてきた現在、物理・論理・プロトコルの層を統合したデバッグが必要なのだ。説明員によれば、「ユーザーが1年かかっても原因が判明しなかった現象を多元同期デバッグで解決できたこともある」という(画像16)。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | アジレント・テクノロジー |
関連キーワード
組み込みAndroid開発 | Atom | Intel | LSI | UniPhier(ユニフィエ) | 組み込みDB | 組み込みLinux | FPGA関連 | 半導体 | Windows CE | 組み込みシステム
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 汎用のER電池とサイズ互換がある全固体電池モジュール、出力電圧も3.6Vに変換
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売
- 独創的なロジック記憶手法で違いを見せつけたActelはいかにして誕生したのか
- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断
- パーソナルAIスパコン向け組み込みコントローラー用カスタムソフトを開発
コーナーリンク
 画像11 自社のCPUボードをベースに開発した通話可能なAndroid端末を展示したアットマークテクノのブースでは多くの人が足を止めていた
画像11 自社のCPUボードをベースに開発した通話可能なAndroid端末を展示したアットマークテクノのブースでは多くの人が足を止めていた 画像12 富士通ソフトウェアテクノロジーズはAndroidをソフトウェア基盤とするカーナビを参考出展。Androidの用途開発に期待が掛かる
画像12 富士通ソフトウェアテクノロジーズはAndroidをソフトウェア基盤とするカーナビを参考出展。Androidの用途開発に期待が掛かる 画像13 コベリティは一般の静的解析ツールと一線を画す「Prevent」をデモ展示、プロシージャ間解析、パス解析によるバグ検出能力の高さをアピール
画像13 コベリティは一般の静的解析ツールと一線を画す「Prevent」をデモ展示、プロシージャ間解析、パス解析によるバグ検出能力の高さをアピール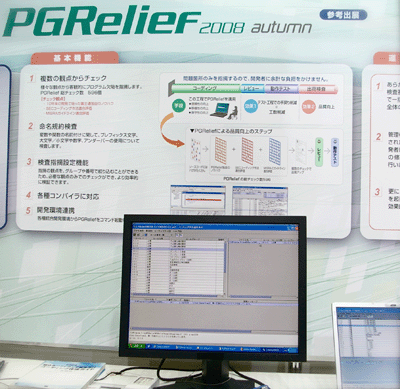 画像14 MISRAでC++のコーディング規約(MISRA-C++)が策定されたことにより、静的解析ツール「PGRelief」でもC++対応が進められている
画像14 MISRAでC++のコーディング規約(MISRA-C++)が策定されたことにより、静的解析ツール「PGRelief」でもC++対応が進められている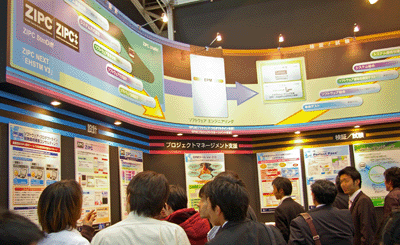 画像15 盛況ぶりを見せるキャッツのブース。設計段階から品質を作り込むという同社の製品コンセプトはユーザーから高い評価を得ているという
画像15 盛況ぶりを見せるキャッツのブース。設計段階から品質を作り込むという同社の製品コンセプトはユーザーから高い評価を得ているという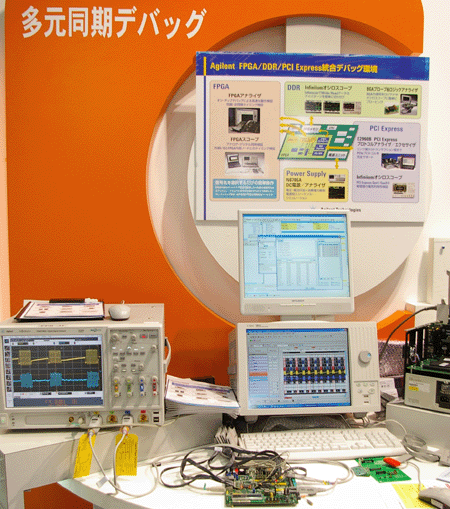 画像16 アジレント・テクノロジーが提案する「多元同期デバッグ」。オシロスコープとロジックアナライザ(DDR、FPGA、プロトコルなど)を連携させる
画像16 アジレント・テクノロジーが提案する「多元同期デバッグ」。オシロスコープとロジックアナライザ(DDR、FPGA、プロトコルなど)を連携させる

