中小製造業のDXの現実――「使いこなし」にこだわったエースが成功した理由:これからの中小製造業DXの話をしよう(5)(1/3 ページ)
本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第3〜5回は実際の中小製造業におけるデジタル化の取り組み事例を紹介していますが、第5回では高度な金属加工を手掛けるエースのデジタル化事例を紹介します。
大田区における中小製造支援プロジェクトでの取り組みを基に、小規模製造業の今後進む道について解説している本連載ですが、第3回、第4回は、中小製造業のデジタル化のリアルな姿を事例をベースに紹介しています。
≫連載「これからの中小製造業DXの話をしよう」のバックナンバー
第5回となる今回は、東京都大田区で金属加工を行うエースの事例を取り上げます。エースは、東京都大田区城南島に本社を構える1974年設立の企業です。主に金属加工、組み立て、検査治具の製作、専用機械部品の製造、試作品の開発を手掛けています。社内にはマシニングセンター、複合加工機、平面研削盤、汎用フライス盤などの設備を備え、CAD/CAMを活用した高度な加工技術を保有しています。
エースの特徴は、自社の高い技術力に加え、300社以上の協力工場と連携し、最適な生産パートナーを選定できることです。これにより、自社だけでは対応が難しい加工や特殊な技術が必要な案件でも、最適なモノづくりを実現しています。また、多くのパートナーとつながることで、より多くの加工ができるため、積極的な営業活動で多数の案件を獲得しています。本稿では、この外部連携と営業活動を強みとするエースが、小規模製造業ならではの特徴を踏まえながら、どのようにデジタル化を進めていったのかを詳しく紹介します。
(1)エースはなぜデジタル化に本格的に取り組んだのか
エースがデジタル化に本格的に取り組むようになった背景には、大きく2つの要因がありました。1つ目は、年々増加する営業案件に対して、現有の人的リソースだけでは対応が追い付かなくなったことです。少人数で営業活動を行っていたエースでは、受注対応から見積もり、進捗確認、納品調整、アフター対応まで、全てを一部の社員が兼務する状態が続いていました。そのため、対応のスピードや精度の維持に限界がありました。リソースが逼迫(ひっぱく)し、目先の顧客対応に追われるあまり、受注機会を逃してしまう場面も増え始めていたといいます。
2つ目は、300社以上の協力会社とのやりとりに伴う業務の煩雑さです。エースのビジネスモデルは、自社で加工できない案件を適切な外部パートナーに振り分け、全体として最適な工程を構築する「広域分業型」ともいえる体制に支えられています。しかし、案件ごとに仕様や納期、加工内容が異なり、それらを都度調整、管理するには、アナログな手段では限界がありました。電話やFAX、紙ベースの資料に依存したままでは、情報の取り違いや伝達漏れといったリスクも高まり、生産全体の信頼性や効率に悪影響を及ぼす恐れがありました。
特に顕在化していた課題として、以下の4点が挙げられます。
- 営業人員不足による業務過多:日常的に複数案件が同時進行する中、営業担当者が全てを抱える構造となっており、業務が属人化しやすい状況にありました
- 案件数の増加に伴う受発注、入出金処理の煩雑化:Excelや紙の帳票を使って管理していた業務は、案件数の増加とともに処理工数が跳ね上がり、ミスや二重入力といった課題も浮上していました
- 外部工程(協力会社)の進捗管理の困難さ:外部加工先のスケジュールや仕掛品の所在、納期の確定などを把握するための情報が分散しており、リアルタイムの進捗確認が難しいという問題がありました
- 紙図面の保管スペースと検索性の問題:加工に必要な図面は紙で保管していたため、物理的な収納スペースが逼迫し、必要な図面を探すのにも時間がかかるなど、業務効率の面で大きなロスが生じていました
これらの課題を放置したままでは、将来的な業容拡大はおろか、現状維持すら困難になるリスクがありました。特に中小企業にとっては、限られた人員や設備のなかで生産性を高めるには、業務の合理化と可視化が急務となります。
そうした背景のもと、エースでは、デジタル化によってこれらの問題を根本的に解消することを模索し始めました。ちょうどそのタイミングで、IT導入補助金の制度活用が可能になったことや、大田区内の製造業者が連携して立ち上げたデジタル推進ネットワーク「I-OTA合同会社」との出会いが、大きな後押しとなりました。I-OTAでは、同じような悩みを抱える企業同士が情報交換を行いながら、自社に合ったツールやプロセス改善の知見を得ることができ、エースにとっても外部の視点から自社の課題を見直す貴重な機会となったのです。
このようにしてエースは、単なる「ITツールの導入」ではなく、自社の業務構造やビジネスモデルに適した形でデジタル化を推進していくという、戦略的な方針へと舵を切ったのです。デジタル化の本質は、既存業務の効率化だけでなく、将来の競争力強化と経営の持続性を見据えた変革の一環であることを、同社は早い段階で認識していました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
コーナーリンク
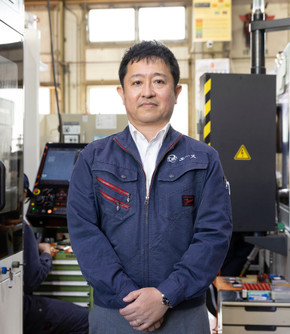 エース 代表取締役の西村修氏
エース 代表取締役の西村修氏



