中小製造業のDXの現実――基幹系をまとめてデジタル化した堤工業のポイント:これからの中小製造業DXの話をしよう(4)(1/2 ページ)
本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第3〜5回は実際の中小製造業におけるデジタル化の取り組みを事例を紹介していますが、第4回は、プラスチック切削加工を行う堤工業の事例です。
大田区における中小製造支援プロジェクトでの取り組みを基に、小規模製造業の今後進む道について解説している本連載ですが、第3回からは、中小製造業のデジタル化のリアルな姿の事例をベースに紹介しています。
≫連載「これからの中小製造業DXの話をしよう」のバックナンバー
第4回となる今回は、東京都大田区でプラスチック切削加工業を営む堤工業の事例を取り上げます。堤工業は、大田区西六郷に本社を構える1943年設立の企業です。FRP(繊維強化プラスチック)、エンジニアリングプラスチック(エンプラ)、熱硬化性樹脂、汎用プラスチックなどの加工を得意としています。社内にはCAD/CAM、マシニングセンター、NCフライス盤を15機程度保有し、2D/3D検査機器を用いて日々の業務を行っています。
(1)堤工業はなぜデジタル化に取り組んだのか
堤工業では、社内業務の整理整頓に長年取り組んできましたが、従来のアナログ的な方法では期待する成果が得られませんでした。その後、IT導入補助金を活用した業務効率化について知り、周囲の工場に補助金の具体的な活用方法や利用システムについて調査を進めました。その過程で、既に生産管理システムを導入しており、本連載で前回紹介したフルハートジャパンからテクノアの紹介を受け、本格的なデジタル化の推進を決めました。
堤工業 代表取締役社長の栗原良一氏は「将来的なシステム更新を見据えたデジタル化を進めています」と語っています。一般的なシステム化では情報の一元管理が重視されがちですが、同社では特定のITベンダーへの依存を避け、複数ツールを併用する戦略を取っています。これは、アカウント数の制限によるコスト管理や、将来的な会社の成長を見据えた柔軟な対応を可能にするためです。一つのシステムに集中してベンダーロックインされるのを避け、さまざまなツールを活用することで、将来的なシステム展開の選択肢を広げることを重視しています。
(2)生産管理業務のデジタル化
ここからは堤工業のデジタル化状況を見ていきます
基幹系システムのデジタル化
IT導入補助金を活用し、テクノアの「TECHS-BK」を導入して受注、製造、出荷、売上高、仕入れに関する管理業務のデジタル化を実現しました。これに加えて、導入当初は製造工程の進捗管理も同一システムで行えるようにしました。バーコード管理システムを組み合わせ、各工程の進捗状況をリアルタイムに把握できる仕組みを構築したのですが、現場の作業員が入力作業を避ける傾向にあり、運用面でうまくいきませんでした。現場の担当者は、加工以外の業務に時間を割きたくないという心理が根強く、デジタル化の効果を最大限に引き出すには、運用面での工夫が必要だと分かりました。そのため、現場改善に関するツール導入の際には、事前に現場での実行可能性を確認してから着手する方針としています。
生産管理システム以外では、見積もり業務のデジタル化に着手しています。これまで紙で行っていた見積書の作成と管理を、フリップロジックの「FLAM」というツールを活用し、ペーパーレス化しました。このツールは無料で試用できたため、使い勝手を確認しながら導入を進め、業務のスムーズな移行を実現しました。
生産管理システムで売り上げ、仕入れを把握できますが、システム以外でも確認できるように、スプレッドシート(Excel)にデータをアウトプットして管理しています。これには栗原氏のシステムに対する考え方が反映されています。「企業の成長過程において、増員時にシステム投資が困難な場合を想定し、アカウント数による利用者制限で活動が制約されないようにする配慮しています」(栗原氏)。これは小規模事業者の成長過程ならではの対策といえます。
バックオフィス、情報共有のデジタル化
社内のコミュニケーションツールについては、これまで利用していたコミュニケーションツールのコスト上昇を受け、NTT西日本の「ELGANA」に移行しました。大手企業が提供するサービスという信頼性も選定理由の1つとなりました。現在は社内でスマートフォンとPCで活用しています。
このツール活用が定着したことで、スケジュール管理の方法も効率化を図りました。従来のカレンダーへの納期記入方式では、現場作業員の確認頻度が低かったため、チャットによる毎日のリマインド方式へと変更しました。現場では作業に集中するため自発的な情報確認が少ないという特性を考慮し、受動的な情報共有から能動的な情報発信へと切り替え、業務が円滑になりました。
さらに、労務管理にはDONUTSの「ジョブカン」を、経理/会計管理にはマネーフォワードの「Money Forward」を導入し、会計と給与情報を一元化しました。これにより、データ入力や確認作業が効率化され、経理業務の負担が大幅に軽減されました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり
コーナーリンク
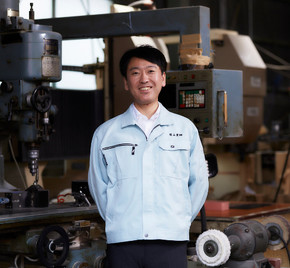 堤工業 代表取締役社長の栗原良一氏 出所:堤工業
堤工業 代表取締役社長の栗原良一氏 出所:堤工業



