国産RTOSの礎となった「TRON」の歴史を語ろう:リアルタイムOS列伝(58)(2/3 ページ)
3種類の開発が予定されていたBTRON
さて、ITRONはちょっと後に回すとして、先に他のTRON OSについて説明しておこう。まずBTRONは、PCやワークステーション向けのBTRON(後にBTRON1に改称)と、ワープロ機などへの実装を予定していたμBTRON、それと1990年に完成予定だったトロンチップ上で動作する事を想定したBTRON(後にBTRON2に改称)の3種類が開発予定だった。
これらのうちμBTRONに関しては、最終的に後にでてくるITRONの小型機器向け仕様であるμITRON(正確にはμITRON3)をベースに、PDAなどに向けたμBTRONとして1996年ごろにリリースされている。ちなみに携帯電話機への採用なども狙ったようだが、結果から言えば若干の製品に採用されるにとどまっている。
BTRON2は、1992年に仕様書こそ出版されたものの製品化には至らなかった。理由の一つは、トロンチップの開発が芳しくなかったことだ。東大のトロンサブプロジェクト-CHIPサブプロジェクトページによれば、富士通/三菱電機/日立製作所の3社グループによりGmicro 100/200/300/400/500、それと東芝のTX1/TX2、松下電器産業のMN10400、沖電気のO32という6社合計で9種類のトロンチップが開発されたとしている(図2)。
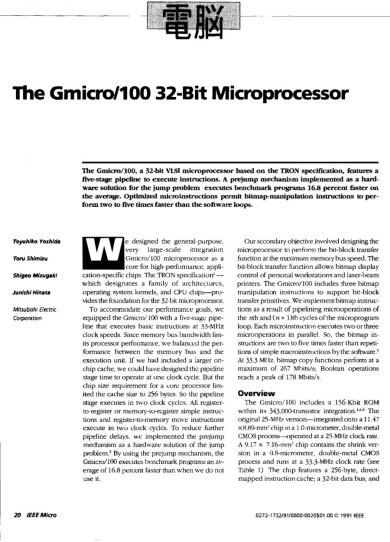 図2 IEEE Micro Volume 11 Issue 4に掲載された三菱電機の「The Gmicro/100 32-bit microprocessor」より。33MHzのGmicro/100は16.7MIPSとされたが、もうこの時期にはi486やi960、R3000などが市場に投入されていた[クリックで拡大]
図2 IEEE Micro Volume 11 Issue 4に掲載された三菱電機の「The Gmicro/100 32-bit microprocessor」より。33MHzのGmicro/100は16.7MIPSとされたが、もうこの時期にはi486やi960、R3000などが市場に投入されていた[クリックで拡大]ただし、いずれの製品も性能のわりに構造が複雑で高コストのCISCチップだったこともあって、絶対性能や価格の観点でx86をはじめとする汎用CPUには勝てなかった。組み込み向けとしても、価格や性能/消費電力比の観点でARMや日立のSHシリーズなどに遠く及ばなかった。それでも、後述するCTRONの成功のおかげで、そのCTRON向けにある程度の量産はなされたが、通常のワークステーションやPC向けでは全く成功しなかった。
一般ユーザー向けのBTRONマシンは発売の機運を逃す
話をBTRONに戻すと、当時の国内PC市場ではNECのPC-9801シリーズがかなり大きなシェアを獲得しつつある時期である。ちょうど当時の文部省が学校へのコンピュータ導入を検討し始め、通商産業省と文部省が共同で設立したCEC(財団法人コンピュータ教育開発センター)がその学校機関向けコンピュータの仕様を定め始めたが、ここでNEC以外のメーカーが一致協力する形でBTRONの採用を強く推すことになる。
この学校機関向けBTRONは松下電器産業が開発を担当し、1989年にはBTRONを搭載したCEC向けマシンが完成したものの、その1989年にUSTR(米国合衆国通商代表部)が貿易障壁年次報告としてBTRONを名指しするなどして、大きくもめることになる。NECも当然自社のPC-9801シリーズを強く推すなどしたため、最終的にCECはBTRONベースで仕様を統一する事を断念。これが引き金になり、一般ユーザー向けのBTRONマシンは発売の機運を逃すことになった。
その後、パーソナルメディアを中心にBTRONソフトウェア開発機構が1991年に設立され、松下電器産業が開発したBTRONをベースにしたノートPCの発売や、BTRONをAT互換機に移植した1B/V1の開発などで、一部のユーザーがBTRONを使うようになる。パーソナルメディアはその後、μITRON 3.0をベースにしたItIs Phase 3を基に独自拡張をおこなったBTRON3の仕様を策定。1998年にはこのBTRON3に基づくAT互換機向けのB-right/Vを、1999年にはこれに多漢字を扱える機能を追加した超漢字を発表するなどしているが、残念ながらWindowsやその後に登場したLinuxなどに比べると成功から程遠い位置にいる。
電話交換機に広く採用されたCTRON
CTRONは、ここまでで少し言及したが、特に電話交換機のシステムにうまく採用された。これは、そもそもCTRONの開発の主導を電電公社(日本電信電話公社:現在のNTT)が取ったことが功を奏した格好だ。当時、電電公社の電話交換機は電電公社独自の仕様になっており、この独自仕様が電電公社の赤字の一因にもなったのだが、電電公社は1990年代から導入した新しい交換機の仕様を、CTRONが稼働すればアーキテクチャを問わないとしたことで、各社がCTRONを利用して交換機を製造/納入することになった。また、CTRONは全銀システム(全国銀行データ通信システム)の中継器にも採用された。このCTRONベースの電話交換システムは長らく利用されたが、2010年代に入って電話網のIP化に伴い機器の入れ替えが起きる中で急速に数を減らしており、現時点でどの程度残っている(もしくは既に完全に撤去された)かは不明である。
そしてMTRONは、ITRON/CTRON/BTRONの上位に当たるOSというよりは今で言えばハイパーバイザー的な位置付けになるはずのものであったが、BTRONがほぼ失敗、CTRONは特定用途向けにとどまり、そもそも成功したのがITRONだけという状況では実装のしようもなく、結局構想だけで終わっている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開
- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売
- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功
- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断
コーナーリンク



