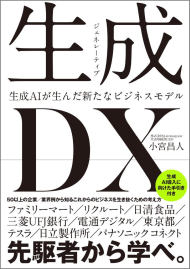グローバル連携の下で広がる製造業のデータ共有圏「Manufacturing-X」とは?:加速するデータ共有圏と日本へのインパクト(6)(3/3 ページ)
【航空業界】Aerospace-Xの活動
Aerospace-Xは、航空産業におけるデータ連携を通じたサプライチェーンの付加価値向上を目指す取り組みだ。需要の変動、地政学リスク、サイバー攻撃などさまざまなサプライチェーン課題に対して、データ連携を通じてサプライチェーンの効率性やレジリエンスなどを改善する。フラウンフォーファー研究機構が主導し、Gaia-X、Catena-X、Plattform Industrie 4.0、IDTAなどの関連プロジェクトの結果と経験を航空業界にトランスファーする。ドイツ経済気候対策省が資金提供しているプロジェクトだ。エアバス傘下のAirbus OperationsはOEM企業の視点を代表し、コンソーシアムを主導する。
- プロジェクトパートナー(29企業/組織):Airbus Operations、キャップジェミニ、ドイツ空軍、SAP、T-システムズ、ロールスロイス、ティッセンクルップ、DMG森精機など
ユースケースとしては、需要と容量の管理、CO2排出量とCO2フットプリントの規制、循環型経済、共同品質管理に取り組んでいる。
【化学業界】Chem-Xの活動
Chem-Xは、化学産業のバリューチェーンに沿って材料情報の透明性を高め、持続可能性と競争力を強化することを目的とする。化学物質と材料のオープンなデータスペース構築を目指す。バリューチェーン全体でカーボンフットプリントなどの持続可能性データや、「低PCF(製品カーボンフットプリント)」「リサイクル含有量」「生物起源含有量」などのデータを交換し、デジタルプロダクトパスポートの作成を可能にする。下記の14のパートナーおよび団体のコンソーシアムである。
- プロジェクトパートナー(14企業/組織):BASF、Catena-X、Cofinity-X、Covestro、DAW、Evonik、Henkel、メルク、SAP、Siemens、SIKAなど
下記の3つの目的やユースケースの実現を目的として取り組みが進んでいる。
| 目的 | 概要 |
|---|---|
| 【#1】競争力 | 化学固有のデータモデルと技術仕様の標準化を通じて、サプライチェーンの相互運用性と効率性を向上 |
| 【#2】持続可能性 | PCFやリサイクルコンテンツなどの持続可能性特性の透明性を促進 |
| 【#3】レジリエンス | デジタルマテリアルツインなどのデジタルテクノロジーにより、市場の変化に柔軟に追従 |
| 表3 Chem-Xのユースケース | |
【ロボット業界】Robot-Xの活動
Robot-X は、ロボットシステムの製品ライフサイクルをデジタル化し、関係するアクターを結び付けて、相互作用プロセスを最適化することを目指す。中小企業にとって、ロボットシステムへの参入障壁は、投資コストの高さと開発段階の複雑さが原因になっていることが多い。Robot-Xプロジェクトは、これらのハードルを下げ、中小企業がカスタマイズされたロボットや自動化ラインにアクセスしやすくすることを目的とする。
これは、MBSE(モデルベースシステムエンジニアリング)とAI(人工知能)の活用によって可能になる。このプロジェクトの中核は、AIを使用したデータとモデルベースのシステム開発を可能にするために、ロボットコンポーネントのデジタルツインを調和的に交換するためのネットワーク化されたデータ空間の作成にある。このアプローチは、モジュール原理に基づいてロボットシステムの自動構成を追求する。この目的のために、3つのユースケースでさまざまな業界横断的なアプリケーション シナリオが実装されている。
- 防衛や農業で使用されるドローンの離着陸装置であるドローンポート
- 産業における不規則な形状の製造部品の工業用パッケージング
- 複合材加工、航空業界向けの自律精密研削システム
【ヘルスケア業界】HealthTrack-Xの活動
HealthTrack-Xは、ヘルスケアのためのオープンで分散化されたデータエコシステムの構築を目指す。
- プロジェクトパートナー:Roche、Siemens Healthineers、フラウンフォーファー研究所、バイエル、ジョンソン&ジョンソン、MSD、武田製薬、T-システムズ、ZVEIなど
このプロジェクトの目的は、物理的な商品とサプライチェーンに沿ったその経路をデジタルで記録および追跡できるようにする、統一されたマスターデータ管理システムの概念と標準を開発することであり、次の3つのユースケースに重点を置いている。
- 【生産サプライチェーンのデジタル化】医薬品/医療製品/医療機器の配送に付随する書類データを標準化し安全な配送を実現する
- 【標準化されたCO2排出量管理】標準化されたCO2管理を通じて生産およびサプライチェーン全体における持続可能性データ交換を可能にする
- 【データ連携による供給不足解消】デジタルネットワーク化されたサプライチェーンにより、医薬品配送のボトルネックを早期に予測する
次回は、米国や中国、アジアにおけるデータ共有圏の取り組みを取り上げる。(次回に続く)
筆者紹介
小宮昌人(こみや まさひと)
株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO
東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授
日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施。
(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援
(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援
(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援
(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援
専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム/リカーリング/ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。
近著に『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)、『メタ産業革命〜メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる〜』(日経BP)があり、2024年11月には『生成<ジェネレーティブ>DX 生成AIが生んだ新たなビジネスモデル』(SBクリエイティブ)を出版。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。
- 問い合わせ([*]を@に変換):masahito.komiya[*]keio.jp
関連記事
- ≫連載「加速するデータ共有圏と日本へのインパクト」バックナンバー
 アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?
アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?
欧州を中心にデータ共有圏の動向や日本へのインパクトについて解説する本連載。第5回は、自動車向けデータ共有圏であるCatena-XとCofinity-Xを紹介する。 GAIA-Xが目指す自律分散型データ共有、“灯台”プロジェクトは協調から競争領域へ
GAIA-Xが目指す自律分散型データ共有、“灯台”プロジェクトは協調から競争領域へ
欧州を中心にデータ共有圏の動向や日本へのインパクトについて解説する本連載。第4回は、第3回で取り上げたIDSAと並んで業界共通での仕組み作りを担うGAIA-Xを紹介する。 データ主権を守りながら共有していく、IDSAとは?
データ主権を守りながら共有していく、IDSAとは?
本連載では、「加速するデータ共有圏:Catena-XやManufacturing-Xなどの最新動向と日本への産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏の動向やインパクト、IDSA、GAIA-X、Catena-X、Manufacturing-Xなどの鍵となる取り組みを解説していく。今回は第3回としてIDSAを紹介する。 製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト
製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト
本連載では「加速するデータ共有圏(Data space):Catena-XやManufacturing-Xなどの最新動向と日本への産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏の動向やインパクトを解説していく。今回はデータを共有することのインパクトを紹介する。 製造業の「データ共有圏」、2023年の最新動向と5つのポイント
製造業の「データ共有圏」、2023年の最新動向と5つのポイント
本連載では、「加速するデータ共有圏(Data space):Catena-XやManufacturing-Xなどの最新動向と日本への産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏の動向やインパクト、IDSA、GAIA-X、Catena-X、Manufacturing-Xなどの鍵となる取り組みを解説していく。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く
- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生
コーナーリンク