ホンダは宇宙へ、離着陸実験成功の「サステナブルロケット」実機を披露:Japan Mobility Show 2025
ホンダはジャパンモビリティショー2025で、2025年6月に離着陸実験に成功した「サステナブルロケット」の実機を公開した。再使用型機体と再生可能燃料で持続可能な宇宙輸送を目指す。【訂正あり】
ホンダは「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー)2025」(プレスデー:2025年10月29〜30日、一般公開日:同年10月31日〜11月9日、東京ビッグサイト)において、同年6月に北海道大樹町で離着陸実験を行った、再使用可能なことを特徴とする「サステナブルロケット」の実機を披露した。
【訂正】初出時、タイトルに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。[編集部/2025年10月30日17時50分]
今回展示した実験機は、外形寸法が全長6.3m×直径85cmで、乾燥重量900kg/燃料込み重量1312kg。機体には推進力を生み出す「燃焼器」、上昇/下降時に機体を安定させるための「制御翼」、着陸時の衝撃を吸収する「着陸装置」を備えている。
「ホンダの四輪車や航空機であるホンダジェット、F1レーシングカーといった多様な製品開発を通して培ってきた燃焼技術や機体の制御技術などを生かすことで、段階的に技術課題をクリアしてきた」(ホンダの開発担当者)という。
ホンダは2019年より宇宙領域の研究をスタートした。現在のロケットは打ち上げ費用が非常に高額であり、活用のハードルが高いことから、再使用可能なサステナブルロケットの開発に踏み込んだ背景がある。ホンダはサステナブルロケットの開発を通じてロケットの打ち上げコストを低減し、人工衛星の活用拡大や、新たな宇宙輸送手段の提供を目指す考えだ。
高度300mでの実証成功、2029年に準軌道の到達目指す
ホンダは2025年6月17日、北海道大樹町の同社専用実験設備にて、この実験機を用いた離着陸実験を実施した。実験の目的は、ロケットを再使用するために不可欠な、上昇/下降時の機体の安定性や、垂直姿勢での着陸機能といった要素技術を実証することである。
実験の結果、機体は高度271.4mまで到達し、目標地点から37cmの誤差で着陸した(飛行時間56.6秒)。目標としていた機体の離着陸挙動の確認とデータ取得を実現し、実験は成功を収めた。開発担当者は「今回の実験において、ロケットに求められる要素技術の検証は全て済んだといってもいい」と成果を強調した。
ロケットの実用化に向けてはより機体を大型化する必要があり、ホンダは次のステップとして機体の大きさに合わせた技術技術拡張を進めるとともに、2029年に高度100km以上の準軌道へ到達を目指す。
ホンダは今回のJapan Mobility Show 2025で、「“夢”の力が生み出した陸・海・空、そして宇宙のモビリティ」をコンセプトに掲げ、「Honda 0(ゼロ)シリーズ」の新型EVプロトタイプ「Honda 0 α(ホンダ ゼロ アルファ)」なども世界初公開した。
同社 取締役代表執行役社長の三部敏宏氏はプレスブリーフィングにおいて、「ホンダは夢を本気にしてきた会社だ。ロケットの開発はまだその一歩を踏み出したばかりだが、従業員一人一人の挑戦こそが、未来を切り開き、他にはない価値を生み出していく」と語った。
関連記事
 ホンダはジャパンモビリティショーで「0シリーズ」を日本初公開
ホンダはジャパンモビリティショーで「0シリーズ」を日本初公開
ホンダは「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表した。二輪車、四輪車、パワープロダクツ、航空機などさまざまなホンダ製品と関連技術、コンセプトモデルを出展する。出展内容はジャパンモビリティショー2025の開幕まで段階的に明らかにしていく。 ホンダの再使用型ロケットは2029年に準軌道を目指す、初の離着陸実験に成功
ホンダの再使用型ロケットは2029年に準軌道を目指す、初の離着陸実験に成功
ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所は、自社開発の再使用型ロケット実験機の離着陸実験に成功したと発表した。今後は、2029年に高度100km以上の準軌道への到達能力実現を目指して研究開発を進める方針である。 「いくっしょ、モビショー!」の前に、各社特設サイトを確認しておこう
「いくっしょ、モビショー!」の前に、各社特設サイトを確認しておこう
まずは情報収集から! BYDが示す日本市場への本気度、モビリティショーで最新モデルを披露
BYDが示す日本市場への本気度、モビリティショーで最新モデルを披露
BYD Japan Groupが「Japan Mobility Show 2025」の出展概要を発表。乗用車はコンパクトEVやeスポーツセダン、フラグシップSUVを中心に、商用車は日本市場向けに専用設計したEVバスを軸に最新技術を披露する。 マツダの世界初公開ビジョンモデルは「走る歓びは、地球を笑顔にする」を具現化
マツダの世界初公開ビジョンモデルは「走る歓びは、地球を笑顔にする」を具現化
マツダは「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー) 2025」の出展概要を発表した。出展テーマ「走る歓びは、地球を笑顔にする」を具現化したビジョンモデルを初披露する。 人が乗れないヤマ発の「MOTOROiD」第3弾は二輪車型の自律ロボットか?
人が乗れないヤマ発の「MOTOROiD」第3弾は二輪車型の自律ロボットか?
そういえば現在放送中の仮面ライダーは久々に二輪車から人型に変形するロボットが登場しているとか。ヤマ発ではなくホンダ案件ですけども……。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開
- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功
- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売
コーナーリンク
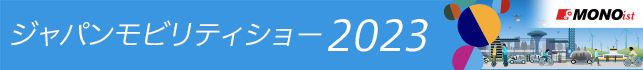





 ホンダの三部敏宏氏
ホンダの三部敏宏氏

