イチから全部作ってみよう(26)プログラムは「処理」と「データ」からできている:山浦恒央の“くみこみ”な話(195)(1/3 ページ)
ソフトウェア開発の全工程を学ぶ新シリーズ「イチから全部作ってみよう」。第26回は、プログラムを構成する2大要素である「処理」と「データ」のうち、データの設計をどのように行うかについて説明する。
1.はじめに
山浦恒央の“くみこみ”な話の連載第170回から、入門者をターゲットとして、「イチから全部作ってみよう」というシリーズを始めました。このシリーズでは、多岐にわたるソフトウェア開発の最初から最後まで、すなわち、要求仕様の定義、設計書の作成、コーディング、デバッグ、テスト、保守までの「開発フェーズ」の全プロセスを具体的に理解、経験することを目的にしています。
興味がある方は、連載第170回からのバックナンバーをご覧ください。
2.前回の振り返り
過去2回は、画面設計の定義方法について取り上げました。
画面設計を作成すると、画面のレイアウトと大まかな処理の流れを紙芝居のように表現できます。また、この画面を発注側に見せることで、細かい仕様を詰めることが可能です。
前回までで、最低限の画面レイアウトと処理の流れが作成できました。今回から、テーマを「データ」に移し、データ設計のイントロダクションの回とします。
3.「アルゴリズム+データ構造=プログラム」
この「数式」みたいなタイトルは、コンピュータ界の神様、ニクラス・ヴィルト(Niklaus Wirth、1934〜2024年)が1976年に書いた書籍のタイトルです。50年たった今読んでも、非常に斬新で示唆に富んでおり、グレンフォード・マイヤーズ(Glenford Myers)著の「ソフトウェアテストの技法」(1979年)、フレデリック・P・ブルックス(Frederick Phillips Brooks Jr.)著の「人月の神話」(1975年)とともに、「50年たっても新しい奇跡の三銃士」と私は思っています。大学の図書館には必ず置いてあるので、この機会にぜひこの3冊を読んでみてください。
「アルゴリズム+データ構造=プログラム」は、プログラムの設計/解析/実装の基礎を「データ構造」と「アルゴリズム(処理方式)」の統合という視点で見た古典的な名著です。「アルゴリズム(処理の論理)とデータ構造(データの表現)は 切り離して考えることはできない」、すなわち、適切にデータ構造を設計しないと、効率的な処理(アルゴリズム)はできないし、適切な処理(アルゴリズム)を設計しないと、データの構造は意味がないと書いてあります。
プログラミングの初級者が「なぜ、このデータ構造と処理方式でプログラムを書くか」を理解する上で、今でも役に立ちます。「データ構造とアルゴリズム(処理)は切り離せない」「プログラミングを設計する場合、どんな構造にすべきか」は、50年たった今でも、非常に新鮮です。
この本では、「プログラムは、単に処理を書くことではなく、データの構造を見定め、そこに適切な処理を組み込むことである」という考え方が一貫していて、理論と実際のプログラム(Pascalで書いてあります)の両面から示しています。一読をおススメします。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証
- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功
- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売
コーナーリンク
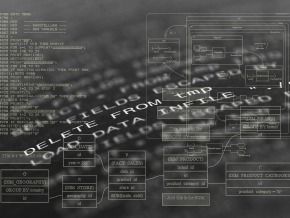 ※画像はイメージです
※画像はイメージです

