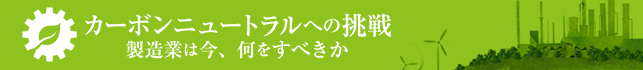HEVの技術を直流マイクログリッドに展開、ダイハツと豊田中研がトヨタ九州で実証:脱炭素(2/2 ページ)
直流マイクログリッドシステムはHEVの電動システムと類似
ダイハツ工業は、先述したバイオガス実証プラントをきっかけに発電した電力を有効活用するマイクログリッドシステムの開発に2021年から取り組み始めた。2022年には、小規模マイクログリッドシステムに適した電力変換器を研究していた豊田中研との共同開発に移行。2023年には、自動車部品の技術やノウハウを用いて改良を重ねたマイクログリッドシステムを試作し、ダイハツグループ九州開発センター(福岡県久留米市)の事務棟に導入して技術検証を実施している。
また、新開発の直流マイクログリッドシステムはHEVの電動システムと構造が類似しており、ダイハツ工業にとっても自社が持つ技術とノウハウを応用する上での親和性が高かったという。
マイクログリッドシステムの開発を進めてきたダイハツ工業と豊田中研にとって課題になっていたのが、技術検証の先にある実証に最適な再エネや蓄電池の設備が整った施設が見つからなかったことだった。一方、トヨタ自動車九州は、工場内に太陽光発電や蓄電池があるものの有効活用できておらず、再エネの電力を生産ラインに使用するための仕組みがないことが課題だった。3社のニーズが合致したことにより、今回の実証実験の実施につながったという。
「SPH」は世界初の3方向接続を可能にする電力変換器
新開発のマイクログリッドシステムで中核的な役割を果たすSPHは、1個のユニットで発電/蓄電/使用の3方向接続を可能にする「世界初」(豊田中研)の電力変換器である。
SPHを中核とする直流主体のマイクログリッドシステムは、従来の交流主体の電力変換システムと比べて電力変換の回数が3分の1に削減できている。このことにより、電力変換によるエネルギー損失を45%削減できたという。
SPHの外形寸法は幅520×奥行き830×高さ450mmである。SPH単体でほぼ全ての電力変換機能を実現できているため、インバーターや大型の商用トランス、DC-DCコンバーターなどが必要な交流主体のマイクログリッドシステムと比べてシステム体積を約10分の1に削減できている。商用トランスを必要としない高周波絶縁トランス技術や、DC-DCコンバーターを不要とする独自統合回路技術、ヒートシンクなど実装部品を小型化できるインバーター高周波制御技術など、HEVの電動システム開発の技術やノウハウを生かした。
SPHにほぼ全ての電力変換機能を集積することによりμ秒レベルの高速制御も可能になった。マイクログリッドシステムでは、電力の使用量に対して、再エネの発電量と蓄電池の充放電量を最適化するためにそれぞれのシステム間での外部通信によって協調制御を行っている。しかし、再エネ発電の変動などに対して外部通信による協調制御が間に合わず遅延が発生し、電力供給不足による瞬停が発生する可能性がある。これに対してSPHは、ユニット内で太陽光発電の変動に即応し、μ秒レベルで蓄電池の充放電力を制御しで瞬停を起こさないことができる。
関連記事
 マルチパスウェイ、EVのCO2削減、車電分離……クルマの脱炭素の形は
マルチパスウェイ、EVのCO2削減、車電分離……クルマの脱炭素の形は
トヨタ自動車の中嶋裕樹氏がマルチパスウェイの意義、EVが製造時に排出するCO2の削減に向けたさまざまなアプローチのアイデア、バッテリーのリユースやリサイクルに向けた“車電分離”の提案など、自動車のカーボンニュートラルについて幅広く語った。 トヨタのスイープ蓄電システムをマツダ本社工場で実証、電池エコシステムの構築へ
トヨタのスイープ蓄電システムをマツダ本社工場で実証、電池エコシステムの構築へ
トヨタ自動車とマツダは、マツダの本社工場内において、トヨタ自動車の車載用電池を活用した「スイープ蓄電システム」をマツダ本社内の電力システムに接続する実証実験を開始した。 トヨタグループ10社でサーキュラーエコノミー、新団体を設立して協調
トヨタグループ10社でサーキュラーエコノミー、新団体を設立して協調
トヨタグループ10社はサーキュラーエコノミーの普及や拡大に向けて協調するCircular Coreを設立した。 BMWとトヨタが水素で協力、成果の第1弾は2028年生産のBMWのFCVで
BMWとトヨタが水素で協力、成果の第1弾は2028年生産のBMWのFCVで
トヨタ自動車とBMWグループは水素分野での協力関係を強化することに合意した。 ダイハツとトヨタが今後の小型車開発の方針を発表
ダイハツとトヨタが今後の小型車開発の方針を発表
ダイハツ工業とトヨタ自動車は海外事業の体制見直しなど今後の方向性について発表した。2023年4月以降に明らかになった国内外の認証不正を受けて、トヨタ自動車が小型車の開発から認証まで責任を持ち、ダイハツが開発を担う体制に変更する。 投資額350億円のダイハツ京都工場の改良が完了、工程数15%減の効率化達成
投資額350億円のダイハツ京都工場の改良が完了、工程数15%減の効率化達成
ダイハツ工業は2022年10月7日、京都(大山崎)工場(京都府大山崎町)で新建屋の建設や改修を行い、竣工(しゅんこう)式を実施したと発表した。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設
- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る
- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に
コーナーリンク