マルチパスウェイ、EVのCO2削減、車電分離……クルマの脱炭素の形は:電動化(1/3 ページ)
トヨタ自動車の中嶋裕樹氏がマルチパスウェイの意義、EVが製造時に排出するCO2の削減に向けたさまざまなアプローチのアイデア、バッテリーのリユースやリサイクルに向けた“車電分離”の提案など、自動車のカーボンニュートラルについて幅広く語った。
自動車技術会 2024春季大会(2024年5月22〜24日、パシフィコ横浜)の基調講演にトヨタ自動車 取締役・副社長の中嶋裕樹氏が登壇した。
トヨタ自動車が推進するマルチパスウェイの意義、EV(電気自動車)が製造時に排出するCO2の削減に向けたさまざまなアプローチのアイデア、バッテリーのリユースやリサイクルに向けた“車電分離”の提案など、自動車のカーボンニュートラルについて幅広く語った。
クルマはいつCO2を排出するか
中嶋氏は公立の小中学校でのエアコン設置率が過去25年間で3%から95%まで増加したケースや、日々の食事を支える第1次産業での変化を例に挙げ、温暖化が与える影響が身近でも感じられることに言及した。
日本は2050年までにカーボンニュートラル社会の実現を目指している。排出される温室効果ガスの約9割がCO2で、このうち自動車を含む運輸部門が20%(約2億トン)を占める。1年間に1万km走行すると、自動車は約1トンのCO2を排出する。杉の木が1年間で吸収するCO2に置き換えると、80本分に相当する。このCO2の排出削減に自動車産業は取り組まなくてはならない。
クルマが排出するCO2は、「部材や車両の製造時」「well to tank(化石燃料の採掘から燃料タンクまで、発電からバッテリーへの充電まで)」「tank to wheel(燃料タンクやバッテリーが動力になるまで)」の3つの領域に分けられる。
HEV(ハイブリッド車)は3領域全てでCO2を排出するが、EVであればtank to wheelのCO2はゼロだ。ただ、日本でEVを充電するには火力発電由来の電力を使用するため、well to tankの観点ではHEVよりもEVの方が排出量が多くなる。製造でのCO2排出に関しては、バッテリーがカギを握る。搭載量が多くなるにつれてCO2排出量が増加するため、HEVよりもPHEV(プラグインハイブリッド車)、PHEVよりもEVが排出削減で不利だと中嶋氏は説明した。日本以上に火力発電への依存度が高いインドネシアのような国でもHEVが最もCO2を出さない電動車となるという。
中嶋氏は「原子力発電が主力のフランスでは状況が変わり、HEVよりもEVがCO2を出さないクルマになる。フランスでは日本と同じく『ヤリス』を製造しているが、日本よりもフランスのヤリスの方が環境に優しいクルマだと言うことができる」と地域の電力事情に大きく左右されることを紹介。各国のエネルギー事情に合わせた最適な電動車の選択肢を提供する戦略の重要性を示した。
これらは新車が排出するCO2の考え方だ。以前から保有されているクルマ(保有車)についてもCO2排出削減を考える必要がある。保有車の台数はグローバルで15億台にも上る。そのほとんどがガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車なので、化石燃料に代わる新たな燃料が注目を集めている。
代替燃料にはバイオ燃料や合成燃料などがある。バイオ燃料は原料となる植物がCO2を吸収し、合成燃料は製造時にCO2を使用するため、保有車に対して即効性のあるCO2排出削減策として期待できるという。また、既存のインフラをそのまま活用できる点もメリットだ。
ブラジルではガソリンにバイオ燃料を混合できる「フレキシブルフューエルビークル」が走っている。サトウキビ由来のバイオエタノール混合燃料は通常のガソリンよりも安価に販売されており、フレキシブルフューエルビークルの普及に貢献しているという。フレキシブルフューエルビークルはインドでも拡大が期待される。また、フレキシブルフューエルビークルのHEV化も進められている。
中嶋氏は「われわれは将来のエネルギーが電気と水素に集約されると考えている。ただ、完全に移行するには時間がかかる。当面はHEVやPHEV、電動化に適したエンジンの開発を進めながら、将来大きなウエイトを占めるEVのCO2排出削減に取り組んでいきたい」と語った。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モビリティの記事ランキング
- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”
- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ
- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に
- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負
- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用
- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く
- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大
- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正
- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る
- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設
コーナーリンク
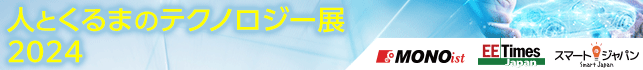
 トヨタ自動車の中嶋裕樹氏
トヨタ自動車の中嶋裕樹氏

