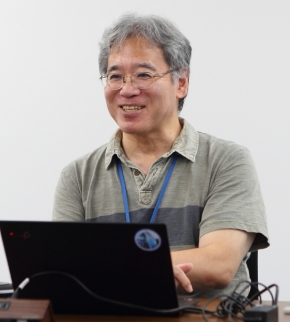ハイブリッドスパコン「地球シミュレータ」は第5世代へ――JAMSTECの上原氏と松岡氏に聞く:AIとの融合で進化するスパコンの現在地(8)(1/4 ページ)
急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第8回は、JAMSTECで「地球シミュレータ」のシステム構築や運用を担当している上原均氏と、生成AI活用を含めデータサイエンスの研究を担当している松岡大祐氏に話を聞いた。
連載第7回で紹介した「地球シミュレータ」の後編に当たる今回は、システムの構築や運用を担当しているJAMSTEC(海洋研究開発機構) 計算機システム技術運用グループの上原均氏と、生成AI(人工知能)活用を含めデータサイエンスの研究を担当している同機構 データサイエンス研究グループの松岡大祐氏のインタビューをお届けする。(インタビューは2025年8月20日に実施)
⇒連載「AIとの融合で進化するスパコンの現在地」バックナンバー
1990年代に「地球シミュレータ計画」がスタート
――地球シミュレータの開発の経緯を教えてください。
上原氏 当時の科学技術庁の「地球シミュレータ計画」の下、地球規模の気候変動などの解明を目的に新たなスーパーコンピュータを開発しようと、1990年代半ばにプロジェクトが始まりました。地球全体を表した大気大循環モデルにおいて、それまでのシミュレーション格子(メッシュ)の解像度は緯度、経度方向ともにおよそ100kmでしたが、それぞれをおよそ10kmに細かくしようという目標が設定されました。鉛直方向も同様に高解像度化する目標が設定されました。
そのような解像度において妥当な時間でシミュレーションを終えるには5TFLOPSの実効性能と32TFLOPS以上のピーク性能が必要との試算に従い、当時の一般的なスカラー型のアーキテクチャでは実現は難しいことから、その時のスパコンの主流であったベクトル型を採用して開発が進められ、2002年3月に稼働を開始したのが「地球シミュレータ」です。TOP500ベンチマークは35.86TFLOPSで、2002年6月から2004年6月まで世界トップでした。
――先ほどシミュレータ棟(連載第7回の図9を参照)を見せていただきましたが、現在のデータセンターとはかなり造りが違っていますね。
上原氏 これだけの規模のスパコンを収容するデータセンターの設計ノウハウが当時はほとんどなく、担当者が悩みながら作業を進めていたのを覚えています。免震構造を採用し、外来の電磁ノイズを遮断するために外壁にシールド素材を使ったり、鉄骨に絶縁処理を施したり、建屋周囲に6本の避雷柱を立てた架空地線方式による被雷対策などの工夫を行っています。また、天井照明(蛍光灯)からも電磁ノイズが出ますので、光源をマシンルームの外に置いてアクリルチューブでマシンルーム内に明かりを引き込むライトガイド方式を採用しています。
――現在のマシンルームにはスペースの余裕が見られましたが、初代の地球シミュレータはどういった規模だったのですか?
上原氏 マシンルーム全体を占めていました。インターコネクトのケーブル長を等しくするために、ネットワークノードを中心に置いて、ベクトルプロセッサを搭載した計算ノードをその周りにドーナツ状に並べた形です。
 シミュレータ棟のマシンルーム全体を占めていた初代の地球シミュレータ。図中の左上において、中心の水色がネットワークノード(クロスバースイッチ64筐体+制御部1筐体)、その周囲の濃い青色がベクトルプロセッサを搭載した計算ノード(筐体当たり2ノード×320筐体)、白がディスク装置などだ[クリックで拡大] 出所:海洋研究開発機構
シミュレータ棟のマシンルーム全体を占めていた初代の地球シミュレータ。図中の左上において、中心の水色がネットワークノード(クロスバースイッチ64筐体+制御部1筐体)、その周囲の濃い青色がベクトルプロセッサを搭載した計算ノード(筐体当たり2ノード×320筐体)、白がディスク装置などだ[クリックで拡大] 出所:海洋研究開発機構――その後、第2世代(ES2)、第3世代(ES3)と進化していくわけですね。
上原氏 第2世代の稼働は2009年3月です。NECのベクトル機「SX-9」を採用し、ピーク性能は初代の3.2倍に相当する131TFLOPSに上がり、一方で設置面積は3分の1ほどに小さくなりました。ES2は「HPC Challenge」というベンチマークの高速フーリエ変換処理部門で世界第1位を獲得し、応用性能の高さを示しました。さらに2015年3月にはNECのベクトル機「SX-ACE」を採用した第3世代が稼働し、ピーク性能は1.3PFLOPSにまで高まりました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開
- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証
- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは
- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター
- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演
- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功
- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア
- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく
- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発
- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断
コーナーリンク