なぜ木を使うのか、IoTデバイスで目指す“穏やか”な技術との関わり:モノづくり×ベンチャー インタビュー(1/2 ページ)
「情報テクノロジーと人の佇まいが無為自然に調和した世界を実現する」をビジョンとし、自然素材のIoTデバイスに取り組み、新たな価値提供を目指すのがmui Labである。mui Labの共同創業者で、Software Architectの久保田拓也氏と、同社取締役CTOである佐藤宗彦氏に、同社を立ち上げるきっかけや製品のコンセプト、また今後の展望などについて話を聞いた。
技術の進歩は人間の生活を豊かにする一方で、逆に人間らしさを失わせる――。こうした議論は古くからさまざまな分野で行われてきたことである。こうした中で「情報テクノロジーと人の佇まいが無為自然に調和した世界を実現する」をビジョンとし、自然素材のIoTデバイスに取り組み、新たな価値提供を目指すのがmui Labである。
mui Labは2017年10月設立のベンチャー企業で、2020年2月には木製のスマートデバイス「mui」を発売した。「mui」は一見するとシンプルな木板だが、手で触れると天気、スイッチや調光のアイコン、メッセージなどがLEDで浮かび上がる。手書きの文字なども送ることができ、家庭内のコミュニケーションハブとして機能する。用途を終えると表示は消え、インテリアとして空間に溶け込むというものだ。
本稿ではmui Labの共同創業者で、Software Architectの久保田拓也氏と、同社取締役CTOである佐藤宗彦氏に、同社を立ち上げるきっかけや製品のコンセプト、また今後の展望などについて話を聞いた。
NISSHAの社内ベンチャー制度を活用して誕生
―― まずは、mui Labの成り立ちについて教えてください。
久保田氏 mui Labはもともと京都に本社を置くNISSHAの社内ベンチャー制度から生まれました。そもそものきっかけは、2015年5月に開催されたニューヨークの国際現代家具見本市(ICFF)にNISSHAが初出展したことです。その際に現CEOの大木和典と共同創業者でクリエイティブディレクターの廣部延安が、「mui」とコンセプトが近い別形態の製品「Wall tile(ウォールタイル)」を開発しました。
それが海外のメディアにも取り上げられるなど好評だったので、その事業を拡大しようと試みたのですが、さまざまなハードルがありそのままでは拡大が難しいということになりました。そこで、あらためて別形態で新しくコンセプトを考え直して生まれたのが、現在の「mui」の原型です。そこから開発を重ね、実際に量産して展開していくために、社内ベンチャー制度に応募し、2016年2月に承認を得ることができました。そして、プロジェクトメンバーで、2017年10月末にNISSHAの子会社としてmui Labを創業し、2019年の5月にMBO(経営陣買収)という形で完全に独立しました。
佐藤氏 mui Labは「Calm Technology(生活に溶け込み人が無意識的に活用できる技術)」をキーワードにサービスを提供しています。現代において情報技術は私達の生活に欠かせないものになっていますが、一方で情報量が多過ぎるなど、人々の生活を逆に穏やかではないものにしているとも考えられます。このような現状に対して、人々がよりよい生活を送るために、適切な情報との関わり方というものを提供していくというコンセプトを持っています。
なぜ素材に「木」を選んだのか
―― 「適切な情報との関わり」を象徴するものとして「mui」を作るにあたり、木を材料に選んだ理由を教えてください
佐藤氏 「Wall tile」の開発後、大木や廣部を中心に大理石などさまざまな素材を試したのですが、展示会で紹介する中で来場者の反応が一番よく受け入れられた素材が木でした。人間が生活する空間に自然に存在し、触れたくなるものとして木という存在があり、それを確認できたのでハードウェアの素材として選んだという形です。その結果、海外のデザイナーや企業から、非常に良いフィードバックやお声がけを数多くいただくことができました。われわれが実現したい「心地よいデジタルのあるライフスタイル」や「穏やかな情報との関わり」に関しても、海外、特に欧州の方から非常に高い評価を受けていると感じています。
―― 一方で、素材に木を選んだ苦労もあったのではないでしょうか。
久保田氏 工業製品、特に電子部品が入る製品に木を使うためには、難燃性の確保など、量産化を進めるのが難しい点がいくつか出てきます。NISSHAで立ち上げに向けた開発を進めていた時もNISSHAのエンジニアからは「これは難しすぎる」とかなり反対されました。NISSHA自体がプラスチックの成形品に自然の模様を印刷した車の内装パーツなどを供給しているメーカーでもあり、社内からは「そういうものを使えばよいのでは」という話がありました。また、社外からも「なぜ印刷ではないのか」といわれることもありました。
詳細についてはお話できないこともありますが、木を使うために生まれた課題やそれでさらに生まれる課題などが複雑に絡まり合う中、一つ一つクリアし、なんとか量産できる形にまで持っていくことができました。「Wall tile」の製作後に素材を木に転換したわけですが、結局最終的に製品を出せるようになるまでに約5年かかりました。それほどのハードルがあったのは確かです。しかし、製品に対する良いフィードバックなどを聞いていると、途中でブレずに突き詰めてよかったと思います。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
中小製造業の記事ランキング
- まるでApple製品のような? シャレオツ仏像フィギュア
- 「奇跡の一本松」を保存した生物研究所が乳がん触診シミュレーターを開発した理由
- DXで成功する中小企業経営者が本音を語り合うWeb番組 2月18日配信開始【予告動画追加】
- これだけは知っておきたい! 「マーケティングって何?」(後編)
- ワクワクする人を察し、自分のワクワクを人に伝え、縁を紡げ
- 社長はプロレーサー! ツーリングでマーケティング
- 女子力とは「誰かのためになることを考える力」
- ワクワクする心が燃料となる リーン・プロダクトアウトとは?
- ピンチはチャンス!? 町工場から生まれた美顔器
- 日本のモノづくりはこれからどうなる? ――大企業と中小企業、それぞれの思い
コーナーリンク


 NISSHAの「Wall tile」 出典:NISSHA
NISSHAの「Wall tile」 出典:NISSHA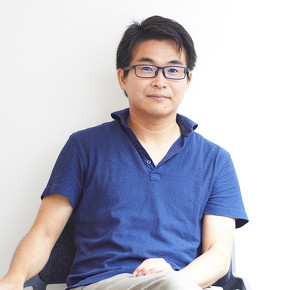 mui Labの共同創業者で、Software Architectの久保田拓也氏
mui Labの共同創業者で、Software Architectの久保田拓也氏


