フロンレスからネットゼロへ、セイコーエプソンが語る環境経営の本気度:脱炭素(1/2 ページ)
アイティメディアはオンラインセミナー「MONOist 環境問題対策セミナー 2025 春『儲かる環境問題対策』を実現するために何が必要か」を2025年6月5日に開催した。本稿では、セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏による基調講演の内容を抜粋して紹介する。
アイティメディアの産業向けメディアであるMONOist、EE Times Japan、EDN Japan、スマートジャパンは、オンラインセミナー「MONOist 環境問題対策セミナー 2025 春『儲かる環境問題対策』を実現するために何が必要か」を2025年6月5日に開催した。本稿では、セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏による基調講演「エプソンの環境経営〜人と地球を豊かに彩る〜」の内容を抜粋して紹介する。
環境問題への取り組みの大きな契機となったフロンレス活動
セイコーエプソンはパーパスとして「『省・小・精』から生み出す価値で人と地球を豊かに彩る」を掲げ、「省(より効率的に)・小(より小さく)・精(より精緻に)」に関するさまざまな技術やその考え方を基に社会課題解決に取り組んでいる。環境問題への取り組みはその大きなテーマの1つだ。
セイコーエプソンでは1988年にはフロンレス宣言をし、1993年に達成するなど、古くから環境問題に注目し積極的に取り組んできた。2008年には2050年をゴールとする「環境ビジョン2050」を策定したが、2021年に脱炭素と資源循環をはじめとした環境問題への取り組みを加速することを社内外にあらためて示すために、達成目標などを具体的に設定した形に改定している。
環境問題に対し全社を挙げて取り組んだフロンレス活動について木村氏は「フロンレス活動を進めた際には社内でも賛否はあったが『企業として環境に悪いと分かったものを使うわけにはいかない』というトップの強い意志と決断があった」と当時を振り返る。これは「信頼される良い会社でありたい」という企業姿勢を示すもので、現在取り組んでいる脱炭素や資源循環の活動の根底にもあるものだ。
ただフロンレス化の道のりは簡単ではなかったという。「多くの部門に影響が出るため、全社のフロンレスを統括する組織を発足させ、各製造部門からも担当者を選任し全社で約300人にわたる推進体制を構築した。その上で実態把握から活動計画を作成した。具体的には、洗浄工程の見直し、無洗浄化の検討、無洗浄化できない場合の水洗浄への切り替え、フロンレス前提の新規開発というステップを踏んで実現した」と木村氏は説明する。
こうした全社一丸となった取り組みにより、まず日本でのフロン全廃を1992年に実現した。1993年には全世界での洗浄工程におけるフロンレス化も達成している。「こうした経験が今の脱炭素や資源循環への活動でも生きている」と木村氏は語る。
なぜエプソンは環境問題に本気で取り組むのか
現在は世界的に環境問題対策が大きなテーマとなっている。パリ協定やSDGsなどにより、ユーザーはより環境低減につながる商品やサービスを求める傾向が高まってきた。また、企業評価でも投資家を中心とするステークホルダーから環境課題への積極的な対応と情報開示が求められている。最近では、情報開示のフレームワークを含め、開示を義務化する規制もみられる。採用面でも入社希望者から環境活動への関心を聞くことが多くなったという。
逆に環境問題に積極的に対応しない場合のマイナス面も拡大している。国際的な批判などに加え、環境税や企業への投資価値の低下、人材流出など実質的なマイナス効果が生まれ始めている。また、製品に対する環境規制も強まり、対応できなければ製品が市場に投入できなくなる。資源循環についても重要性が増しており、特に日本においては限られた資源の中で、資源が使えなくなるリスクを想定しておくことが不可欠だ。「このように事業や生活を維持していくためには環境対応は絶対的な条件になってきた。それに企業としていち早く対応を進める」と木村氏は強調する。
セイコーエプソンでは、環境問題に取り組む意味を「企業と社会が持続可能で、こころ豊かな社会を実現するため」とする。活動を進める中で、製品ライフサイクルの改善(商品や生産プロセスでの資源使用量削減、エネルギーの効率化によるコスト削減)、法規制の順守、顧客ニーズの変化や投資家の期待への適応、企業イメージとブランド価値の向上、新規ビジネス創出、社員のモチベーションアップなどさまざまな面で効果が生まれているという。木村氏は「結果的に企業価値向上および業績貢献という正のインパクトを与えられると考えている」と述べる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製造マネジメントの記事ランキング
- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張
- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築
- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術
- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX
- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈
- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる
- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任
- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資
- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正
- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰
コーナーリンク
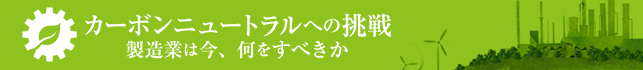
 セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏による講演の様子[クリックで拡大]
セイコーエプソン 地球環境戦略推進室 副室長の木村勝己氏による講演の様子[クリックで拡大]






