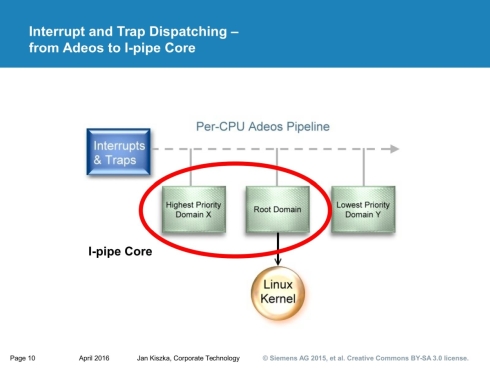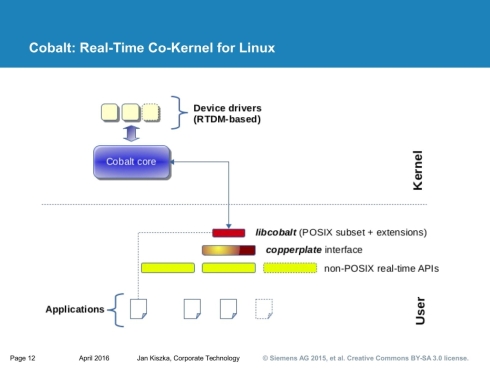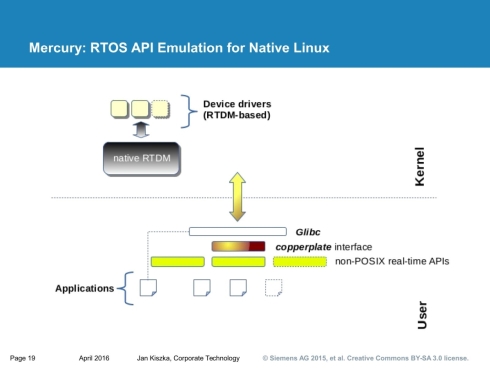Linuxでハードリアルタイムを実現するもう1つの選択肢「Xenomai」:リアルタイムOS列伝(35)(2/3 ページ)
「Xenomai」の実装は“Co-Kernel”
さて、そのXenomaiは基本的に“Co-Kernel”という実装である。それではCo-Kernelとは何なのか? を端的に表現したのが図3である。図3内左側のScheduler AがLinuxの標準スケジューラーであり、これにパッチを当てる形でもう1つ別のスケジューラーも走らせる。この際Interrupt Dispatcherのルーティング先にもパッチを当てることで、一部のInterruptに関してはScheduler Bで直接受けてハンドリングできるようにする。こうした仕組みを取ることで、Linuxの上に、Linuxのスケジューラーとは別に動くTaskを稼働させることができる。
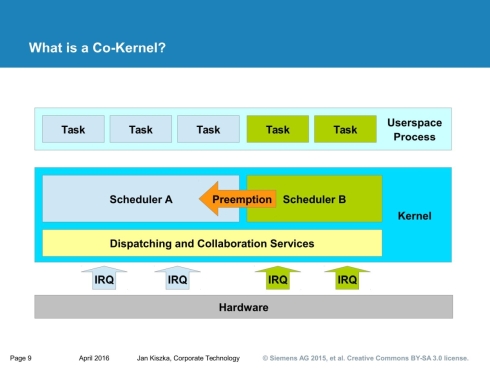 図3 LinuxはこうしたCo-Kernelを標準でサポートしているわけではない。このため、Co-Kernelの実現にはカーネルへのパッチが必要となるのはXenomaiに限った話ではない[クリックで拡大]
図3 LinuxはこうしたCo-Kernelを標準でサポートしているわけではない。このため、Co-Kernelの実現にはカーネルへのパッチが必要となるのはXenomaiに限った話ではない[クリックで拡大]もちろん、このScheduler AとScheduler Bが完全に独立していると、CPUリソースなどを取り合うことになってしまうので、Scheduler Bがフルに動く時には一瞬Scheduler Aを止める形になる。実装としてはいろいろあって、Scheduler BをHighest Priorityを持つTaskとしてScheduler Aに登録しておくといった方法が一番楽ではあるが、これだとInterruptの処理が遅れる場合もある。
このPriority周りに関してのDispatchのメカニズムが先述したI-pipeである(図4)。要するにISR(割り込みハンドラ)の手前に入り、Interruptをいったん受けてDispatchするものだ。図3で言えば、“Dispatching and Collaboration Services”と、あとScheduler BからScheduler AへのPreemptionがこのI-pipeとして実装されることになる。
アプリケーションから見た時の仮想的なハードウェアとして提供されるのがXenomai Nucleusである(図5)。このNucleusには、POSIXやVxWorksなどさまざまなスキンが用意されており、これを利用する形で複数のRTOSが稼働できる(同時稼働が可能か? というのはまた別の問題)。
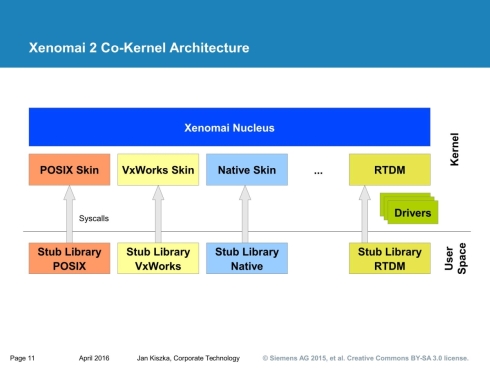 図5 右端のRTDMはReal-Time Driver Modelの略。ハードウェアのアクセスは、このRTDMへのStub Library経由で行い、その先でRTDMに対応したドライバが動くことになる[クリックで拡大]
図5 右端のRTDMはReal-Time Driver Modelの略。ハードウェアのアクセスは、このRTDMへのStub Library経由で行い、その先でRTDMに対応したドライバが動くことになる[クリックで拡大]さて、Scheduler BをつかさどるのはCobalt coreと呼ばれている。これはデュアルカーネル用に設計されたもので、続くXenomai 3ではシングルカーネル(既存のカーネルを完全に置き換えて動作するもの)用のMercuryも提供されるようになったが、Xenomai 2ではこのCobaltのみである(図6)。
これに続き、2015年にはXenomai 3.0が登場した。3.0の最大の特徴は、APIがPOSIX centrixになったことかと思う。またネイティブLinuxへのサポートも新たに追加された項目である。このネイティブLinuxに対応するためのものが先述したMercuryである(図7)。POSIX APIへの移行やMercuryの提供などもあって、使い勝手そのものが多少Xenomai 2から変わったという話もある。またXenomai 2ではソースを展開するとksrc\archの下に機種別のファイルが置かれていたが、Xenomai 3ではネイティブLinux対応ということでこれがなくなっている。もっとも、これはMercuryを使った場合の話で、Cobaltは引き続き機種別対応になっている。それもあり、kernel\cobaltの下には引き続き機種別ファイルが並んでいる。
ちなみにXenomai 3.0.1ではSHやNios IIへのサポートがなくなり、代わりにArm64が追加された。このサポート機種はだんだん減っており、2020年2月にリリースされたXenomai 3.1ではArm/Arm64/PowerPC/x86になっている(Blackfinが落ちた)。現在は3.2.1が最新のStable版としてリリースされている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ
- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める
- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう
- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に
- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】
- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用
- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革
- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発
- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順
- 10BASE-T1S対応のPMDトランシーバー、CANのように簡便性とコスト低減を両立
コーナーリンク