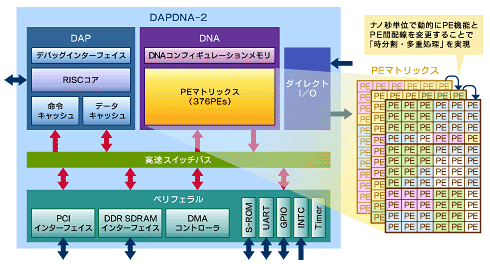Pentium 4を上回る性能でASICやFPGAを駆逐:組み込み企業最前線 − アイピーフレックス −(1/2 ページ)
ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサへの注目が組み込み分野で徐々に高まっている。それに比例して頭角を現しているのが、国内ベンチャーのアイピーフレックスだ。海外では技術力でビジネスを成功させている半導体ベンチャーは珍しくないが、アイピーフレックスは国内でその先駆けとなり得るか。
汎用プロセッサ、ASIC、FPGAの欠点を解決
汎用プロセッサでは要求処理をカバーし切れず、かといって特定処理ごとにASIC(Application Specific Integrated Circuit)などで専用ハードウェアを作り込むのはコストや開発期間が合わず、システムの柔軟性も奪われる。こうしたジレンマを解消してくれると期待されているのが、回路構成を動的に変更できる「ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサ」(DRP)である。
リコンフィギュラブル型プロセッサとしてはFPGA(Field Programmable Gate Array)が広く使われているが、FPGAは回路設計情報(プログラム)を一度ロードしたらリセットするまで回路を変更できない。それに対し、現在注目されているDRPは稼働中に回路をダイナミックに変更できる点が大きい。発展著しい性能面でもFPGAのみならずASICの領域を脅かしつつある。
この分野で大手のNECエレクトロニクスなどとごして国内市場をリードするのが、創業わずか6年目で従業員80名強の国産ベンチャー、アイピーフレックスだ。代表取締役社長 CEOの萩島功一氏は「われわれが製品を発表した当時、(DRPの)市場はまったくなかった。それがいまや市場が大きく立ち上がりそうなところを迎えている」と話す。
性能はPentium 4の50倍以上
アイピーフレックスは、独自開発のDRP「DAPDNA」(ダップディーエヌエー)のコンセプト実証用チップを2002年9月に発表。2004年9月には、現行の実用チップ「DAPDNA-2」をリリースしている。DAPDNA-2は130nm(ナノメートル)プロセスで動作周波数166MHzというスペックを持つ。同社によれば、Pentium 4(3GHz)と比べて最大50倍強の性能を発揮するという。もちろん、動作周波数が低いDAPDNA-2の方が消費電力も断然低いのはいうまでもない。
創業者の佐藤友美氏(取締役副社長 CTO)は、かつてインテル互換プロセッサの開発とビジネスを手掛けた経験がある。そこからインテルアーキテクチャと互換プロセッサビジネスの限界を感じ、並列パイプライン処理を強みとする独自アーキテクチャのDAPDNAを発案したのだ。
「アクセラレータ内蔵プロセッサ」ともいえるDAPDNA-2のアーキテクチャは、図1のようになっている。
同社独自の32bit RISCプロセッサである「DAP」と376個のプロセッサエレメント(PE=演算器)がマトリックス状に並ぶ「DNA」から成る。DAPはソフトウェアを実行しながら高速処理が必要な部分をアクセラレータ役のDNAに担わせる。DAPからの呼び出しでDNAのPE間配線および各PEのパラメータ設定を動的に変更することで、アプリケーションに合わせた最適な回路構成を実現する。DNAのコンフィグレーションメモリには、4通りの回路構成情報を仕込むことができる。1クロック(約6ナノ秒)で回路構成を切り替えられる点がミソである。
国内外でいくつかの半導体メーカーが独自DPRを発表している中で、DAPDNAが市場をリードしているといえるのは、実際にデザインインを多く獲得しているからだ(2006年2月現在で15件以上)。例えば、NTTアドバンステクノロジが販売するネットワークプロセッサボード「Gbit-RNP」は、DAPDNA-2を2個搭載する。Gbit-RNPは、ギガビットファイアウォールなどに活用できる。また、理化学研究所が運営する大型放射光施設で使うX線回折顕微鏡にも採用されている。海外での実績もある。ある米国企業は、米国政府の支援を受けて開発中のタンパク質解析装置にDAPDNA-2を本採用するための評価を行っている。
上記の例を見ても分かるとおり、デザインインを獲得したのは、いずれも組み込み分野でも超ハイエンドで特殊な製品ジャンルだ。これには理由がある。「ベンチャーのわれわれが最初からマスマーケットを狙っても失敗するだけ。いくらプロセッサが魅力的でも、開発ツールやミドルウェアもそろっていないプロセッサを機器メーカーは使わない。だが、ハイエンド分野なら性能だけで勝負でき、突破口になると考えた」(萩島氏)。この戦略は功を奏したようだ。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | アイピーフレックス |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
組み込み開発の記事ランキング
- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ
- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める
- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう
- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に
- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】
- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用
- ルネサスが「Renesas 365」を提供開始、電子機器の開発期間を大幅短縮
- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革
- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発
- 光量子コンピュータ実用化に向けた「10dBの壁」を突破、誤り耐性の獲得にも寄与
コーナーリンク
 アイピーフレックス代表取締役社長 CEO 萩島功一氏
アイピーフレックス代表取締役社長 CEO 萩島功一氏