コマツダイキン明電舎古野電気ANAが故障予測に活用した「PHM」とは:PHM Conference 2019 in JAPANレポート
電通国際情報サービスが開催した「PHM Conference 2019 in JAPAN 〜 様々な取り組み事例に学ぶ 〜」では、コマツ、ダイキン工業、明電舎、古野電気、ANAの5社が登壇し、故障予測などに役立つ「PHM」の取り組み事例を紹介した。
電通国際情報サービス(以下、ISID)は2019年6月6日、東京都内においてPHM関連のイベント「PHM Conference 2019 in JAPAN 〜 様々な取り組み事例に学ぶ 〜」を開催した。
PHMとは「Prognostics and Health Management」の略で、日本語では「故障予測と健康状態の管理」と訳される。製造現場の設備や製品の稼働状況を「Health(健康)」にたとえ、その状態を維持するよう運用/管理するシステム工学的なアプローチだ。
PHMを実践する上で必要なのが「インダストリアル・ビッグデータ」である。かねてISIDは、製造業のデータ活用にはインダストリアル・ビッグデータの特性を理解する必要があると説いている。インダストリアル・ビッグデータとは、主に製造や保全など、エンジニア知見が必要な領域で用いられるデータのことで、定常的に収集できる製品・設備の稼働関連データを指す。
インダストリアル・ビッグデータは、市場からの製品稼働データや不具合履歴データといった「製品設計開発向けデータ」と、製造ラインでの設備稼働データに代表されるような「工場での製造生産向けデータ」に大別される。ドメインに特化したデータである反面、異常値やデータ分析に利用できないノイズデータなどを排するといった「前処理」に手間が掛かる特性を持つ。
今回のカンファレンスでは実際にインダストリアル・ビッグデータを活用し、PHMを実践する企業5社が登壇。それぞれの取り組みを紹介した。
コマツのIoTビジネス戦略とPHM
基調講演に登壇したのは、建設機械の遠隔稼働管理システム「KOMTRAX」を開発したコマツだ。同社は、IoT(モノのインターネット)という言葉が普及する前から機械の稼働データを分析し、建機の品質向上や、遠隔地からの建機の稼働状況把握に役立てている。
コマツは2019〜2021年度の中期経営計画に、「DANTOTSU(ダントツ) Value」を掲げている。これまでの高品質・高付加価値商品の提供を大前提に、建機稼働の可視化などの「サービス」と、施工全体の安全性と生産性を向上させる「ソリューション」を加え、包括的な「DANTOTSU」で新たな価値を提供する戦略だ。コマツ 開発本部 ビジネスイノベーション推進部 部長の浅田寿士氏は「商品、サービス、ソリューションはバリューチェンであり、これをつなぐものがデータです」と説明する。
では、DANTOTSUサービスを実現するためには、どのようにデータ活用をすべきなのか。浅田氏が紹介したのは、巨大なダンプトラックで銅鉱山を採掘する鉱業系企業の事例だ。その会社の課題は「生産コストの低減」だった。浅田氏は「お客さまの課題を“分解”すると、コマツが課題解決に貢献できることはわずかだったことが判明したのです」と説明する。
生産コストの算出は、「TCO(総保有コスト)÷生産量」だ。コマツが高品質のトラックを提供することは、TCOの削減に貢献するが、生産コストの低減全体から見れば、対策の一部でしかない。
TCOの削減には、修繕・修理活動で稼働コストを低減すればよい。そのためには、継続的なモニタリングでマシンダウンタイムや故障を低減したり、コンディションベースでコンポーネントメンテナンス寿命を延長したりする施策が不可欠だ。同時に継続的な現場の改善活動で、生産量(生産性)の向上を図る必要がある。具体的には、現場オペレーションの改善、非効率部分の低減、トレーニングなどがそれにあたる。
浅田氏は「こうした施策の実現を支えているのが、機器から収集したインダストリアル・ビッグデータや無線通信・テレマティクスです。われわれはこうしたデータでPHMを実施してお客さまに新たな価値を提案し、(お客さまの)ビジネスを支援していきたいのです」と訴える。
建機メーカーが顧客に対して生産性向上策の提案をすることは、「出しゃばり」と捉える向きもあるだろう。しかし、浅田氏は「われわれは機械のコンディションをモニタリングする過程で、顧客のオペレーションが“うっすら”分かります。ですから、モニタリングデータを解析することで、業務改善(建機材の最善の使い方)の提案ができる。データに裏打ちされた改善策であれば、お客さまは納得します」と説明する。なお、2019年4月末時点で、KOMTRAXは56万2000台の建設機械をモニタリングしているとのことだ。
データドリブン活動で大切なのは、「何のために実施するか」という目的を明確にすることだ。また、いきなり難しい技術に挑戦するのではなく、できるところから導入し、「80点を目指さず、50点でも前進できる課題設定に」(浅田氏)して効果を見ながら進めていく姿勢が必要だという。もちろん、技術的なチャレンジは継続していく必要がある。
最後に浅田氏は、「(収集した加工前の)データは“ごみ”です。データドリブン活動は“ごみ”を収集し、試行錯誤しながら“ごみ”を価値ある情報=インテリジェンスに昇華させなければなりません。製造業がデータ活用で“攻めて”いくためには、(“ごみ”収集のような)地道な活動から始める必要があります」と語り、講演を締めくくった。
ダイキンにおけるAI活用とHVACシステムの故障予知事例
空調機/化学製品のグローバルメーカーであるダイキン工業は、現在の戦略経営計画「FUSION20」の中で、13の全社重点戦略テーマを掲げている。その筆頭にあるのが、「IoT/AI技術を活用した空調ソリューション事業の加速」だ。製品稼働、設備稼働といった「モノのデータ」と、空調機、建築、気象、空気質といった「コトのデータ」をデジタル環境で統合し、製品ライフサイクルの各フェーズでAI(人工知能)やデータ分析技術を活用してサービスの高度化、効率化を実現する戦略である。
ダイキン工業 テクノロジー・イノベーションセンター 主任技師の小倉孝訓氏は、「PHMを実施するには“モノ”と“コト”の両方のデータが必要です。『どのような環境で稼働しているのか』といったコトのデータがなければ、故障予知/診断はできません」と語る。
小倉氏はPHMの取り組み事例として、空調機をオンラインで遠隔監視し、センサーデータを用いた故障予測サービスを提供する「エアネット」のデータを用いた分析事例を紹介した。
実はエアネットサービスは、PHMに本格的に取り組む前――20年以上前――から提供している。ただし、その分析方法はこれまでのドメイン知見に基づいて、「特定センサーの値が閾値を超えたらアラートを出す」といったものだった。
小倉氏は「ダイキンは過去から積み上げた知見を基に、故障予測サービスを提供しています。ただし、これまでの取り組みでは、空調停止を招いた要因までを特定することは困難でした。ですから、故障の再発による繰り返しの訪問を避けるため、故障につながる可能性のある部品も併せて交換せざるを得ないケースが多かったのです」と語る。
空調停止の要因で多いのは、圧縮機の故障だという。圧縮機は空調機の心臓部分で、最も交換費用の高い部品だ。故障の原因は、他の部品の劣化や故障がトリガーになることも多いが、解明できない故障モードも多い。
今回のデータ活用で目指すサービスは「修理の一発完了」と、空調の変調を早期に発見し、適切なメンテナンスを施す「予防保全」である。そのためには、データ分析で圧縮機故障の真因を解明する必要があった。
そこでダイキンでは過去10年分の空調機の運転データと修理対応履歴データを活用し、ISIDと、同社の関連会社で故障予知技術を提供するプレディクトロニクス(Predictronics)の協力を得て、故障予知につながるデータ分析を実施した。
その方法はこうだ。
まず正常データでモデル生成する。そして、作成したモデル診断対象のデータを入力し、「正常であればこの値が出るはずだ」ということをAIに学習させ「予測値」を割り出す。これと「実測値」を比較し、両値の乖離度で異常検出する。データの前処理ではドメイン知識を生かし、特徴量を選択した。複数のパラメータを試した結果、有識者の組合せ入れ込んだ組合せがもっとも有効だったという。
小倉氏は今後の課題として「異常捕捉率と誤検知率のバランス」や「予防保全コストに見合うサービスメニューの提供」さらに「予測モデルの再学習の必要性」を挙げる。今後は本格的な実装に向けて、ビジネスモデルの確立や、現場の業務フローを考慮したKPI(重要業績評価指標)の設定が必要になるとのことだ。
データに基づく設備状態診断における課題解決に向けた取組み
121周年を迎えた電気機器メーカーの明電舎は、設備の安定稼働支援と点検作業の合理化、高度化を目的に、PHMの実践に取り組んでいる。高経年設備の増加や、少子高齢化による熟練技術者の不足、設備停止時間のミニマム化といった課題を解決するには、PHMは不可欠だ。
ただし、明電舎 ICT統括本部 企画部 主管技師の伊藤博起氏は「データ駆動型故障検知は非常に有効ですが、万能ではありません」とクギを刺す。
情報技術の進展を背景として、多種多様な大量データの取得、取扱が可能になった。“いつもと違う”状況を捉える方法として、データ駆動型故障検知は有用だ。しかし、伊藤氏は「通常時(データ)との乖離度は、必ずしも故障の重要度と一致しているとはいえません。また、学習データが全ての正常値を現しているものでもありません。環境が変われば、正常範囲が広がる可能性もあります。ですから単体ではなく、他の手法と組み合わせることが有効です」と説く。
明電舎もダイキンと同様、機器に取り付けたセンサーから情報を収集し、遠隔監視での障害発生検知を早期から実施していた。一定間隔で瞬時値を測定し、閾値判定で障害発生を検知する方法だ。ただしこの手法では、障害発生は検知できるものの、その故障が発生する前の予兆を捉えることは難しい。
では、故障予兆を捉えるにはどのような手法が有効なのか。伊藤氏は、「検出したい障害の情報が含まれるデータをあらかじめ検討したうえで、データを取得することです。つまり、データモデリングによる事前の有効性確認が必要なのです」と説明する。
明電舎がモデリングツールとして利用したのが、故障予知のためのモデルベースのエンジニアリング分析ツール「MADe」だ。選定の理由は、システム間の故障に相関関係と影響フローをモデルで表現していること、視覚的に故障ロジックを解析できる点を評価したからだという。
MADeによる分析の結果、故障が起きたときの影響伝播のプロセスと、既存センサーの診断率を把握することができた。これによりセンサーの数はそのままにモニタリング対象を変更することで、診断率が向上する可能性があることが判明したという。
最後に、伊藤氏は、「センサーをやみくもに追加しても、検出したい故障の予兆を捉えられるとは限りません。場合によっては設備停止が発生する可能性もあります。これを防止するには、『どこの』『どのようなデータが』必要なのかを明確にしたうえで、事前の取り組みを実施することが重要です」と力説した。
MADeを活用した舶用機器保全設計への取り組み
世界で初めて魚群探知機の実用化に成功し、さまざまな船舶用電子機器の製造を手掛ける古野電気も、MADeを活用した保全設計の取り組みを行っている。
同社がMADeを導入した背景には、船舶業界ならではの事情があった。以前よりも機器のデジタル化が進み、故障修理は専門家でなければ不可能になっている。そのため、故障した場合は訪船前に故障原因を特定し、港に船が停泊している間に修理を完了する必要がある。古野電気のエンジニアは、交換が必要だと想定される、全ての部品を持って訪船しなければならない。
古野電気 情報システム部 ITソリューション室 情報通信基盤開発担当課長の田村進司氏は「これではわれわれが保守部品在庫を多く抱えることになります。また、人材確保が難しい状況で、正しく修理をできる人材を育てるのは時間もコストもかかります。製品自身の技術的知識や経験がないと故障の特定と修理はできません」と説明する。
保守体制改善のために取り組んだのが、交換部品単位での故障検知と、保守レベルの向上、そして製品ライフサイクルの適切な運用だ。具体的には、各交換部品にMADeでモデリング検証を実施する。実際にモデルとなる機種を選定してモデリングを実施したところ、保全設計をする上で実際の回路図とは異なることを体感したという。
田村氏はMADeを製品ライフサイクルへ組み込む際の課題として、「PHMの理解」や「社内関係部門へのPHM啓蒙活動」、「定期的なMADeトレーニング」が必要だと説く。「現場にモデル化のメリットを理解してもらわないと、(現場は)『付加作業が増えてしまう』と不満を持ってしまいます。また、作りっぱなしにならないよう、モデルの活用方法を事前に検討することも必要です」(田村氏)
今後は、開発プロセスにもMADeを組み込み、商船で使用される機種に展開することも考えている。また、MADeのシミュレーション結果を基に、エラー出力への変更や、センサーの追加、マニュアル改定、保守コストの予実比較などにも活用していきたいと考えている。田村氏は、「将来的には不具合結果とMADeのシミュレーション結果の比較や、モデル更新プロセスの確立も目指したいと考えています」としている。
航空機整備における故障予知アプローチ
ここまで4つの講演はB2Bで事業を展開する製造業の取り組み事例だったが、コンシューマー向けにサービスを提供する企業の視点から故障予知アプローチを紹介したのが、全日本空輸(以下、ANA)だ。ANAでは約270機のジェット旅客機を所有し、1日に国内便数800/海外便数200を運航している。同社整備センター 機体事業室 機体技術部の長谷川翔一氏は「われわれ航空機エンジニアのゴールは定時出発率100%です。しかし、現実的な目標として定めているのは100%ではありません」と語る。
ANAでもベテラン社員の高齢化による退職や、運航便の増加などで今後さらに人財が必要となる。その課題を解決するために取り組んでいるのが、予知整備だ。航空機に取り付けたセンサーでデータを収集、分析し、故障しそうな部品を先回りして整備する。どのデータを取得し、課題(不具合)を見つけ出すか議論した結果、「航空機メーカーやエンジンメーカーによる対応では後回しにされがちでも、われわれにとっては早期に対応したい不具合を見つけ出す」ことが決まったという。
“メジャー”な不具合は、既に航空機メーカーが対応策を講じている。しかし、ANAのような航空会社と航空機メーカーでは、解決すべき不具合の優先順序が異なるケースが多い。例えば、全世界の空を飛行している自社の航空機全てが対象になる航空機メーカーと、日本を中心に飛行している航空会社の航空機とでは、データを取得する際の飛行パターンや外部環境が異なってくる。長谷川氏は「飛行地域や飛行パターンが異なれば、不具合が発生する箇所も異なります。そのため、われわれがすぐに対応してほしい不具合でも航空機メーカーがタイムリーに対応してくれるかどうかはさまざまです」と説明する。
予知整備のトライアルとして利用したのは、機内に空気を送り込む役割を担う「フローコントロールバルブ」という部品だ。フローコントロールバルブは飛行時間に比例して汚れが蓄積されるため、一定期間でのメンテナンスが必要になるという。
ANAでは、特定の特徴量に着眼してモニタリングした結果、不具合の兆候値を示すデータを詳らかにすることができた。現在は試験段階だが、今後は実際に稼働している飛行機のデータを当てはめ、予知整備に役立てて行きたいとのことだ。
長谷川氏は、トライアルから見えてきた課題として「インフラを含めたデータ準備」「ドメイン知識」「不具合データの不足対策」「生産現場の理解」を挙げた。中でも予知整備の重要性を生産現場の担当者に理解してもらうことは重要だという。そして、「『あと3カ月後に故障しそうなので、交換してください』と言っても、はじめは整備生産計画部門の担当者になかなか理解していただけません。予知整備は、会社全体として取り組むことが大切なのです」(同氏)と語り、講演を締めくくった。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:株式会社電通国際情報サービス
アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2019年7月27日
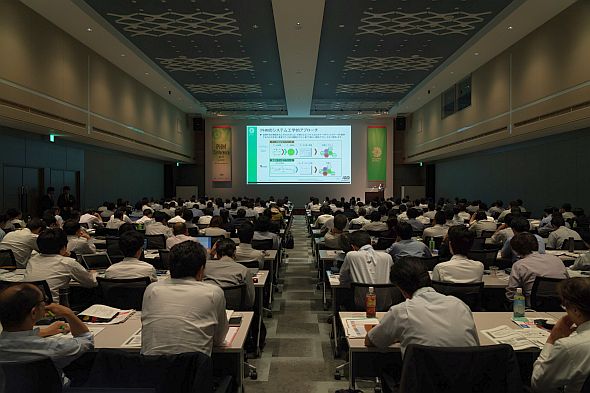 約500人が参加した「PHM Conference 2019 in JAPAN 〜 様々な取り組み事例に学ぶ 〜」の会場の様子
約500人が参加した「PHM Conference 2019 in JAPAN 〜 様々な取り組み事例に学ぶ 〜」の会場の様子 コマツ 開発本部 ビジネスイノベーション推進部 部長の浅田寿士氏
コマツ 開発本部 ビジネスイノベーション推進部 部長の浅田寿士氏 ダイキン工業 テクノロジー・イノベーションセンター 主任技師の小倉孝訓氏
ダイキン工業 テクノロジー・イノベーションセンター 主任技師の小倉孝訓氏 明電舎 ICT統括本部 企画部 主管技師の伊藤博起氏
明電舎 ICT統括本部 企画部 主管技師の伊藤博起氏 古野電気 情報システム部 ITソリューション室 情報通信基盤開発担当課長の田村進司氏
古野電気 情報システム部 ITソリューション室 情報通信基盤開発担当課長の田村進司氏 全日本空輸 整備センター 機体事業室 機体技術部の長谷川翔一氏
全日本空輸 整備センター 機体事業室 機体技術部の長谷川翔一氏
