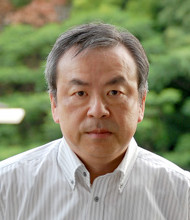乱流シミュレーションを使いこなす:CAE解析とExcelを使いながら冷却系設計を自分でやってみる(13)(4/4 ページ)
CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第13回は、乱流シミュレーションについて解説する。
ラクランジェ表記とオイラー表記
流体シミュレーションの最後に、「ラクランジェ表記」と「オイラー表記」について少し触れておきます。図17に、両者のイメージを示します。
左側のラクランジェ表記は、流体粒子を考えればよいと思います。例えば、t=0[s]の時点で(ξ,ζ,η)にいた流体粒子の、時刻tにおけるx方向変位はx(ξ,ζ,η,t)と表記されます。この(ξ,ζ,η)は、流体粒子の“背番号”(例えるなら野球のユニフォームの番号)のようなものであり、計算が進行しても変わりません。そして、この背番号(ξ,ζ,η)を持つ流体粒子を追い掛けます。背番号(ξ,ζ,η)の流体粒子の、時刻tにおける速度vはvξ,ζ,η(t)と書けるのでしょうか、少し自信がありません。
一方、オイラー表記では、流体粒子を追い掛けません。代わりに、座標(x,y,z)における時刻tの速度v(x,y,z,t)を計算します。
1960年代に米国のある研究所で「コンピュータが使えるようになったので、今後の流体シミュレーションはオイラー表記で行うか、ラクランジェ表記で行うか」が検討され、そのときはオイラー表記を採用する方針となったようです。
ここで紹介した有限体積法は、オイラー表記に基づく手法です。
ラグランジュ表記によるシミュレーションの例を紹介します。図18は、粒子法による計算結果です。一つ一つの粒子を追い掛けていきます。計算には約1時間を要しました。当時、東京大学の越塚誠一先生からソフトを提供いただきました。
粒子法の利点は、自由表面解析を容易に実施できる点です。現在では有限体積法でも自由表面解析が可能になりましたが、粒子法の方がはるかに簡単に実現できます。表面張力についても、粒子間に引力のような力を発生させることで、シミュレーションに組み込むことが可能です。
連載第9回でナビエ・ストークス方程式を紹介しましたが、その中の式9の左辺に移流項というものがあります。この項があると微分方程式が解けなくなりますが、粒子法はラグランジュ表記であるため、移流項の計算が不要となります。
自由表面を持つ流体の挙動について、筆者はサイズによって支配する力が入れ替わると考えています。そのイメージを図19に示します。
流体のサイズが小さい場合、形状を決定づける要因は表面張力になります。その代表的なサイズは、雨粒程度です。例えば、霧やオイルミストなど雨粒よりも小さい場合には、形状が球に近づきます。球に近づくということは、「最小ポテンシャルエネルギーの原理」から見て、表面張力が系を支配していることを意味します。このとき、ポテンシャルエネルギーは「表面張力×表面積」で表され、最小となる形状が球であるためです。
流体のサイズが大きくなると、その形状は球ではなく、さまざまな形になります。これは、支配する力が表面張力から他のものに変わるためです。例えば、図18に示したようなサイズになると、形状は球とは程遠くなり、重力と粘性力によって決定されます。
重力(慣性力)が支配するか、粘性力が支配するかは、レイノルズ数によって判断できます。レイノルズ数の分母は動粘性係数、分子は代表長さでした。図19に単位を記載してありますので、それを見れば分かりますね。
ここでは流体の形について述べてきましたが、固体粒子についても同様のことがいえます。例えば、サイズが大きい雨粒は落下しますが、霧やオイルミストは風に流されて地面になかなか落ちないのは、表面に作用する圧力が重力を上回っているためです。
また、米びつからカップでお米をすくうとき、米粒がカップに付着することがあります。これは、静電気力が表面積に比例し、重力が体積に比例するため、静電気力が重力を上回っていることによります。バレーボールは米粒より密度が小さいものの、サイズが大きいため、その挙動は重力に従います。決して「いやいや、粒の挙動を支配しているのはシュレディンガー方程式なんだ」なんて言わないでくださいね。
乱流シミュレーションについての説明は、ひとまずここまでです。次回は、「熱流体解析」を取り上げます。熱伝達率の机上計算には、利用できる実験式が限られており、見積もりの精度はあまり高くありませんが、熱流体解析では熱伝達をシミュレートすることが可能です。
あっ、そうそう。「オイラ、たまに流体解析をやっているんだが、Y+なんて見たことないや」と思われた方は、お使いのソフトの取扱説明書をご確認ください。 (次回へ続く)
Profile
高橋 良一(たかはし りょういち)
RTデザインラボ 代表
1961年生まれ。技術士(機械部門)、計算力学技術者 上級アナリスト、米MIT Francis Bitter Magnet Laboratory 元研究員。
構造・熱流体系のCAE専門家と機械設計者の両面を持つエンジニア。約40年間、大手電機メーカーにて医用画像診断装置(MRI装置)の電磁振動・騒音の解析、測定、低減設計、二次電池製造ラインの静音化、液晶パネル製造装置の設計、CTスキャナー用X線発生管の設計、超音波溶接機の振動解析と疲労寿命予測、超電導磁石の電磁振動に対する疲労強度評価、メカトロニクス機器の数値シミュレーションの実用化などに従事。現在RTデザインラボにて、受託CAE解析、設計者解析の導入コンサルティングを手掛けている。⇒ RTデザインラボ
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もり
乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もり
CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第12回では、乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もりについて取り上げる。 圧縮性流体の圧力損失を求めて実験値と比較する
圧縮性流体の圧力損失を求めて実験値と比較する
CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第11では、マッハ数が0.003[-]という実験値を基に、層流における圧縮流体の圧力損失を求め、その結果を実験値と比較する。 CAEソフトに仕掛けられたトラップ
CAEソフトに仕掛けられたトラップ
金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。第1回のテーマは「CAEソフトに仕掛けられたトラップ」だ。 連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」の内容と有限要素法
連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」の内容と有限要素法
金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。連載第2回では本連載の「あらすじ」と「有限要素法」について取り上げる。 解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと
解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと
連載「CAEと計測技術を使った振動・騒音対策」では、“解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと”を主眼に、CAEと計測技術を用いた機械の振動対策と騒音対策の考え方や、その手順について詳しく解説する。連載第1回では、本連載の趣旨、振動対策や騒音対策が必要となる場面などについて取り上げる。 設計者なら一度はやってみたい形状最適化、お金をかけずにどこまでできる?
設計者なら一度はやってみたい形状最適化、お金をかけずにどこまでできる?
原理原則を押さえていれば、高額なソフトウェアを用意せずとも「パラメトリック最適化」「トポロジー最適化」「領域最適化」といった“形状最適化”手法を試すことができる! 本連載ではフリーのFEM(有限要素法)ソフトウェア「LISA」と「Excel」のマクロプログラムを用いた形状最適化にチャレンジする。