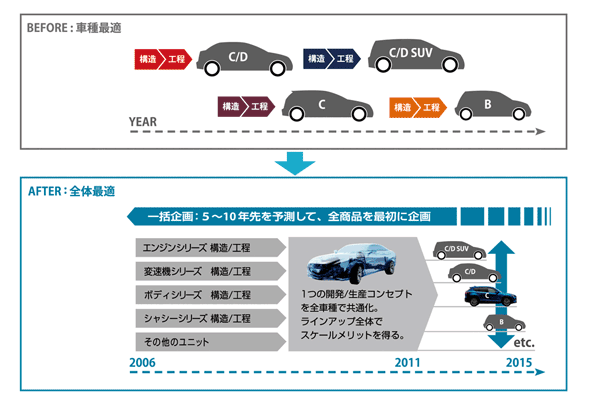先手を打ったマツダの製造業革命――真の“コンカレントエンジニアリング”がもたらす新しい価値:井上久男の「ある視点」(11)(1/4 ページ)
それは、生き残りをかけた究極のイノベーションであり、産業史にも残るものであろう。マツダが次の飛躍に向けて進める大胆な開発・生産プロセス改革の深層を追った。
マツダが「究極のコンカレントエンジニアリング」を推進している。ハイブリッド技術を使わないで内燃機関の進化によって日本で初めてガソリン1リットル当たり30km(10:15モード)の燃費効率を超えた「スカイアクティブエンジン」は、実はそのたまものなのである。筆者はその誕生プロセスを取材し、日本の産業史上に残る意義深い取り組みだと感じる。
マツダは水面下で2006年から全社的に取り組み始めたプロジェクトを総称して「モノ造り革新」と呼ぶ。「モノ造り」というよりも「新たな価値造り」と呼ぶ方が適切かもしれないほど、設計や生産などの部署が大胆に発想を転換し、これまでにないような自動車の開発・生産のシステムを編み出した。「スカイアクティブエンジン」の誕生は、その活動の結晶であると同時に氷山の一角でしかない。
「モノ造り革新」は2つの大きなコンセプトから成る。それは「コモンアーキテクチャ」と「フレキシブル生産」という考え方である。この2つが密接に絡み合うことで成果につながる。プロジェクトの推進役である金井誠太副社長、「スカイアクティブエンジン」を担当した広瀬一郎パワートレイン開発副本部長兼エンジン設計部長へのインタビューなどをベースにその構造を解説していく。
個別最適設計からの脱却を目指す一括企画
「モノ造り革新」はマツダ社内では通称「一括企画」とも呼ばれている。2006年にマツダは2015年度末までにどんな会社になるべきかの長期プラン策定に入った。そのプロセスで商品に織り込むユニット(エンジンや変速機やシャシーなど)の技術レベルについて2015年に世界一の水準に到達させるとの高い目標を定め、全車種を新しい技術に塗り替えてしまうことを決めた。
2011年に発売する新車から新技術を適用することも決めた。しかし、マツダは資金など経営リソースが潤沢な会社ではない。これまでのように個別車種ごとに企画→開発→生産といったプロセスを踏んでいては予算や人手が足りなくなるという現実的な課題もあった。まして個別車種ごとの開発では開発期間も短縮できず、コスト削減にはつながらない。
これまでの日本の自動車メーカーでは、車種ごとに開発責任者が存在し、その責任者がデザインや技術やコストなどの管理を総合的に束ね、開発が終わるころにバトンタッチして次モデルの開発をゼロに近いところからスタートさせる「個別最適型」の開発が主流である。共通化にしても前モデルの設計図の一部を流用するといった程度であった。
日本製造業は、個別最適の設計を得意としてきた。一つ一つの部品を調和させながらきめ細かな品質を「宮大工」のように造り込んでいくイメージで、これを「すり合わせ型モノづくり」と呼び、「メイド・バイ・ジャパン」の競争力の根源の一つとされた。
しかし、新興国市場の拡大により顧客の多様な価値観に素早く対応する商品開発力が求められるようになり、「すり合わせ型モノづくり」はスピードとコストの両面で相対的な優位性を失いつつある。これは「すり合わせ型モノづくり」の是非というよりも、日本企業の多くの経営者が、時代の潮流の変化を見定め、仕事の仕組みを変えていくといういつの時代にも必要な努力を怠ったことが競争力の低下につながっていると筆者は感じている。
前述したように経営リソースが潤沢ではないマツダは危機感を持ち、発想を大転換して2011〜2015年に投入する全ての新車の企画、開発、生産をいっぺんに重ね合わせていく仕事の仕組みに大きく変えた。故に「一括企画」なのであり、コンカレントなのである。マツダの技術陣や工場は本社がある広島県に集中しており、情報収集やそのすり合わせも素早く行えるという地理的特性も優位に働いたとみられる。
15年時点でも通用する高い水準の技術を使う一方で、コストも安くしなければならない。これまでの常識を否定するような車作りが求められ、ブレークスルーも必要だった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.