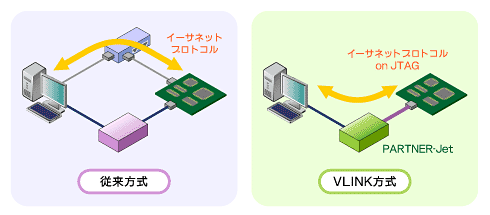業界初のLinux対応ICEが成功した理由:組み込み企業最前線 − 京都マイクロコンピュータ −(1/2 ページ)
京都マイクロコンピュータは「デバッガ」をこだわり続けるICEベンダである。2003年、当時の業界で実現が難しいとされていたLinux対応ICEをリリースし、現在の組み込みLinux隆盛に少なからず影響を与えた。常に3〜5年先の技術トレンドを見据えて開発を進め、下請け仕事は一切やらない。“わが道を行く”希有な存在である。
デバッガで本領を発揮する
西山山麓に抱かれ、京都の中でもひときわ静かな西京区。そこに組み込み開発ツール専業ベンダ、京都マイクロコンピュータ(以下KMC)の本社がある。20年の社歴を持つが、東京オフィスを含めても社員数は10名ほど。規模は決して大きくない。だが、組み込み分野におけるKMCの存在感は、決して社員数では測れないものがある。
1985年、大学を卒業したばかりの山本彰一氏と塚越勲氏、2人の青年が興したのがKMC。いまでいえば、学生ベンチャーのノリに近かった(現在、山本氏がKMCの代表取締役兼CEO、塚越氏が取締役開発部長兼CTOを務める)。80年代後半から90年代初めにかけて、“アルバイト仕事”として一時的に手掛けたPC-9801シリーズ向け拡張ボード(CPUアクセラレータ「Turbo-486」など)が商業的に大成功を収め、PCマニアの中でKMCはちょっと名の知られた会社となった。だが、大手周辺機器ベンダが市場に参入してくると、あっさりと手を引く。自分たちが本領を発揮するフィールドをしっかりと見極めていた。
そのフィールドとは組み込み開発ツール、ずばりいうなら「デバッガ」である。「良いソフトウェアを開発するには、良いデバッガが要る」。創業者2人は根っからのソフトウェア技術者。当時の技術者は、プログラムを作成する際に開発ツールを自作することも多く、デバッガの重要さを痛感していた。
会社設立の3年後、1988年に発売したマルチCPU対応ターゲットデバッガ「PARTNER-T」は、この分野でKMCの名前を知らしめたヒット商品となる。日本で初めて製品化したROMエミュレーション方式のICE(インサーキット・エミュレータ)だった。ここから、ハードウェアデバッグ環境を提供するICEベンダとしての道を歩み始める。1998年には、JTAG(注)専用デバッガ「PARTNER-J」を発表。いち早く「JTAG-ICE」に取り組み始めた。
一般にJTAG-ICEは、従来のフルICEに比べて通信速度が遅いが、KMCのJTAG-ICEはその当時から高速性で知られた。PARTNER-Jは、ターゲットCPUへのダウンロード転送1Mbytes/sを実現(CPUがMN103の場合)。当時から肥大化し始めていた組み込みソフトウェアのデバッグにも耐え得るものだった。東京オフィスゼネラルマネージャの辻邦彦氏はこう話す。「ICEというとハード側のデバッグツールというイメージもあり、実際、ICEベンダの多くはハード寄り。ただ、われわれの製品は、80〜90%がソフトウェアのデバッグで使われている。高速なのでストレスなくデバッグできる点が評価され、機器メーカーのソフトウェア部門やその傘下のソフトウェア開発会社で使われている」。
高速性を生かした「VLINK」と呼ぶ独自の仮想化技術もユーザーから好評だ。ターゲットCPUとホストPCを結ぶPARTNERの通信回路をターゲットとホストを“直結”するための回路としても開放するのがVLINK機能である。これが何を意味するかといえば、ターゲットCPUで動作する映像や音声など各種コンテンツもホストPC上へ仮想的に展開でき、デバッグできるということだ。また、実行状態をチェックするためのログファイルが必要な場合はPC上に作成できるため、ターゲット上にファイルシステムがなくてもよい。同様に、PCのネットワークデバイスを使ってターゲットにネットワーク機能を持たせ、動作を検証するといった使い方ができるのだ。
| 関連リンク: | |
|---|---|
| ⇒ | 京都マイクロコンピュータ |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.