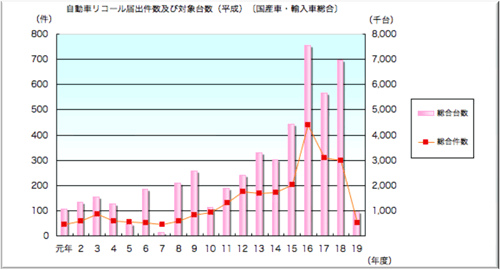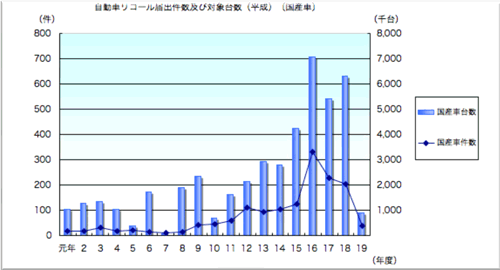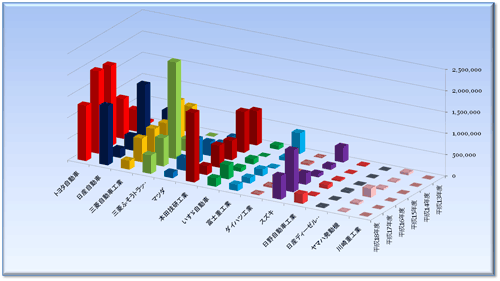メカ設計者たちよ、ニッポンの製造業を救え!(上):エンジニアスジャパン 加藤社長インタビュー(1/2 ページ)
いま、日本の製造業が危ない。それを救うには、従来の生産技術思想をひっくり返し設計初期段階からの品質の作りこみを徹底的にするべきだ
最近、大手製造メーカーが起こした自動車やリチウムイオン電池などのリコール問題のニュースをよく耳にします。いまの日本の製造業が抱えている問題に、機械設計者はどう向き合うべきでしょうか。今回は、エンジニアスジャパン 代表取締役社長 加藤毅彦氏にお話をお伺いしました。
――最近、御社の製品に対して、顧客からはどのような要望が出ていますか?
「製品品質の改善をとにかくしなくちゃいけない!」、そう考えている人たちが増えていると思います。それはすなわち、もっと「性能が高い」「品質が高い」なおかつ「コストが低い」、そんな製品設計を実現しなければいけないということです。
「とにかく、この現状をどうにかしてくれ!」、それには「従来の想定を超えた設計環境が必要」だと考えているようですね。
――日本の製造業は、いま、どのような状況であるとお考えでしょうか。
まさに、危機に直面していると思いますよ?
ここでまず、日本の車と輸入車を併せたリコール台数を示したグラフ(グラフ1)を見てみましょう。
次に、日本車だけのグラフ(グラフ2)を出してみましょう。
さて、上の2つのグラフを見比べてみてください。
ほとんど数が変わらないのです。つまり、世界中の自動車のリコール台数中ほとんどを日本車が占めているということになります。
「後でメディアにたたかれるのを避けるために、問題が出たら早めに発表してしまおう」という意識の表れも、確かにあるのかもしれません。以前には「リコール隠し事件」のように発展してしまうようなこともありましたから。
さらに、グラフ3の数字を見てください。製品の高品質イメージが強い企業でさえもリコール台数が約100万台以上――件数で見ると、案外多くはない感じがすると思いますが、車の場合、1件のリコールで、そのロットすべて、つまり何十万台何百万台が補償対象となってしまう可能性があります。さて、車1台に対し、リコールへの対応で何万円かを掛けたとしたら、それだけで数百億円のリコール対策費用が必要になるでしょう。
――どうして、このようなリコールが多発するような状況になってしまったのでしょう?
大学教授の方々や製造業に携わる方々が、製造・設計に関する論文などを発表したりメディアで評論したりしていますが、「品質向上を図るには設計が大事だ」といいながら「現場力が大事だ」という結論で締めくくってしまうことが多いのが実情です。また、技術系の新聞社や雑誌社、Webメディアが、製品の品質改善のカンファレンスを開けば、その参加者のほとんどが生産技術部門の人たちだといわれています。
つまり日本では、「『品質』といえば『生産技術』」だと思い込んでいる人たちが多い」ということになると思いますが、これが問題だと思います。
このような考え方による設計・生産プロセスでは、作業負荷が後工程に来るほど多くなってしまうのです。最近では、市場から要求される納期がどんどん短くなっている傾向なので、負荷はさらに後ろに掛かることになります。
設計製造のカンファレンスなどで「コンカレントエンジニアリングにより設計期間を1年に短縮しました!」といったような発表をしているのをよく見掛けますが、その中身をよく見れば、設計・生産プロセスを変えずに、単に工程(時間)を無理やり圧縮しているだけのことも多々あるようです。
私がこの業界に入ってから二十数年たちますが、その間コンピュータの能力は、ものすごい勢いで上がっていきました。でも、設計・生産プロセスは、20年前といまと比べて、大して変わっていないのです。
――現場では何が起こっているのですか?
図面の寸法に公差が入っていますよね? しかし、私が実際に見てきた限りでは、この公差に、現実の材料のばらつきや生産工程の誤差などがぜんぜん考慮されていないケースが多かったのです。「過去ずっとこの公差を使ってきたし……」 と。昔と比べ、当然、生産するロボットも、材料も違っているのですから、公差だって見直さなくてはいけないはずなのですが。
設計時点で分からないことは、実験で検証することになります。しかし、実験結果の誤差はかなり大きく、再現性がないものです。できることにも限界もあります。「部品『内部』のねじれ具合や応力」まで正確に測定して数値化することはできません。せいぜい部品の表面にひずみゲージを張って測定して数値をサンプルし、それを基に関数を駆使して予測するぐらいが限界でしょう。
また、実際の使用環境にきちんと合わせた検証実験をしようにも、限界があります。人間の手によって実際に、製品を深海や宇宙に持ち込んで「さあ実験しよう!」というのは、さすがに難しいですよね? ライフサイクル特性の評価も同様のことがいえますね。例えば、ある製品を「10年間使ってもらおう」としたら、本来すべての使用環境、使用パターンで「人間が実際に10年間使って実験」するべきでしょう。それは現在の多様化された市場では不可能に近い状況ですし、そんなことをまともにやっていたら、当然、マーケットに間に合わなくなります。
少しでも実験結果の再現性を取ろうとするために、沢山のサンプルを使って実験しようとすれば、当然、その分コストがかさむことになります。例えば、車の試作品数千台を衝突実験させようとしたら、相当な額になってしまうわけです。
実験の限界をカバーするのが、CAEなどによる解析技術なのですが、多くの企業内において、解析専門の技術者の手が十分に足りていない状況です。また、設計者自らで解析は行わないことが大半です。設計者は、解析までする時間の余裕はないと思っているでしょうし、解析に関する知識も乏しいのが通常です。
そうして、設計時の実験や解析でも検証しきれず、あふれてしまった問題は試作段階で解消しなければならなくなります。結局、製品仕様を満たして出荷するために、生産技術部門が不具合を必死になって修正する羽目になるのです。
さらに、組み立てでもばらつきがでますよね? 例えば、うまい人が組み立てれば品質が高いけれど、少し手を抜いて組み立てれば品質は落ちていきます。
そしてとうとう、問題を解消し切れないうちに、仕様や規格に対して妥協して市場へ出荷してしまう場合すらあるというわけです。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.