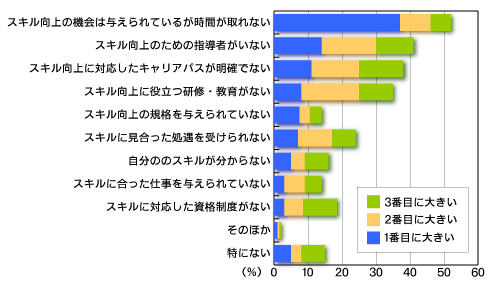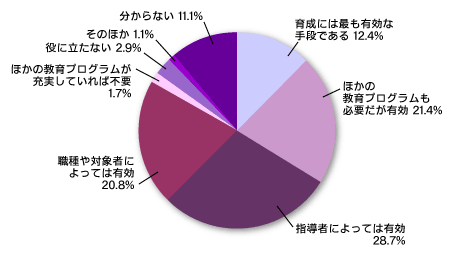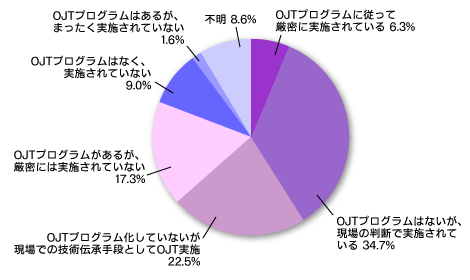場当たり的なOJTを体系的な教育カリキュラムへ:組込みスキル標準(ETSS)入門(4)(1/4 ページ)
現場任せのOJTだけでは、効果的な人材育成は望めない。業界全体にとってメリットのある教育カリキュラムの整備が必要である
人材育成の現実
本連載の第1回で紹介したとおり、開発の現場では「人材が足りない」「スキルが足りない」といった悲鳴が上がっています。これらを解消するために、組み込み分野における人材育成を実現する必要があります。ところが、組み込み分野を取り巻く状況や特性に起因する課題が存在します。
組み込みシステム製品に使われている技術要素は、高品質の追求や競合製品に対する優位性確保などの理由によって、新技術が積極的に導入され続けています。その結果として、製品に組み込まれる技術要素はとても早く陳腐化し、技術者は常に新技術習得に取り組まなければならない状況となっています。また、大規模化した開発に対応するために、プロジェクトマネジメントや開発プロセスなどのソフトウェアエンジニアリングの本格的な導入や習得の必要性が、組み込み分野においても高まってきました。
その一方で、これまで大規模化や複雑化が進む開発を短期間で行うため、個人の負荷を上げることでしのいできました。技術者個人の負荷増大は、人材育成のために確保できる時間が相対的に短くなることにつながります。
教育の実態は現場任せのOJT
2005年に経済産業省が実施した「組込みソフトウェア産業実態調査」における「自己のスキル向上に関して問題と感じている点」という問いに対して、「スキルの向上の機会は与えられているが時間が取れない」という回答が最も多く現場の技術者から寄せられました。
これまでは、現場に配属され実務を通じて教育するOJT(On the Job Training)型の人材育成が大勢でした。OJT型は実践的な技術を習得できるという面で大きな効果があり、またOJT以外の教育方法では習得が困難な技術やスキルも数多く存在します。
しかし、実践的である半面、習得できる技術の範囲やレベルがほかの教育の実施形態と比較して限定的になる傾向があることも否めません。無計画に行われたOJT型の人材育成では、習得できる技術の範囲やレベルは指導者となる先輩社員の力量に大きく左右されます。前出の実態調査では、「部門でのOJTの有効性について」の問いに対して約半数の技術者が「指導者によっては有効(28.7%)」「職種あるいは対象者によっては有効(20.8%)」と回答しています。
OJT型の人材育成は、「どのような人材を、どのように育成するのか」を明確に計画し、適切に運営することで本来の効果を発揮します。場合によっては、指導者にOJTを実施するための訓練を行うことも必要です。現状では、計画的にOJTが実施されていないことが前出の実態調査の結果から読み取れます。「部門でOJTはどのように行われているか」という問いに対して、「OJTプログラムに従って厳密に実施されている」と回答した技術者は6.3%にすぎず、ほとんどのOJTは配属先の現場任せになっているようです。
組み込み開発に即したカリキュラムの不足
組み込み分野における人材不足が課題化されているにもかかわらず、教育機関(大学や専門学校など)や教育サービス企業において、開発に即した教育カリキュラムが少ないのが現状です。その理由に、「カリキュラム開発の難しさ」があります。
組み込み分野には多種多様な技術が存在し、開発対象の製品分野などによって取り扱う技術分野も異なります。業界横断的に利用できる標準的な技術やスキルの体系がこれまでなかったために、教育の技術範囲およびレベルの定義や指定などが正確に伝達できませんでした。
また、既存の教育カリキュラムを活用するにしても、研修カタログなどから読み取れる数少ないキーワードから目的とする人材育成が実現できるカリキュラムであるか否かを判断しなければなりません。教育カリキュラムの供給者と受講者での間で正確な情報や意思の伝達が行えないことは、「期待した技術内容が含まれていない」「不要な教育内容が多く、時間の割には得るものが少ない」といった不満や不信につながります。教育カリキュラムに対する期待が低ければ、受講者は集まりません。受講者が集まれなければ、教育を供給する側はカリキュラムを開発するモチベーションを維持することが困難となります。
これらは、教育機関においても同様のことがいえます。教育機関で開発にかかわる教育を実施していたとしても、その内容を就職先となる企業が適切に理解し評価することはほとんどありません。また、企業側から教育機関に対して、具体的に「どのような技術を持った人材を輩出すべきか」といった提言がなされることもほとんどありません。結果として、教育機関は企業が望む教育を十分に把握できないために試行錯誤し、企業は教育機関で教育済みの内容を、就職後に再度企業内で教育し直すといったムダが生じます。
もし、就職先の企業が教育機関の教育カリキュラムを適切に評価し、そのうえで企業として必要な技術やそのレベルを正確に教育機関に提言できれば、学校教育から企業教育の間にシームレスな人材育成が実現できると考えています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.